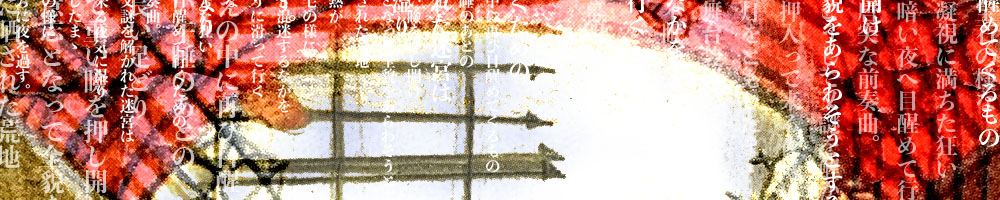
2020/08/3
『崖の上の家:母の声、父の気配』
序章
私が長く住み、そこで成人となった西片町の家は父と母の家であり、やがて私がそこから出ていく家だった。私は1961年にアメリカへ留学のためにそこを発つったので、西片町の家はそこで終わりを遂げた家となった。留学から帰った時、父と母は近くに家を建ててそこに移り住んでいたのだ。その新しい父母の家に整えられていた私の部屋は、家族を連れて帰国した私には、狭くて住めなかった。私の西片町の家は、文字どおり1961年でなくなっていたのである。
現在も私は西片町に住んでいるが、それはずっと後になって、年老いた母の近くに住むために建てた家であり、私の子供たちが生まれ育った家ではない。その家に住むようになって、初めて私は西片町という場所になぜ連れ戻されたのか、その本当の意味を知りたいと思うようになった。アメリカから帰って以来、私は家を探し続けていたが、どの場所も母の了承が得られず、結局母の近くに住むことになったのだが、それは本当の理由ではなかったように思い始めたのだ。私の心の底に、西片町は大きな痕跡を残したままで、かつての家は空白の空間としての心の風景にたち続けていたのである。
西片町に住むことは私の記憶の呼び戻しであると同時に、そこに住んだ作家たちの書いた作品の中の「場所」との遭遇でもあった。そして何よりも、その頃の、若かった父と母の生活の姿との記憶の中での再会を果たすことでもあった。西片町は、このように私自身の大人への成長の日々の記憶を中心に三つ巴の想像の世界へ引き込んでいく場所となった。
私が中学生になった頃から住み、現在もその界隈で暮らしている西片町は、本郷通りを弥生町と言問通りの交差点を過ぎてすぐに左に折れる旧白山通り、現在の国道17号線へ入って、その関越に続く通りの左側に広がる地域である。
西片町というのだから東片町も昔はあって、現在は向丘に統一されて地名としては使われていない。東片町は旧白山通りと本郷通りの間にあるあまり広くない地域で、そこの一軒家の一階を戦後間も無く父と母が借りて住み、3年ほど遅れで私たち姉妹も疎開先から移って一年あまりそこから小学校へ通った。1951年、中学に入った頃に、東片町から西片町の家に住むようになり、私はその西片町の家で中学から大学、そしてアメリカへ留学する1961年まで大学院時代もそこで暮らした。
西片町と東片町はどちらも空襲に焼け残った場所だが、そもそもが大変雰囲気の異なった住宅街で、戦後すぐの頃まではその違いが歴然としていた。東片町は本郷通りと旧白山通りの間のかなり狭い地域で、門や庭のない小ぶりな家が軒を並べていた、いわゆる庶民の住む街だった。東片町から本郷通りに出ると、そこは追分町というところで、現在は東大農学部、そして言問通りを挟んで広がる、東大キャンパスとなっている加賀百万石の大名上屋敷の生業に関係する人々が住んでいた地域だということがわかる。追分町は馬係や鍛冶屋などの職人が住んでいた場所らしいとも思うが、実は追分宿場で、東京から出て初めての宿場だったという。草野心平さんのおでん屋「呑気」が、つい最近まであったので、知る人も多いと思う。
私の父水田三喜男は1946年の新憲法の下での最初の全国総選挙で衆議院議員となり、東片町の焼け残った一軒家の一階を借りてそこから国会へ通い始めたのだった。1946年当時東京は焼け野原のままで、すぐに住める家を探すのは大変だったという。二間と台所、風呂のついた狭い家だったので、私たち姉妹は父の選挙事務所のある館山市の家に祖父母とともに戦後3年近く父母と離れて暮らしていた。
当時本郷通りには一九番という都電が走っていた。巣鴨や王子駅から日本橋まで、たまには新橋まで行くこともあったように思う。バスは荒川土手から東京駅北口までの路線を走っていて、こちらの都バスは今でも運行されている。小学校の六年生の時に東京の父母と一緒に暮らすことになり、私はこのどちらかに乗って、御茶ノ水まで行き、そこから省線の中央線に乗り換えて、四谷の小学校に通った。
東片町から本郷通りを越えると、弥生土器の発掘で有名な弥生町を言問通りに沿って下り、根津、池の端、谷中と低地になり、そこからまた上野へ坂を登って行く。
西片町は東片町に比べて広い地域であり、そこから坂を下って、現在は白山通りという、巣鴨、駒込方面から日比谷まで続く、低い土地になる。そこから現在の小石川植物園へ向かって、また坂を登って行くので、白山通りはおそらくは川の流れた谷間であったと思う。西片町は福知山藩の藩邸だった場所で、藩校の誠之学校があり、明治以後は公爵となった阿部邸があったところである。現在も誠之小学校、阿部公爵邸の一部が阿部公園、や阿部幼稚園などとして残っている。西片町は東大のあるためもあって、医者や学者の街として知られてきていて、上田敏や夏目漱石、太宰治などの作家も多く住んでいた。
西片町と隣接する街は東大前の地域が森川町と言って侍や職人が住む場所であった。森川町の地名は東片町や追分町と同様に今では使われなくなっているが、明治に入ってからは、旅籠屋や下宿屋などが多くあり、石川啄木、今東光、徳田秋声などが住んだ界隈として知られている。「落第横丁」は今でも健在だが、肉屋、魚屋、八百屋などはもうすっかりなりを潜めてしまって久しい。私はそこのマンションにも子供達とともに住んだことがある。
本郷通りは東大前を御茶ノ水、秋葉原へ向かって、日本橋まで続くが、途中の本郷三丁目あたりからだんだんと緩やかに下り坂になっていき、本郷台地と呼ばれる大地の地形が区切りを見せる。本郷三丁目の角には「かねやす」という服飾雑貨屋があり、「本郷はかねやすまでは江戸のうち」と言われて、江戸の街はずれであったことを表している。秋葉原、広小路、淡路町、岩本町は台地ではなく低地で、いわゆる下町であり、商人や問屋街、そこから茅場町へ進めば金融街となっていく。
一方の本郷台の境は西片町から国道一七号線の旧白山通りと平行に走る、本郷通りを白山上、そして駒込、西ヶ原あたりまでである。白山上からは急な下り坂になって白山下へ出て、現在の白山通りを、後楽園や水道橋、神田神保町へと続き、そして、白山上から反対側は谷中、鶯谷へと隅田川へ向かって急降下していく。
本郷台は東京の台地の中でも広く、また文化的にも江戸や東京の中心的学問文化の地だったが、現在でも東京大学、六義園、湯島聖堂、上野博物館、芸術大学、 上野寛永寺などが昔のままの姿で残り、根津、谷中の寺町、隅田川に続く下町がそれを取り囲んで、江戸時代の地形と雰囲気を残している。
衆議院議員になった父がどのような理由で東片町に仮住まいの場所を見つけたのかは聞いていないが、疎開前には田端や千駄木から日暮らし坂を登った渡邊町というところに住んでいた関係で、本郷は焼け残った区域の中で、全く見知らぬ場所ではなかったからではないだろうか。
とにかく狭い間借り暮らしの、その二間の家に、中国から引き上げてきた父の弟も一時身を寄せていたので、私たち姉妹が住むようになっても、とても家族で住めるような環境ではなかった。しかし、そこから父は国会まで、白山下の低地に降りて日比谷まで行く都電35番か37番に乗って、毎日通った。
私は東片町の家に、小学校の5年生の終わりから6年生の終わりまでの一年とちょっとしか住まなかったが、その一年は、日々の生活の細部まで鮮明に記憶に残っている。その生活の中心には若い父の姿がある。
父は戦争責任やレッド・パージで多くの政治家が政界から排除された戦後政治で、一年生の時から、党の様々な役目を担う地位に付いていた。41歳という若さであったし、占領下の日本の政治は占領軍の指図を受ける支配下にあったので、GHQに行くことも多かったのだと思う。帰ってきた父が浴衣に着替え、小さなちゃぶ台の脇にその大柄な体を横たえている姿は今でも目に焼き付いている。
西片町の家に移ってからは、父は来客とはいつも碁を打っていて、私のコーラスの友人たちの東大生が幾人も家に遊びに来ていた時も、彼らを捕まえては碁を打っていた。母の話によると、結婚前の父は、大学を卒業して失業していた時も、いつも同郷の人や知り合いの人たちが下宿に来ていて、ご飯を食べたり、碁を打ったりしていたという。その頃の物や見かけにこだわらずおおらかで、見栄をはることのないありのままで悠々としている若い父の姿に、母の両親も、そして周りの人も、すっかり魅せられていたと、母は言っていた。
父は千葉県安房郡曽呂村西という山の中の小さな村の、小さな地主で村長の8人兄弟の三男で、大学卒業後は家からの仕送りをあてにすることはできなかったので、おそらく下宿生活は貧乏生活だったに違いない。山村の家で、子供達が中学以上の学校へ行ったのは父の家だけだったそうで、京都での下宿生活には父の一番上の姉で、千葉県の大地主に嫁いでいた叔母からの仕送りがあったのだと聞いている。男の兄弟は全て大学へ行き、姉妹は女学校で勉強させてもらったのだから、教育にかける期待を父の父母は明治人として強く持っていたに違いない。父の生まれ育った曽呂村の小学校は父の生家からは八キロも離れていて、小さい子供たちが通うには遠すぎるので、四キロほど離れたところに分教場が建てられたが、それは明治八年のことだったから、房総半島の突端の寒村にまで、明治の教育法令は確かな成果を上げていたことになる。
東京での下宿暮らしに慣れていた父は、東片町の借り間生活などに驚いたりめげたりすることはなかったに違いない。吉田政権の、身分出自や教養のある政治家の中にいても、いつも野人の気取らない自分のままでいる姿について、私はのちに同じ政治家の方から聞いたことがあった。しかしその中でも、GHQでの交渉から帰って来た時の父は疲れている様子がありありとしていた。私は父が文句や愚痴を言うのを、また弱音を吐くのも聞いたことがないが、うまくいかないことがあったり、嫌なことがあったりしたのであろう時、父はよくちゃぶ台の脇に横になって、そのまま寝てしまうことがあった。
その頃の父は酒豪と言われていて、よく家でお酒を飲んだが、失意の時はあまり酒を飲まなかった。一人で酒を飲むことはなく、酔うと朗らかになり、お腹を出して、腹づつみを打っては母に嫌がられていた。いつもにこにこして穏やかな温顔の父が、黙って寝てしまう時には私たち家族は、敏感に父の苦労を感じ取っていたのである。
父は自民党の役職だけではなく大蔵政務次官にもなった。大蔵省はその頃は四谷の仮り事務所で、父が出省のついでに私を学校へ送って言ってくれたことがあった。たった一度であったが、キリスト教の厳しい学校だったので、私は校長先生から呼び出されて叱られた。当時は車を持つ家族は少なく、何か偉そうに見えたのに違いない。その時、「蛙の子は蛙だから、政治家の子は政治家のように振舞う」と言われたことが、今日まで忘れられずに覚えている。二間の借り家に住んで、占領軍に卑屈な思いをさせられては黙って寝ている若い父の豪放な姿を、私はその言葉で初めて、可哀想に思ったのだった。
しかし、父には「可哀想」と言う言葉は少しも似合わなかった。どんなに不当な扱いやひどい目にあっても、悪意ある中傷に対しても、自尊心を傷つけられることがなく、変わりなく平然としている。自分のためにお金をつかわず、贅沢や見栄を一切はらず、カッコをつけず、浴衣を裏返しに着たままで新聞記者の人たちと会ったり、イワシ好きの粗食で、家での食べ物についての注文や不満を一切言わない、人の悪口を言わず、秘書やお手伝いさんたち、娘たちにも小言を言わない父の一貫した生活態度に、可哀想と言う感情や言葉は不要なのだった。
西片町に移ってから、私は中学生、高校生として、自分の部屋を持ち、物事を考えるようになっていく過程で、いつも東片町での、終戦直後の父や母の姿を原点として思い出すのだった。質素な官僚の家で育った母もまた贅沢な暮らしを望んだりすることはなかったが、父母にとって、敗戦後の暮らしは、さぞ屈辱的なことだったのではないだろうか。ましてや占領下の日本にあってはである。西方町の家は決して広くはなかったが、東片町の家とは比べものにならない、瀟洒な数寄屋作りで、庭に古い蹲のある、戦前の趣味の良い人が住んでいたに違いない趣のある家だった。
私たちが仮住まいの東片町から、旧白山通りを越えた西片町に移り住んだのは私が中学一年生の一九五〇年だった。その家の隣には大きくて立派な家があり、それは占領軍に没収されて、アメリカ人の中佐夫妻が住んでいた。その家の主人が息子のために建てたというのが私たちの家で、家自体も庭も小ぶりで敷地も親の家の三分の一くらいだったのではないだろうか。西片町十のろの一七という番地で、その先の十のろの七というところは漱石が『門』を書いた家のあるところである。私たちの家の裏は崖になっていて、その下は丸山福山町、樋口一葉が住んだ崖の下の、いわば「陽の当たらない町」が広がっていた。
崖に突き出た部分の二階の部屋が私の部屋で、そこから、崖の下に広がる町、白山通りを超えて小石川植物園の森、新宿まで見渡せた。そこで私は大人になっていく時間を過ごしたのである。
このエッセイは、自分の姿を記憶の中に辿る自伝的なエッセイであるが、同時に、私が知っている若い父と母の追憶であり、そしてさらに、西片町という場所を流れる文化的な、あるいは文化の深層といってもいい記憶を、戦後の時代の中で辿ってみる試みも含んでいる。その記憶を蘇らせる場は「家」であり、家は私だけの内密な夢想の場でありながら、都市や街の記憶の中に立ち続ける歴史の場でもある。
東片町、追分町、森川町、そして何よりも西片町は、多くの記録を持っていて、今でも散策の人たちが絶えないが、私の記憶の中での最初の家、田端の家があった渡邊町界隈は、あまり多くの記録を残していない。そのためもあって、2歳半ごろから疎開先の房州勝山町へ移るまでの幼女期の数年を過ごした田端の家は、私の生まれた家に等しい、文字通りの夢の家である。この家は3月10日の東京大空襲で36発の焼夷弾を落とされ、一瞬のうちに跡形もなく消え去った。
序章
終わり
2020/06/18
崖の上の家:第五章:東片町時代
衆議院選挙当選後、父母は東京に住むようになった。私たち姉妹は祖父母とともに館山にそのまま住んで、私は小学4年生に、姉は中学2年生になって、館山市のそれぞれの学校へ行った。父母は本郷の東大前の東片町に家を借りて、父はそこから国会へ出かけたのである。3月10日の大空襲で田端の家は全焼したし、5月24日の大森地域の空襲で祖父母の家も焼けてしまったので、東京に住むには家を借りなければならなかった。1946年、東京は復興もまだ始まらず、焼け野原のままで、空襲を免れた地域で借りることのできる家は大変少なかった。国会議員の宿舎などもなく、父は何としても東京に住む場所を必要としたのである。特に台東区や上野、田端付近は3月10日の東京大空襲ですっかり焼け野原となっていた。一晩で10万人が死ぬと言う凄まじい空襲の爪痕がまだ生々しく残っている地域でもあった。国会に近い場所に住むとなるとやはり土地勘のある文京区あたりの焼け残った場所を選んだのだと思う。東片町の家の一階の二間を借りるのがやっとだったのだろう。二階には女性が一人住んでいた。
母は私たちを東京に連れてきては銀座通りと有楽町の中間あたりにあったフルーツパーラーでアイスクリームやプリンを食べさせてくれたが、借り家には泊まっていくスペースがなく、日帰りで館山へ帰るのがいつもだった。両国駅まで母が送ってきて、そこから席が取れないこともあった内房線に乗って姉と二人で館山へ帰るのだった。その頃の汽車はものすごい混み方だった。
有楽町界隈は戦災を免れた盛り場で、有楽町駅のガード下には焼き鳥屋やカストリなど酒を飲ませる屋台がひしめき合っていたし、その頃ストリップショーをしていた日劇のある数寄屋橋から日比谷公園までの通りも屋台がびっしり立ち並んでいた。銀座四丁目の服部時計店あたりには進駐軍のためのPXがあって、銀座通りには女性連れのアメリカ兵が目立っていた。その銀座通りも新橋の方へ向かっては闇市が立っていたし、反対方向の日本橋から三越百貨店を通り、神田や須田町、岩本町、そして本郷通りに入る秋葉原近くまで、道の両側に屋台がびっしり出ていて、白い服の傷痍軍人がそこ、ここに立っていた。
須田町から淡路町、神田神保町、そして皇居のお堀端を経て靖国神社を通り、新宿へと続く靖国通りは空襲から逃れた地域だったが、中でも本屋街の神保町はアメリカ軍の空襲マップから意図的に削除された保護地域だったとのことである。日本美術研究者のラングドン・ワーナー(Langdon Warner)博士が皇居、上野博物館、神田神保町、御茶ノ水などを保護するように必死でアメリカ政府に働きかけたと言うことである。彼はのちにアメリカで初めての日本美術学科をハーバード大学に設立したことで知られている。
旧加賀藩屋敷跡に立つ東京大学は、須田町、岩本町、淡路町、駿河台、小川町、神保町と続く低地を走る大通りから、これも道幅の広い大きな坂を登って、御茶ノ水で外堀を超えた先に広がる本郷台地にあり、その広い台地一帯は戦災に会わないままだった。東京大学の裏門からは上野池の端、根津、谷中、千駄木、日暮里から隅田川へ急な坂を下りていき、その途中で上野博物館、芸大、西洋美術館などのある上野の山がまた狭い台地の一画をなしていた。本郷台地は隅田川と皇居の外堀までの間に位置する、いわば、江戸の街外れ、江戸の行政地域の境に当たる地域に位置していて、その中央を走る本郷通りが、日本橋から昭和通りで秋葉原まで来て、そこから神田明神、湯島聖堂、本郷三丁目から東大赤門、正門、農学部(旧一校)、白山上、団子坂上から駒込、王子へと続いていく江戸一番に広い台地である。
本郷台地一帯はこのように加賀100万石屋敷を中心として、大名屋敷、上野や、湯島聖堂の学問所、谷中の寺町、湯島神社や根津神社、神田明神などに囲まれた坂の多い街だった。政治、商業地域からは離れた教育や宗教の区域と言っていい。戦災に会わなかったので、戦前の東京の雰囲気、そしてさらに江戸の風情が残っている街並みが続いていた。
東片町は現在東京大学と農学部のキャンパスを隔てて隅田川へと続く言問通りと本郷通りが交差する弥生町を少し過ぎて、本郷通りから分かれて中仙道へ続く旧白山通り(現在の国道17号線)と別れて、駒込へと続く本郷通りの間に位置する狭い地域で、本郷通りに面した追分町から細い道を入った一帯だった。追分町と言うからおそらくは加賀藩の馬の世話役係たちが住んだ一画なのだと思っていたが、そうではなく、日光へ続く御成街道の本郷追分宿のあった場所で、栃木へと続く道にはいくつかの追分宿があるが、その江戸での最初の馬休め、足休めの宿場だったそうである。それほど、本郷は江戸の街外れ、町街外への第一歩の場所なのだったのだ。
私たちが住み始めた頃には草野心平さんが「呑ん兵衛」というおでん屋を出していたので、追分町は作家や詩人たちには馴染みのある場所だったらしい。草野心平さんは、ずっと後になって父が創立した城西大学の学歌の作詞をしてくれた人なので、東片町時代を思い出すと、何か縁があったのだと感じたものである。その頃父は将来大学を作るなどとは考えもしなかったであろうし、私たちもまた、飲み屋とも詩人とも関わりがなかった。1964年オリンピックも終わって日本の国際社会への復帰が目に見えてくる頃創立された城西大学の学歌に草野新平さんがいいと父が言ったということを知って、あの短い東片町暮らしの中で、父は草野心平さんの詩についても心を打たれていたのだと思った。父もまた文学青年として青春時代を過ごしたのだろう。
東片町は現在向ヶ丘という地名一帯の一部になっていて、東片町と言う名前は残っていないが、西片町の対になる地域としてつけられた地名であるだろう。片町と言う呼び方は、例えば飯倉片町などのように江戸時代にはよく使われた地名だったのだと思う。東片町は西片町とは違ってとにかく狭い地域で、そのほとんどが「しもた家」というのが適当な、門がなく道に面して玄関のある庶民の住居が屋根を並べてたち続く町だった。道からすぐ家に入るのは、時代劇で見る長屋のような感じがした。家は玄関に1畳ほどの畳敷きの間があり、その先に六畳と八畳ほどの部屋があり、短い廊下を隔てて台所があった。八畳間の外には狭い廊下とその先に濡れ縁があって、そこから少し下の家の中がよく見えた。お習字の先生の家だったので、墨の匂いが漂ってきて、それが気持ちよいと母が言っていた。
その家に天津の伯父に勧められて中国の同文書院で勉強をしていた父の末弟が引き揚げてきたのだった。田端の家で私に英語を教えてくれた結伯父の弟で、五一伯父といった。水田家の男の子たちは皆顔つきが似ていて、体の大きさだけが、下に行くに従って小柄になっていったが、皆父に似た柔和な面ざしだった。祖母にも、祖父にも似ていて、皆一目で兄弟だと感じる雰囲気を持っていた。五一伯父は六男なのでそう名付けられたと聞いた。父の長兄は一、次兄は二輔、三男の父は三喜男、次弟は四方太、その下が結、そして五一伯父だった。私たちはまだ館山に住んでいたので、この五一伯父とは一緒に住むことがなかったが、その後千葉県の高等学校の教師になった伯父は、歯に布着せず物事をはっきりと言う、しかも大変辛口の批評家で、私は高校時代にこの伯父から率直な中国体験を聞いたことが楽しい思い出となっている。伯父はかなりの苦学生だったらしく、上海で浮かれていた日本人たちには大変厳しいことを言った。
この狭い家に私たち姉妹は1948年から父母と一緒に住むことになった。私が雙葉学園の五年生に編入試験で受かったことや、姉の高等学校が始まることなどが、その理由だったと思うが、とにかく父母は私たちを祖父母に預けっぱなしではいけないと考えたに違いない。その家はなんとも狭かったが、記憶に鮮明に残っているのは、どのように私たちが寝たり、食事をしたりして暮らしたかではなく、国会から帰って来た父が茶の間で横になっている姿や、良くたずねてきた父と同郷に東大生とその友人と碁を打ったり、時には麻雀をしている姿である。
その頃の父は国会からすぐに家に帰って来て、夕食をよく家でとっていたが、体の大きな父が、浴衣や丹前姿で茶の間に横になると、それだけで茶の間のスペースは占領されてしまった。そういうときはいつもただ黙っていたが、決して暗い顔を見せることはなかった。しかし、その疲れ様は明らかで、母から占領軍との打ち合わせがあったことを聞かされることもあった。私は1、2度見たことのある日比谷の占領軍指令本部の入り口に立つ拳銃を持った背の高い米兵の姿を思い出し、そこから中へ入っていく父の姿を心に思い描いたりした。
同郷の友人などが来てお酒に酔った時には、父は実に元気よく喋り、本当に楽しそうであったが、母はそういうときも父が大変な経験をして来たときだからと、酔っ払っても少しも文句を言わなかった。水田家の人たちは皆大酒飲みだが、母の実家の人たちは少しもお酒を飲まないので、母も初めは驚いたと言っていた。その母も選挙で初めてどぶろくを飲まされ、そのときのひどい苦しみ方はそばで見ていた私も今でもよく覚えている。祖母が心配して、とにかくお酒を飲んだことなどなかったのだからと、背中をさすったり、汗を拭いてあげたりと大騒ぎだったのである。その母も次第に腕が上がって、晩年は大した酒豪であった。
戦争責任やレッド・パージred purgeで先輩のいない国会運営と党の仕事で、父は第一回当選後早くから様々な、言わば要職についていたようで、私たちが一緒に住み始めた頃は党の政調副会長や大蔵省の政務次官にもなっていた。父がその頃どのような仕事を手がけたかは詳しくは知らないが、占領下で税制度を手がけたことは自伝でも言っている。いわゆるドッジラインに関わる新たな税制の設定である。教育法や義務教育から大学までの教育制度に関する仕事も早くからしたようで、義務教育の国庫負担、ララ物資を使っての給食制度の設定などは父の仕事だったと、のちに文部省の方達から伺った。ずっと後になって私が城西大学の理事になってから、大学の仕事で文科省を訪ねたとき、体育関係部署の局長さんが、その当時の給食制度担当を務めた、給食制度の設定は素晴らしい出来事で、やりがいのある仕事だったと、話してくださったことも、なんとなく誇らしい気持ちとなり、記憶に刻まれている。その局長さんの初めての仕事だったというが、若い父にとっても同じだったのではないだろうか。
東片町の家での父の姿の思い出には、同郷の若い東大生が、友人を連れてよく遊びに来たときのことが多くある。二人は母と麻雀をしたり、父がいれば碁を打ったりして、食事もして、かなりの時間を家で過ごした。ちょうど大学を卒業する年に当たっていたらしいが、戦争と敗戦によって、人生の見通しが大きく変わったことへの不安を抱えていたのだと思う。彼らは私にいろいろなことを教えてくれた。まずゲーテについて、青年の悩みについて、そして、旅について語り、人間が精神的に成長するためには孤独な旅が必要なのだと言った。ヘルマン・ヘッセの東洋への旅についても話してくれたのである。法律を勉強した二人は、かなりの文学青年だったらしい。そのために私はゲーテはともかく、ヘッセという作家の名前を覚えた。
戦前は、東大出は学士さまと言われて、就職に困るということはなかっただろう。敗戦直後だから誰にとっても厳しい就職難なのはと当たり前だったが、約束されていると思っていた将来が霧消してしまうような不安にかられるのは特に学士には多かったのだろう。彼らの中には苦学生も多く、それだけに苦労したことへの、その若い時期への、どこか裏切りのような悔しい思いをしたことだろう。戦後新制大学ができて大学への進学者が増えてからでも、1960年代の終わりごろまで、男子の大学進学率は12%前後だったのだのだから、戦前の帝国大学生は一握りのエリートだったのである。
やがて彼らは卒業して、同郷の相川さんは内閣法務局に、そして彼の友人の松山出身の松沢さんは特許庁へ就職して、それからの長い20世紀後半の日本の復興と発展の時期を、国家公務員として生涯地道なキャリアを全うした。就職してからも二人はよく家に来ていて、それは二人とも結婚して家族を持つまで続いた。広くなった西片町の家では、訪問者がいかに親しい人でも、子供たちがずっと一緒にいることはないが、部屋数のない借り屋だったからこそ、他にいる場所がなくて、ずっと一緒に話を聞くことができたのだ。
私は小学校の6年生の終わりまで東片町の家に住んだが、その一年の間の家での生活は鮮明な印象となって残っている。玄関の前の細い道を隔てたお向かいの家族との交流や、少し離れた近所に王子製紙に勤めていた家族が住んでいた。そこには私たちより少し年上の「お姉ちゃま」がいて、その人の家へ幾度か遊びに行ったことを思い出す。広い庭があり、「お姉ちゃま」はお母様といつも一緒で、とても華やかな、見たこともないような化粧品や香水ビンの並ぶ鏡台があった、お姉さんは私の髪を結ってくれてリボンもつけてくれた。考えてみると母には鏡台もなく、化粧品も多く持っていなかった。戦中も戦後もたくましく生きた母は、結構おしゃれだったにもかかわらず、化粧品や香水、リボンなどのある女性らしい自分の部屋を持ったことはなく、私たち姉妹も母の化粧品をこっそり使うなどといういたずら遊びを経験したことはなかった。
二階を借りていた中年の女性に関しては大きな謎だった。私は父母がこの家を借りた経緯などは聞いていないし、ましてやその女性について誰からも話を聞いたことはなかったが、母は意図的にその女性の話に触れないでいたような感じがした。だいたいあまり顔を合わすことがなく、外出もほとんどしない人だったように思う。玄関からすぐ二階への階段が続くのだから、外出の時には顔を一度だけ見たことがあるように思うが、そのとき大変質素な感じの、身だしなみの良さそうな人なことに驚いたことを覚えている。すでにずいぶん歳を取っているのか、若いのかよくわらないほどに、印象のきつくない物静かな人で、その着物姿からも、着こなしや、趣味などからも、一見してわかるものはなかったように思う。あまり私たちに挨拶もしなかったように思う。彼女を訪ねてくる人もなかった。私たちとは全くの没交渉で、私は二階に上がって見たいと思ったことがあったが、呼んでくれることなどはなかった。二階が開けば少しは広くなるのにとも思ったことがあったが、私たちの方が早く家を出ることになった。
東片町時代を思い出すたびに私は彼女のことを考えた。母に聞いても何も答えてくれなかったし、事実誰も彼女のことは知らないままだったようだし、また皆忘れてしまっていた。それは何も隠れた真実など持たない、偶然にその家の二階を借りていた単なる借り人だっただけだろうし、その人について知らなければならないような、特別のこともなかったのだろう。しかし私にとっては東片町時代の謎であり続けた。
東片町は焼け残った場所で、どの家も、家並みも、路地も全てが、戦前の、樋口一葉気配がする、少々しがない、庶民生活の痕跡と雰囲気を色濃く残している界隈だった。1967年アメリカから帰って私は東片町の家を見に行ったが、全く変わらないままだった。こぎれいになっていて、東京都のど真ん中の住宅地になっていたのだから、貧しい近所でないことは明らかだが、マンションができているわけでも、新しい建材屋スタイルの家が建っているわけでもなかった。路地は相変わらず狭く、王子製紙の家もそのままの門構えであった。庭の下の方のお習字の先生は、母の話ではだいぶ前に亡くなったということだった。路地に足を踏み入れた途端、私は真っ先に、あの女性はどうしたのだろうか、今でもどこかにいるのだろうか、と考えた。あんなにひっそりと一人暮らしを敗戦の時代にしていた女性とは、事情があるはずなのに、何も語られないのは、謎があるからでなければならない、と。
東片町に行ったことを話した時に、居合わせた父の知人から、その女性が外国人だったことを知らされた。中国から来たばかりの時に戦争が始まって、そのまま日本にい続けたのだそうである。私が、田端、勝山、そして館山時代を生きている時に、その人は異国の戦争中の日本に暮らしていたのだ。そして、戦後になって東片町の家に偶然に同じ屋根の下に一時住んだのである。私は日中戦争勃発の年に生まれたことを、中国の友人や留学生たちに会うたびに考えたが、あの和服姿の女性が、中国人だったことに驚愕して、やはり彼女は謎だったのだと心を打たれた。
そのことを教えてくれたのは、父の同郷の人で、東片町時代に家の手伝いをしてくれていた女性を紹介してくれた人だった。兄と弟そっくりの兄弟で、いつも父のそばに来ていたのだが、父が大学を卒業して失業していた時代に一緒に下宿をしていたそうである。大人の話を聞くのが好きだった私は、その気取らない、房州弁のおじさんが来ると、いつもそばに行っては話を聞いていたのである。そのお手伝いの女性は同じように同郷の人で、大変涼しげな顔立ちの美しい人だった。家には泊まる部屋がなかったので、どこかに間借りをして、家に来てくれていたが、西片の家に移ってからも、家には一緒に住まず、そのまま通って来てくれていた。その女性を、年下の建設材会社の社長が見初めて、やがて結婚することになった。その若者は硬い筋肉が腕まくりした袖からみえ、今風の感じの、大変素敵な人だと私は思った。その小倉さんというおじさんは、とにかく父のことは自分のことにように思っていて、どんな小さなことでも母の頼みも、なんでもしてくれたそうである。二階の女性が中国人であったことを母が知っていたのかどうかわからないが、そのことが話題にならなかったことは、やはり何か謎めいている気がする。話をしあう中になったら、どちらも気まずい思いをしていたのかもしれない。
東片町の生活で新しかったのは何と言っても、初めての東京での学校生活である雙葉での経験だった。疎開から帰っての雙葉での勉学生活は、千葉の学校での経験とは何もかも違っていたが、私がそのことに違和感を感じ始めるきっかけになったことが一つだけあった。その頃父は大蔵省政務次官をしていたが、大蔵省は四谷の堀を超えた場所に仮の省舎を構えていた。雙葉は堀の内側ですぐ近くだった。ある日先生から呼び出されて、父が雙葉のお御堂(礼拝堂)に花を届けて来たという。そして以後はそのようなことを決してしないように伝えなさいときつく言い渡された。私が、お御堂にはお花が飾られるのだからいいのではないかと聞き返したところ、「蛙の子は蛙ですね」と言われたのである。私はその意味がわからなかったが、家に帰ってその話をすると、花はどなたからかいただいた花籠だということ、そして「蛙の子は蛙だ」というのは「褒めたんだよ」と父から言われた。しかし母の怒りようは少々大げさで、「だから雙葉は嫌いだ」と言い、初めて母がどこか雙葉に違和感を持っていることに気づかされたのだった。家と学校が同じ場所ではないことはもう少し大きくなれば自然とわかることなのだが、私は自分の感じている環境の違いが何か深刻なことのように思ったのだった。
母は私が編入試験に受かった時に、校長先生から呼び出されて、お子さんは雙葉の校風に合わないから、家庭でも教育に協力してほしいと言われたそうである。面接で私は試験はどうでしたかと聞かれて、「良い問題だと思いました」と答えたところ、校長先生が、なぜ良い問題でしたかと聞き返した。ララ物資についての質問は戦後の復興政策の一つで、給食として自分たちの身近な問題でもあるし、法隆寺の火災については、戦争で負けた日本の文化遺産について考えるいい問題だと思いました、と答えたところ、ずいぶんお利口ですね、と校長様が言われた。呼び出しの時に母は、その面接でのやり取りのことを言われて、ずいぶんこだわっていたようだと父に話していた。「試験はどうでしたか」という質問に、難しかったと答えていれば無事だったのかもしれない。父が笑っていたので、私はなんとも思わなかったが、母はそれからもずいぶん長い間この話を幾度も持ち出しては怒っていた。そしてそれは長い間家のエピソードとなった。
言葉つかいも悪く、人見知りをしない、生意気な、政治家の娘、という「俗物」のイメージを、会ったばかりの子供に抱いたのだから、母にとっても雙葉とのなんとも違和感のある出だしとなったのは当たり前だった。母は自分の家庭や教育の仕方が批判されたように思ったのだろう。
東片町の家での暮らしは、スキンシップの濃密な暮らしで、個室はおろか、一人になる場所も時間もない暮らしだった。それだけに、父と母がいつもそば近くにいることを感じ、大人と子供が隔てられることのない、食事も会話も、客も家族もいつもひとまとめに顔を付き合わせる時間を持った暮らしだった。電話もテレビもインターネットもないし、個室もない。顔をあわせる人だけが情報を交換できる人、コミュニケーションする人で、愛情や友情を確かめ合う人たちだった。私の幼児期の「地獄耳」はますます冴え、父から「のり兵衛」は「ベイビー博士」だとからかわれた。
父は散歩をするのが好きで、言問通りから東大の裏門へ前を通って上野子上広小路へ出る道を歩く散歩に私をよくつれていた。のちには落語を聞きにつれて行かれた。何か話をしてくれるわけではなく、ただ一緒にくっついていただけだったが、それは西片町に引っ越してからは次第に少なくなった経験だった。父はお説教をすることが決してない人だったし、何かを教えるということもしなかった。自慢話も一切しないから、父の口から自分がしたことを聞くことはほとんどなかった。周りの人たちを叱ったり、非難することは全くなく、何かを批評することもしなかった。その父が、参った、参った、と言っていた出来事があった。
それは父の若い秘書が持ち逃げをした時である。それは子供心にも驚きでその人の顔も名前も忘れることなく記憶に刻印されている。彼は政治家としての父の最初の個人秘書だったのではないだろうか。何れにしても東片町の家には毎朝、風呂敷包みを抱えて出勤してきていたのである。彼が何をしたかは詳しくは知らないが、お金に関係することであったことは事実で、おそらくは母が託したか何かのお金を持って何処かへ行ってしまったのだろうと思う。そのお金は支払いか何かに必要なおだったらしく、母はその後始末に大変だった様子は今でもはっきりと記憶している。父や母には余裕のお金などなかったのだ。
当時の国会議員の給与はどのくらいだったのだろうか。新憲法では歳費と呼ばれる国会議員の給与は「相当額」とされている。国家公務員の最高額より低くするという定めもあるようだが、敗戦直後のことだから、そのあとにできる様々な法令が整備されてはいなかったと思う。国会議員の給与は無償で、財産のあるものが議員になった旧憲法の印象がまだ人々の心を捉えていた時代である。父には財産がなかったから、家計が火の車だったことは目に見えていて、それはずっと後まで続いたのである。
母のブローチ盗難事件もあった。あの頃は空き巣やドロボーに入られることは日本中どこでも横行していた。万引き、置き引き、すり、などもいっぱいで、強盗や殺人などの重大な事件よりも、お金に困っての盗みが日常に起こっていたのである。東片町の家では、ドロボーに入られたことはないと思っていたが、実は一度だけ母のブローチが盗まれたのでさる。母はそれをてっきりどこかに落としたと思っていた。子供達も動員されて、電車の停留場から家までに道を下を向いて探して歩いた。それは銀細工だったらしく、確かに母はそ入れをよそ行きにしていたし、その他には何も持っていなかったのである。ところがずいぶんあとになって、警察の人がドロボーを捕まえたら、東片町近所にドロボーに入って荒らしていたことがわかり、盗品の中に母のブローチが入っていたというのである。
西片町では何度か盗難に見舞われたが、すぐに入れそうな東片町の家には、ドロボーは訪れなかったと思っていたのだった。何もなさそうな家だし、人がいっぱいで誰かが目を覚ましそうだったのだろうと。しかし、ただ一つ母のブローチが取られたことも、他にめぼしいものがなかったと家での笑い話となった。
東片町時代は父が国会議員だということが特別に現れない生活だった。秘書も家にいないし、選挙区からの来客もほとんどなかった。それは家族のいる場所で、父の威厳はどこにも発揮されない場だった。父はいつも浴衣姿で、今の40代のかっこいい男性からは想像もできない、おじさん風で、いつも自分に構わない、そして人にも構わず、飄々としていた。テレビもなく、ラジオでも、父の国会での様子や省庁や党での仕事ぶりなどは全く知らなかったし、私たちにはいつも変わらない同じ父だった。占領軍本部から疲れて帰って来た父と、いつもありのままにニコニコしている父とのギャップも、やがて思い出の一コマだけになっっていった。
1950年、短い東片町での生活も、西片町への引越しで終わりを告げることになった。それは私が中学生になる時で、私の幼児―子供時代も終わりを告げることになったのである。敗戦後と言われる時代も終わりがすぐそこまで来ていた。
2020/06/18
崖の上の家:父なるものの凋落
第四章
館山の家:政治家の娘
敗戦の8月には小学校の3年生だった私は、翌年安房郡の中心都市館山市に引っ越しをした。父が1946年の新憲法下最初の総選挙に衆議院議員への立候補を決めたので、館山市に選挙事務所を持ったのである。館山市は勝山から数駅、房総半島の岬の方向へ行った内房総の海岸添えの街で、北条、館山、那古、船形と外房へ続く山の方の地域などがあり、私たちは館山駅近くの北条に家を買って、そこに祖父母たちとともに、住むことになった。
勝山の家に比べて敷地が350坪ほどで、田舎町の家としてはそれほど広いことはなかったが、部屋数のある平屋の家と池や果物の木が多い庭があって、私は勝山から移って幼いながらつくづく広いなあと感心をした。離れは茶室に最適な作りで、祖母は早速茶道のお弟子さんをとり始め、庭には様々な茶花を植えた。母は接客のための別棟の洋館を建てた。天井が高く、大きなソファやイスがあり、その奥に台所のようなお茶を出す部屋があって、そこから続く納戸のような部屋を通ると母屋の日本家屋へ繋がった。この洋館は安普請で、ちゃちな感じがしたが、窓が多く、日当たりがよく、ブルーの絨毯が異国風な雰囲気を醸し出して、私はそこに一人で座っていることが大好きになった。小学校4年生ともなれば、自分のことも気になり始め、世の中のことに少し違った見方をし始めた頃だった。
この館山の家が、父と母の戦後の出発点となる場所だった。
家は館山駅前のロータリーのある広場から、海岸沿いに半島の先の白浜から外房線の終着駅の鴨川方面へと行く県道へ出て、そこを縦断して北条小学校の方へ、そしてさらに嶺岡の山々を経て鴨川から外房へと続く北条地域の大きな通りから、2本奥へ入って、県道と並行する住宅路にあった。隣は私立の熊沢女学校(安房西高等学校)の小ぶりな校庭で、前は槙の垣根で囲われた大きな敷地のお屋敷があった。この道は短くてやがて突き当たり、左は県道へ、そして右に行けば北条通りとやがてどこかで合流して三好や平群などの山村へと続いて行く道となっていく。戦災に合わなかった地方の都市の昔ながらの構造がそのまま残っている場所だった。
駅前から県道へ出て、北条通りの交差する目抜き通りの角の建物の一部を借りて、父は選挙事務所を開いた。二階が今でいう対策事務所で、支援者が集まっては、マイクで道ゆく人に呼びかけをしたりしていた。選挙は確か3月で、北条小学校に転入する前だったから、私はよくその事務所へ遊びにいった。
父は40歳。戦前は京都大学で反戦運動をしていたし、戦争中は特攻に見張られ続けるほどだったから、自由党から出馬するには、何のコネもない状況であったという。いわゆる地盤、カバン、看板がない、一介の若者だった。それでも党の公認を得ることができたのだった。日経の「私の履歴書」、『蕗のとう』で父自身が書いているが、面接時に鳩山一郎党首から「君は共産党ではないのかね、なぜわが党から出るのかね」と聞かれたそうである。のちに父は敗戦の間際に宣戦布告をしてきたソ連は信頼のできないと言っていたから、日本の復興をスターリンの率いるソ連との関係に託すことに疑念を抱いていたことは確かだし、民主主義の発展こそが日本の繁栄を可能にするとも述べている。
敗戦後初めての選挙だから、日本中が新たな熱気に溢れていたことは確かだった。当時のニュース映像を見ても、日本にとっての大事な新たな一歩を踏み出すための、重要な全国一斉の活動であることの意義は大きかったことがわかる。その上、日本初めての女性の参政権の取得、男女平等社会の実現へ向けての議員の選出の機会であり、多くの女性候補者が出た。戦争責任を問われた旧政治家や軍部の役員が皆政治から撤退させられている中で、戦争中に弾圧にあった反戦主義者や活動家の政治への晴れの表舞台進出の機会でもあった。
父の選挙事務所が特別な賑わいだったとは思えないが、母の必死の反対を押して立候補した父を家族全員が応援する様子は私には珍しい風景だった。幼い頃を含めて、子供の私の生活に父の姿が強い印象を残すような日常は初めてだったのである。父は戦時中巣篭もりをしていたわけではないが、戦争にも行かず、青年の頃の反戦の気持ちを抱えながら、史上最大の東京空襲の最中を、家族と離れて暮らしていたのである。父の姿はその頃の子供の生活で大変希薄であった。
父は選挙演説の会場へ私を連れいきたがり、小さな子供が舞台に上がって、よろしくお願いいたします、と選挙応援活動をしたことが評判になった。次の選挙からは選挙法で子供は応援に参加できなくなったので、それが私が父の選挙の応援をしたただ一回きりの経験となった。私には選挙がなんであるか、衆議院議員とはなんであるかは全く知らなかったので、ただ、父がそばにいることが嬉しく、応援するという自意識は全くなかった。父は人と会うときも私を膝の上に乗せて話をすることがしばしばで、選挙の時の短い日々が私が子供として無邪気に父に甘えていた思い出となった。選挙が終わると父と母はすぐに東京の東片町に家を借りて住むようになり、私たちは祖父母とともに館山の家に残されたのである。
父の選挙区は当時は千葉県全県一区で、連記投票で15人が当選だった。父は7位当選だった。政治には何の人脈を持たなかった若い新人の父の7位当選は、父を応援してくれた郷土の人たちがいかに大きなうねりとなったかを表して、多かったかを表して、新しい時代の幕開けを皆が感じたという。当選直後館山の家の玄関先で撮った写真があるが、そこに写っているのは親族だけと言っていいほど、家族と皆私も知っている人ばかりで、選挙戦が、大げさなものではなかったことを示している。2回目の選挙からは中選挙区になり、父の選挙区は千葉三区で、山武、東金から外房地域全体と木更津以南の内房地域と、千葉県の南端から外房地域となった。当選者枠は5名で、連記投票もなくなった。その後父は連続13回当選、30年国会議員としてつとめ、国会から表彰された。父の死後日本は小選挙区制に変わるが、父は小選挙区での選挙はしたことはなかったのである。
2回目からのは中選挙区制での選挙は、父個人の選挙であっても、5人中何人自民党が確保できるか、という戦いにもなって行き、競争の在り方が変わっていったということである。父は選挙中は全國遊説に飛び回り、その間母が選挙活動の指揮をとった。1953年父は欧州諸国の選挙制度の視察に初めて外国訪問をした。視察団の団長として日本を発つ父を羽田空港へ見送りに行った時の写真が残っているが、女性議員、中山マサ議員と他数名の議員とともにプロペラ飛行機のタラップに写っている父は40代後半の若い議員の姿だった。
館山の家での生活は、父や母がいないことで、私には毎日が自由に遊びまわることのできる日常になった。祖父は俳句を作らせてくれたし、祖母はお茶の席に座らせられた時でも、褒めることはあっても、あまり厳しく指導はしなかった。新しい北条小学校では、戦後の民主主義教育が始まって、先生方も戸惑いが多いように見え、叱られることはほとんどなくなった。勝山時代はクラスの誰かが叱られると一番先に泣き出すので困ると母が先生から苦情を言われたほどに泣き虫だったらしいが、北条小学校の4年生ともなると自分で自分のことが少しわかるようになってきていたし、俳句や詩で県の賞をもらったり、音楽が得意になったりした。
しかし何と言っても、放課後多くの友達と家で遊んだ思い出が鮮明である。庭には果物の木が多くあったので、みかんや桃を取って食べたり、木を登って屋根に上がったりして一日中遊び呆けた。祖父母は自分の子供たちは厳しく躾けた教育パパとママだったという評判だったが、孫の私たちには大変優しくて、親と離れていることを可哀想がり、何をしても叱ったりしなかったのである。中学生の姉はどんどん背が高くなり、長い足を立膝をして座るのを、帰ってくる度に母に叱られていたが、祖父母は姉を「脛長彦」と呼んで行儀を正すことはなかった。祖父母の元で私たち姉妹は野放しだったのである。後になって収穫を楽しみにしていた果物をみな子供軍団に食べられてしまったことや、屋根の上で遊ぶ子供たちに、すっかり瓦が歪んで雨漏りをしたことなど、随分祖父母を困られていたことを母から聞かされた。
毎日友だちとリヤカーに乗ったり、載せたりする遊びや、前の屋敷の槇の垣根から中を覗き見したり、隣の女学校の校庭へ忍び込んだり、たわいない遊びに明け暮れていたのである。その友達とは今も手紙や折々のハガキのやり取りをしているのだから、本当に仲良しだったのだ。
祖父はすでに逓信省を退職していて、一日中俳句を作っていた。富安風生先生が安房へ吟行に来られた際にはお供をしたり、家にお招きしたりして、句会を開いたりしながら優雅な老後生活を楽しんでいる様子だった。祖母はお茶の先生業にますます精を出して、離れのお茶室で、毎日お弟子さんたちにお稽古をつけていた。お弟子さんの数も増える一方で、小学校の教師を結婚でやめた祖母にとっては、本来の自分を取り戻したように生き生きとした生活だったのだと思う。館山の家は祖父母にとっての終生の住まいとなり、祖父が亡くなってからも、祖母は一人で暮らし続け、東京で一緒に暮らそうという母の薦めを拒み続けたのだった。庭の茶花やイチゴなどを栽培にも精を出し、私たちは汲みとり口から庭の隅の畑まで桶をかつがされて閉口したものである。戦後のこの時期は食糧難にも関わらず皆生き生きとしていたのだった。
父は代議士になって、土地の「名士」になったので、祖父母にとっても皆に親切にされることが多く、居心地が良かったのだと思う。祖父母の父びいきは大変なもので、若い頃の大学を出たばかりで就職先もなかった父に一人娘をやるということを決めたのだから、父の人柄をよほど見込んでいたのだと思う。母は私たちを心配してちょくちょく帰ってきたが、その都度バイオリンなどを買ってきてくれた。私はバイオリンよりも、勝山時代に東京空襲から救い出された蓄音機でかけた英語のレコードの方を聴き続けてすっかり歌えるようになっていた。バイオリンはついにうまく弾けないままだった。
館山の家には池があった。庭に池があるのは縁起が悪いと、私の留学後のことだが、その池は潰されてしまったようだが、その当時家族には縁起を担いだり、占いに頼ったりするものは一人もいなかった。その池には大きなガマガエルがいて、その鳴き声は恐ろしいくらいに大きかった。東京に移ってから、いつ頃かは覚えていないが、そのカエルは何処かに行ってしまったということだが、そのカエルは私たちがいても物怖じぜず、茶色の、かなり見場のよくない姿を堂々と見せて池の縁に座っている。カエルは庭の風物だった。房総には大きな家蜘蛛も多かった。茶色で実に大きい蜘蛛が、家の壁にはりついていた。毒もないし、家の中の害虫を食べるからと、誰も気にかけないでいた。夜中に起きた時に暗闇で何かを踏んだと思っていたら、朝になって大きな蜘蛛の死骸が床にあったことなどを思い出す。
館山の家にネズミは出なかったし、ヘビもあまり見かけた記憶はない。房総半島はマムシで有名で、父の生まれた曽呂村などは、夏には夜は皆長靴を履いて道を歩いたものである。ヤモリやムカデなどはよく見たし、夏には、蛾が引き切りなしに入ってきた。祖母は揚羽蝶やモンシロチョウをこさせたいと、いろいろな花を勉強するようになった。館山時代にはさすがに髪にシラミを住まわせている子供はいなかったが、蚤やシラミはいたのだろうし、ハエや蚊は家の中を自由に飛び回り、クマンバチは庭に大きな巣を作って退治するのに大変だった。春にはツバメが軒下に巣を作り、鳥は果物を食べに一日中庭に来ていた。開放的な日本家屋は、縁側からすぐが庭で、土に近く、ミミズはもちろんのこと様々な虫がいたのである。庭に果物の木があり、畑もある地方都市の家には様々が虫が共生していたのだ。なんと言っても大小の蜘蛛が家の中のあちこちにいたのである。後年カリフォルニアのリヴァーサイドの家の玄関で、大きなトランチュラを見たことがあった。その時はちょうど母が私たちを訪ねてきた時で、夫は驚いて母を驚かせまいと蜘蛛を追い払った。トランチュラは館山の家蜘蛛の二倍は大きいが、母は全く怖がらず、むしろ平気だった。トランチュラは毒グモなのだ。
館山には八幡神社という大きな神社がある。父の通った安房高はその神社に面していて、父は選挙に出た時に守り神様だと必ずご挨拶にいっていた。そこの祭りは大変有名で、神輿と屋台がいく台も出た。父が代議士になってからは、屋台や神輿が、家の前の通りにもやって来て、祖父母は門を開き、皆にお酒や水、食べ物を振る舞った。ところがそのあとは、祖母が丹精して植え育てた茶花は皆踏みにじられてしまい、祖母の落胆は大きかった。それでも毎年小さな草花を植え続けた。八幡神社の境内には父の死後銅像が建てられているが、後年安房高を訪ねた時、柔道部の先生が、柔道部の部屋に飾られている父のその頃の写真を案内してくださり、柔道部は朝練の前に、父の銅像の拭き掃除をすることを話してくださった。父は政治家としてではなく、安房高(当時は安房中学校)を全国優勝へ導いた先輩として尊敬され続けていたのである。
館山の家ではまだ電気冷蔵庫以前の生活で、氷を入れる冷蔵庫だったので、氷を買いに氷室へ行くことも楽しみの一つだった。群馬出の祖母は榛名湖が凍ることや、氷を切り出す様子などを話してくれた。そこから大きなトラックに積み込まれて東京や房総まで運ばれてくる様子を話してくれたのだが、温暖な館山の生活では想像もつかない風景だった。祖母が最初に教えた小学校は伊香保町で、のちに林芙美子の『浮雲』の映画を見たり、城西大学の父母後援会で訪れた時は、いつも祖母のことを思った。その当時の生徒だった人たちの幾人かは土地にいて、その中の一人は大きな旅館の主人になっていた。その人の息子さんが城西国際大学に入学したのである。彼は父母後援会の会長を引き受けてくれた。若い頃の祖母の話も大層面白かったが、祖母の生徒には群馬県選出の代議士や大臣になった人もいて、祖母のことを覚えてくれている人も少なくなかったのである。
冷蔵庫は小さかったから、ごくわずかななまものだけを入れて、毎日の食料品は近くの店へ祖母の買い物について行った。祖母は天ぷらが好きな祖父のために魚をよく買って、房州はすごいね、といつも店の人に言っていた。海のない群馬では新鮮な魚を手に入れることは贅沢の極みだったのだのだろう。戦後すぐの館山も食糧難だったが、野菜や果物は豊富で、食べ物に不自由はしなかったように思う。祖母はお蕎麦を自分で打ったが、上州のそばの美味しさは到底出せないと悔しがっていた。こんにゃく好きも大したもので、その影響で私はアメリカ留学中に最も懐かしかったのがこんにゃくだった。いくら防臭が気に入っていても、祖父母は群馬の食事も懐かしかったのだろう。
菓子類はほとんどなく、私は田端時代から引き続き甘いものを知らずに育った。買い食いをキン十れていたので、母が東京からおせんべいを持ってきてくれた時には、本当に美味しいと思ったことを覚えている。祖母は、こんなものは自分でも焼ける、と盛んに言っていたが、一度も焼いてくれたことはなかった。今では千葉はおせんべいの名産地である。その頃祖母がお茶のお菓子に何を出していたのかは知らないままだったが、後になって、古いお弟子さんの一人が、芋ばっかりでね、と祖母と笑っていたのを聞いたことがあった。お茶葉や抹茶も入手困難だったそうで、他の流儀の先生の所ではお茶が薄くて泡が立たない、など色々と話を聞いたものである。父や母を飛ばした祖父母との生活は、緊張感も軋轢も薄い上に、年のかけ離れた大人たちとの接触も多く、いろいろな知識を仕入れる機会ともなった。地獄耳だとよくからかわれた田端時代の幼い頃とはまた違った、もう少しまともな好奇心を育ててくれたようにも思う。
館山時代の思い出に、天津から引き上げてきた伯父一家、中でも、従姉妹、従姉妹たちとの交流がある。父母は北条の家を見つけるまで、駅から少し離れた館山港に近いところに家を借りて、選挙の準備などをする生活のベースにしていた。その家もまた敷地が広く、家自体もかなり大きくゆったりとしていた。門の脇にざくろの木とイチジクの木があり、どちらも実をたわわにつけた。木々の側には井戸もあった。アラビアンナイトの話には砂漠のオアシスにデーツやイチジクの実が現れるが、ざくろとともに異国情緒いっぱいの感じで、館山時代の思い出の風景となっている。
館山港はこの地方の大きな漁港で毎朝の市場の賑わいもあったが、戦争中は軍部の基地があったので、空爆の的になることもある、どこか機密地域でもあったのである。敗戦直後は基地駐在の将校たちが暴動を起こすかもしれないし、また兵隊さんたちから彼らが標的になり危険にさらされるという噂が立ち、父は私たち家族をしばらく九重の伯母の家で過ごすように取りはからったこともあった。館山湾は東京湾の出口に近い大きな湾で、波立ちの少ない穏やかな内海を形成していた。鏡ヶ浦と呼ばれるくらいに、一枚の鏡のように張り詰めた水面が三浦半島の上にそびえる富士山を大きく映し出す。どこか雄大で、おおらかな、威厳のある風景を展開している。父に連れられて、長い館山桟橋の先まで行き、そこから東京湾に沈む夕日を見た時は心を打たれて、忘れられない記憶の風景となっている。勝山の竜島の湾は小さく、物語の中のかくれ里のようにひっそりとしていたが、館山湾は外に向かって拓けていて、同時に広い東京湾の入り口を守る凜とした気配を漂わせている。対岸の三浦半島は伊豆半島の入り口だが、鎌倉時代の頼朝の亡命の例をとっても、東京をバイパスした交通路となって人の移住や交流も盛んだったのである。浜辺は館山海岸から北条海岸まで長く続いていて、この水泳場として人の集まる浜辺もまた、竜島のプライベートなひっそりとした佇まいとは対照的だった。勝山は松林が残る避暑地の雰囲気をもつ漁村だが、館山は地方の大都市なのだ。
そこへ天津で海運会社を経営していた父の次兄二輔伯父一家が引き上げてきたのである。千代子伯母は四国の出身で房総には縁者がいなかったし、伯父一家が千葉へ帰ってくるのは、そして父を頼ってくるのは当然のことであった。天津では羽振りが良かった伯父一家も、日本の敗戦とおそらくは命からがらの引き上げの船旅で疲労しきっていたのだと思う。
一家が初めて家に入ってきた時のことは忘れることができない。父よりもさらに大柄な伯父、地味な感じの伯母と二人の若い女性の娘たち、そして、姉と私とはそれぞれ一つ年上の少年の息子たちが、皆大きな風呂敷包みを背負って隊をなして門から入ってきたのである。上の従姉妹たちはもう年頃と言っていい女性たちで、口紅を塗っていたことを覚えている。もんぺではなくズボンを履いていて、どこか異国風で華やかな雰囲気を持っていて、見慣れた田舎の日本人の女性たちとははっきりと違った印象だった。やがて上の従姉妹(正子さん)は館山で評判の美人として戦後の地方の若者たちの間でもてはやされるようになった。まもなく土地の由緒ある商店のハンサムな長男と結婚し、実業家としての実力を発揮するようになる。下の従姉妹(友子さん)はおとなしいが自分の考えをしっかり持った女性で、勉強に精を出して外務省に勤めるようになり、地道で自立したキャリアーウーマンの道を選んだ。彼女は生涯独身で東京での一人暮らしを貫いた。私はこの容貌も性格も生き方も違う、全く対照的な二人の従姉妹たちを、遠くから眺めているだけだったが、戦前、田端の家に天津からお里帰りをしてくる時の伯父一家の中でも、綺麗な服を着たお人形のようなお姉さんたちから、キラキラしたセロハンで包まれたチョコレートをもらった時のことを思い出して、モンペをはいて風呂敷包みを背負った姿との違いに、不思議な気持ちになったものだった。甘いものが全くなくなっていた当時、チョコレートは宝石のような宝物で、私たちは近所の高崎さんの姉妹を始め数人の遊び友達とそれらを分け合って食べたのである。チョコレートの包み紙は、ずっと大切に箱にしまっておいた。
外地からの引き揚げはそこでの生活の全てを失う経験で大変きつかっただろうし、引き上げの船旅は身体的に困難な旅であったことは一家の疲れ方からもよくわかった。しかし、彼らは皆大変プライドが高く、精神的にへこたれたりする様子は人に見せなかった。贅沢な生活から、一文無しで帰国し、親戚の家に居候をする生活への変化は、自尊心を傷つけたであろうことは明らかなのに、母の献身的な世話に対しても、どこか頭を高く構えているようなところがあった。若い従姉妹たちにとっては、何もわからないままに歴史に巻き込まれて、急に逃げなければならない理不尽な経験をしているのだった。怒りや反抗心を内に持ったとしても不思議ではない。天津での生活との暴力的な断絶と引き上げの卑屈な経験が、それからの従姉妹たちの人生に、同じ戦後第一世代であっても、日本の戦後の若い女性たちとは違った大きな影響を及ぼしたことは確かだと思う。
従姉妹たちはそれまで日本での生活をほとんど経験したことはなかったと思う。彼らは日本を知らないで成長したのだ。敗戦で荒廃した日本、そして古い習慣の残る地方都市での生活を彼女たちがどのように感じ、日本人と自分たちとの違いとそのギャップにどのように対応しようとしたのか、彼女たちの内面の思いを私は知らないが、どこか揺るがない自己主張を内に秘め、一人は反抗的なほど派手に、わがままに、そしてもう一人は他者には無関心な単独者の姿勢で自分の道を行く女性たちは、引き揚げ者というよりも、祖国に帰還しながら、自分たちをよそ者であると感じる異邦人意識を持ったであろうことは想像に難くない。祖国離脱者ではないにしても、帰還者のはみ出し者意識を自己意識の根底に持ち続けたのではないだろうか。その意識と内地日本人への違和感を持って、たくましい生き残りの生を生きようとしたのではないだろうか。
下の男の子たちは、年下の、と言っても同い年に近い私たちには大変横暴でいつも大威張りだった。美味しいものに食べ慣れていて、大勢の召使いたちに囲まれて、自分たちは偉いと思ってきたのだろう、周りの人にも横柄な態度だった。私たち姉妹は、この従兄弟たちとは、小学校も中学も違っていたが、歳が近いせいでよく一緒に遊ぶ仲になった。それでも私はいつもいじめられたり、してやられる側で、体の大きな彼らはボス気取り振舞いを続けたのである。のちに私たちは東京へ引越しするが、彼らは大学に行くまで、館山の学校にいて、ともに高校の野球選手になって活躍した。彼らは私にカーブやノックルボールの投げ方などを教えてくれたし、カーブボールの見分け方も教えてくれたので、私はいっぱしの野球少女だったらしい。ずっと後になって、1980年代の終わり頃、アメリカから帰ってきている時に、私は北条小学校でキャッチャーをしていた男の子(渡邊さんという男性)に偶然銀座で出会った。ともに夫婦連れであったが、話に出たのは野球をした時のことだった。遊びの少なかった敗戦直後には、女の子も男の子と一緒になって、棒切れで球を打って遊んだのである。その子によると私はピッチャーだったそうで、二人とも、その時の思い出をずっと持ち続けていたのだ。
二人の従兄弟の横柄な態度は伯父譲りだった。伯父の態度はボスの態度そのもので、特に母に対しては三男の嫁扱いだった。引き上げてきた夏、居候をしている家で、暑い道を歩いて帰ってきた母が風呂に先に入ったと、ひどく叱られたことがあった。母は舅、姑に仕えたことがないので礼儀を知らないとも言われたらしい。父のことはもちろん、水田家の人々の悪口や文句を言ったことのない母が、この伯父に関しては大変厳しい評価で、いつもその態度だけではなく考え方にも批判的だった。伯父は館山に落ち着く間もなく、いろいろな事業を企画し、その大半がうまくいかなかったので、その度に尻拭いを父がしていたそうである。その中でも弟たちに家や田畑を売らせてその資金で彼らを株主に仕立てて始めた事業が失敗した時は、父母は弟たちの土地を買い直すのに奔走したということである。父や母は決して金持ちではなかったので、よほど母はこたえたのだろう。それ以来伯父は母には出入り禁止扱いにされていた。
伯父は見たところも豪傑で、水田家の男兄弟たちの中では、最も頭が良く、行動力にも優れていて、植民地天津での海運業に成功していたので、皆から一目置かれてもいたらしい。弟たちにも影響力を発揮して、その代わりに昔はよく面倒を見たということである。父は山村に育った兄弟を皆励まして教育を受けさせるように父親に交渉し続けたこの次兄が大好きで、引き上げ後の相次ぐ事業の失敗からの屈辱をなんとか軽減してあげたいと考えていたようである。
国会議員として中央で活躍するようになっていく父を故郷の人たちは暖かく、心から応援してくれていたので、伯父が事業で失敗し、いろいろな人に迷惑をかけ続けることを母は大変心配していた。しかし伯父はやがて、千葉県の金谷港と川崎をつなぐ東京湾横断フェリーの会社を設立して、事業に成功した。事業がうまくいかないときでも、母によれば子煩悩の伯父は子供たちに高価なステレオなどを買い与えて、私立大学へ行ってからも家庭教師までつけて落第しないようにしたと、母はだから子供たちが甘やかされてしまうのだと言っていた。政治家の家には子供たちに出たばかりのステレオなどを買い与える余裕など全くなかったのである。
しかし私たちにとっても、従兄弟は従兄弟で、母もまた、彼らが東京に来ると優しくして何日も家に泊まらせていた。私は彼らの人生に深く関わることも、その内面に関心を持つこともないままに自分の道を進んでいくようになるが、彼らは私の幼年期の記憶の風景に強烈な印象を刻んだことは確かなのだ。疎開先の勝山から館山へと理由もわからないままに居場所を変えていった敗戦後の生活の中で、不意に現れた風呂敷包みを背負った家族の姿は、惨めったらしく、うなだれているどころか、傍若無人なよそ者の巨人たちが侵入してきたかのようだった。その思い出の風景はどこか神話的な匂いのする遠い異国の風景のようなのだ。彼らは皆個性的で、日本の家父長制家族の中の女性や子供たちとは明らかに違って、模範生とは正反対の、世間の評判を気にしない、自由なところのある人たちだったのだ。
私にはその後の彼らの人生が順調であったかどうかはわからないが、たまに法事で親戚が集まるときに、彼らは出て来ることが少なく、一人はアフリカに行ったということであった。従姉妹たちは、一人は外務省勤務を定年まで勤め上げたし、館山で事業家になった上の従姉妹は、事業に失敗したり、家族の問題を抱えたりしたこともあったらしいが、子供たちに後を継がせて、たくましく自分なりの華のある人生を全うしたと聞いている。
父は受勲をした時、母に伯父と囲碁を打ちたいと言ったそうである。母はあまり交流がなくなっていた伯父を招いて、二人は思う存分囲碁をしたと聞いている。父は伯父のことで迷惑をかけ続けた母に気兼ねをしていたのだと思う。その頃は、私はアメリカの大学で教鞭をとっていたのだった。
館山時代は父の時代の幕開けだった。敗戦によって、父は自分のやるべき仕事、生きる場と生き方を見つけたのだ。公的な、社会的な居場所を得たことで、父の父としての存在は高まったが、家庭内での父の力は大きく凋落した。母なしに政治家の家庭は機能しないことが明らかになったし、家族としての営みはすべて母中心で進んだのだ。母は父にとっても、私たちにとっても、そして水田家にとっても、不可欠な力を持ったのである。それは戦前の夫は外で仕事、妻は家庭の中という性別役割分担に、主婦の社会的な存在意義が正式に認められたことでもあった、主婦は影の存在ではなく、実力者となったのである。
しかし、そのような生き方は母にとってはどうであったのだろうか。今では全く当たり前の参政権や親権なども母はそのとき初めて女性として得たのであった。戦後の選挙では現在までの歴史で最も多くの女性議員が誕生したし、女子大を卒業した女性たちの多くは国立大学に入り直して、学者や医者、国家公務員のキャリアーに進む人もいたし、海外の大学へ留学して、独自な人生を歩んだ女性も多かった。戦後の転換期に、女性にはそれまでになかった人生の道や社会進出の機会が開かれていたのだ。30を出たばかりの若い母にはそのような可能性を開拓していく将来が見えたはずである。
その反面、戦後の日本には戦争未亡人や戦争花嫁となって渡米した女性たち、原爆の被害者と、多くの戦争犠牲者がいた。敗戦直後は男たちと同じように闇市でも働き、内職をし、売春禁止法ができるまでは色街でも働いた。そのようにして生き延びをした女性たちだが、次第に、復興した企業での仕事は性別格差が定着し、女性の給与は男性のそれより低く、専門職への道はほとんど閉ざされていくようになる。一方では核家族の一般化で、男、夫は仕事、妻は家事育児という分担が一般化していき、女性は再び家庭に封じ込められるようになっていく。戦後の復興は、男性にとっては経済発展の戦士としての役割を、女性にとっては、その男性の労働力の再生産と子供を産み育てる生命の再生産を担う家庭内での役割に、定着させられていくのである。
疎開中にリーダーとしての資質と能力を自ら見出した母にとっては、戦後自分のキャリアーを育てる機会はあったと思う。教師としての職業に誇りを持っていた祖母は、長女には教員になる道を選ばさせていた。しかし母は政治家の妻として、父とともにその道を歩むことを決めたのだった。結婚するときに、政治家だけにはならないと約束させられた、と父は自伝で書いているが、母はそれほど嫌っていた人生の道を選ぶことが、自分のキャリアーでもあると考えたのだろうと思う。それは全くの裏方の役割だが、実際には地域の人々との交流が最も大きな仕事である役割であった。疎開での経験から母はそのことに自信を得たのだと思う。母はのちに自分の会社を経営し、また、高等学校や大学の理事長として教育事業に携わるようになるが、それらは父の遺志を継ぐという目的を持ったものでもあり、母はあくまでも父の妻として、ともに生きていく道を選んだのだと思う。その意味でも、母は個人であることを追求する新しい女性というよりは、むしろ母系家族のマトリアークのようだったのである。それは明らかに、祖母のDNAが流れていたのだった。
母は都会の中産階級家族の娘として、女学校は出たが、学者や研究者になる修行や勉強はしていなかったし、作家や芸術家でもなかった。特別な技能も身につけていなかった。しかしそのどれをも洗濯して自分のものとする機会を、30を出たばかりの母は持っていたのではないだろうか。父を助けるだけではない自分の仕事や生きる道を、母は、当時も、そして父の存命中は考えなかったのだろう。1976年父が亡くなった直後に、選挙区の支援者の方たちが、母に選挙に出て欲しいと正式に頼みに来たことがあった。母は地盤を継ぐにふさわしい人だと考えたのだろう。しかし母は頑としてそれを受けなかった。その代わりに、父の創立した大学の理事長を引き受け、以来27年間全身全霊で大学の発展に尽くした。それは父との人生を全うすることであったのだ。
私たち家族も母が代議士に出ることには反対した。何よりも、政治家としての仕事はきつく母には気楽で自由な晩年を過ごしてもらいたいというのが私たちの願いだった。すでに女性の時代は大きな曲がり角に来ていたが、男女雇用機会均等法ができるのはまだ10年先のことだった。頭の良い母は、自立した政治家として活躍するためには、政治家の妻という長年の役割が役に立つとは思わなかったのである。自分が新しい時代の女性政治家として貢献できるとは思わないという母の自己評価を、私はさすがだと思い、母の決断を尊敬した。
母は1976年、父の没後大学の理事長になると即座に女子短期大学を設立して、社会で活躍する女性のための教育プログラムに熱を入れたのである。それ戦後の女性・ジェンダーをめぐる変化を肌身で経験しながら、妻であることに甘んじた母の積年の夢だったのかもしれない。
伊香保の祖母の生徒さんの旅館で私は、祖母だけではなく母の戦後の生き方についてよく考えた。母は生涯父にとってはかけがえのないパートナーで、家庭の中では母の力の方がはるかに大きな影響力を発揮していたばかりでなく、水田家という家族共同体にとっても、その維持やまとまりを保つための中心的役割を果たす存在だった。戦後家族内での力のバランスは、母の力の上昇に比例して父の力の弱化という、洋の東西を問わず、女性の平等獲得の歴史では、古くて新しいあり方だった。政治家としての父は国際社会でも活躍するようになり、日本の経済復興を支える重要な仕事を次々とこなして、大変忙しい年月を過ごした。選挙は母にとっては責任の重い、身体的にも大変な時で、終わった後は、ひどい時に数ヶ月も全身の湿疹が治らない時もあった。私たちは杉の葉や柿の葉など、シップに効くという植物を近所にもらいに行ったものである。
疎開中は母は自分が主役の、責任のある生活を見事に生き抜いたが、戦後は政治家の妻としての役割が、公なのか私的なのか境界線が曖昧な生活の中で、父にとって母の存在が必要になればなるだけ、不燃焼な自分を感じていたのかも知れないのである。大学の理事長になってからの晩年においても、母はまだ知名度の低い大学を盛り立てようと、猛烈に忙しい生活だった。母は少しも変わることなく、「肝っ玉おっかあ」でい続けたのである。
私の館山時代、母はすでに東京に戻っての仮住まいだったが、洋服を着ることが多くなり、髪にはパーマをかけて、館山のダンス教室に通って社交ダンスを習った。建て増しした洋館で母は一人で練習をして私にステップを教えてくれたこともあった。それが悪口の種になり、母は祖母に叱られたそうであるが、母はダンスをやめることはなかった。正月に父が帰ってくると選挙区の人たちや郷土の人たちが大勢家に来て家中は大変な騒ぎだった。母は大きな魚を何匹もさばいて食事を作り、私たちは玄関で下駄番をさせられた。中には父がいる間中毎日来てくれる人もいて、総じて100人はゆうに超える来客に、私たちはお正月に晴れ着を着たことなどは一度もなかった。
館山時代は2年ほどで短かったが、父母と離れて祖父母と暮らす日常で、庭仕事や肥やし担ぎをし、祖母から日本の古典文学について色々と聞いて教わったし、俳句も毎日作った。お茶の指南も受けた。お小遣いはなく、近くの店に何かを買いにいくことは「買い食い」と言われてダメだった。その頃から自転車に乗り始めて、私はよく祖母を後ろに乗せて役場へ行ったりした。ある時、祖母が落ちてしまい、唇を紫色に腫らせてしまった。私は申し訳なくて泣いたが、祖母は平気な顔をして、薬もつけなかった。小学校4年生の自転車に乗せてもらうには勇気がいると祖父はかえって感心していた。
館山の家の風呂場は外にあった。祖母は風呂からあがると食卓に鏡を立てて、クリームを首から胸まで塗って肌の手入れを怠らず、ある時は白髪染めをして、私は仰天したことがあった。祖母の白髪姿を見たことがなかったからである。祖母も母も朝家族の前に出る時には決まって身支度を終えていたので、稀に見た祖母の風呂上がりの様子は驚きに満ちていた。他方、おしゃれで有名だった祖父はごま塩の髪を毎朝、鏡の前で櫛で真ん中で丁寧に分け、口髭を整えた。それは私が知っている限り生涯変わることのない毎朝の行事だった、その時には祖父はすでに身ごしらえを終えていて、いつもの着物をきちんと着ていた。私は毎朝そばでその様子を見ながら、絵に描いたような日常の決まりをこなしていく祖父に畏敬の念を感じたものだった。酒に酔っ払ったり、夜更けまで大勢の人たちと話し込んだり、碁を打ちながらあたりに灰を撒き散らす父とは全く違っていたのである。祖父も祖母もお酒を一滴も飲まなかった。
勝山町と館山市で過ごした小学校時代は、私の子供時代の思い出の中心を占めている。それは失われた楽園のような、信じられない子供時代の私の姿を残している、夢の風景の記憶となっているのだ。小学校の5年生で東京へ移ってから、私は雙葉学園というキリスト教の私立学園で勉強することになり、それからは学校生活も家での生活も全く違うものとなっていったのである。それはあまりにも激しい変化だったので、私の性格形成や考え方、そして情緒的な面でも、その変化は「断絶」というに近いと言えるだろと思う。それは自意識の形成なのでもあり、私の子供時代は館山で終わるのであった。東京での生活は私の精神的自立へ向けての出発だったのである。
東京から勝山へ疎開しても私はよそ者としての自覚を全く持たなかったが、東京へ帰ってきてからは、私はどうも雙葉の上品で文化の香り高い環境からはみ出したよそ者だと感じることが少なからずあったのである。友人はすぐにできたが、雙葉の生徒たちは親が雙葉出であることが多く、環境に馴染んでいる人たちばかりであった。私ともう二人が5年生への編入試験に受かって入った新参ものだった。その中の一人は阪口美奈子さんと言って、のちに演劇「アンネの日記」のアンネ役でリクルートされて、女優になった人だった。彼女もまた、映画や舞台に立つことを禁止していた雙葉では、どこかよそ者であり続けた友人だった。
私の「よそもの」意識は、まず父が政治家であるということを初めて意識させられたことからであったと思う。同時に、私の家族はキリスト教ではない「俗物家族」だという意識でもある。田舎育ちの私は雙葉では言葉遣いがまず違ったが、雙葉流のことば使いは、反対に家ではかなり笑われたりしたのだ。特に公立の男女共学の学校へ行っていた姉にはよくからかわれた。私は真っ黒に日焼けして、房州弁で喋り、学校でも友人関係でも物怖じしない、活発で明るい子供から、無口で陰気な子供になった、というのが父の意見で、父はいつもそれが気に入らなかったようだった。
確かに雙葉では「校長様」をはじめ先生方は黒衣に身を包んだ修道尼が多く、フランスやアイルランドから来た尼さんたちが多かったし、毎週のイグナチオ教会でのミサや、小学生にも必須科目だった英語とフランス語の勉強と、学校での勉学環境は館山でのそれとは全く別世界だっただけではなく、家庭の環境とも随分違っていたのだった。雙葉に馴染んでいくに従って、私は家でもよそ者意識をもつようになったのである。それは特に母に対して大きかった。
しかし、館山から東京へ移り、やがて西片町に住むようになった私の中学、高等学校時代を通して、雙葉での学園生活こそが私に文学や哲学への思考を導いたのであり、キリスト教の道徳観も考え方に影響を与えたのである。私の自意識はこの時代に形成された。今振り返ると、1948年戦後の東京へ帰るまでの田端、勝山、館山の家で過ごした子供時代だけが、どのような慚愧の念や恥ずかしい気持ちを感じることなく、ただ懐かしさだけで思い出すことのできる記憶のように思える。そこには未だ自意識で犯されていない無邪気な子供の姿が見えるのである。
2020/06/8
崖の上の家:父なるものの凋落
第三章
勝山の家
1942年の暮れに千葉県安房郡勝山町へ疎開した時は、まだ幼かったこともあって引越しの理由も何も不思議に思わずに母に連れられて新しい家へ移動したのだった。疎開という言葉も家ではあまり聞かなかった。勝山の家は龍島という小さな湾の浜辺の、松林の終わるところにある小さな家だった。八畳、六畳、そして、畳のある玄関の入り口の間、台所があり、引越してから風呂場を取り付けた。そこは父の友人で、山村聰の映画『蟹工船』の悪人船長の役を演じたこともある、俳優の平田三喜造さんが持っていた貸家だった。平田三喜造さんは勝山地域の網元で、顔役、「大いなる力」を持っているということだった。声の大きな、色黒でギョロ目の、体格のいい人で、カリスマ性に満ちているが、気さくで、母とも気が合ったらしい。よく私たちの面倒を見てくれたことを覚えている。毎朝魚を台所のバケツに投げ込んで行ってくれるので、食べ物には困らないと母はいつも言っていた。
父と平田さんがどういう友人関係なのかは今でもはっきりと知っているわけではないが、同じ房総の出身で、おそらく同い年だったと思うので、安房中学時代の友人だったかもしれない。父は学生時代はマルクスに心酔し、反戦運動に関わっていたので、小林多喜二の映画に出演した三喜造さんには、同窓の友人という以上の親しさを覚えていたのかもしれない。文学青年だったという父なので、演劇にも興味があり、網元の息子でありながら俳優をしているユニークな平田さんに特別な親しみを感じていたのだろう。戦後山村聰さんが、西片の家に何度か来られたことも覚えている。千田是也さんも来られたことがあった。父は戦後の演劇の復興にも貢献したのかもしれない。少なくとも国立劇場の建設に深く関係したのは確かである。
勝山町は、房総半島を上総と下総に分ける鋸山を超えて、次が保養地として名の知れた保田町、そして次が勝山町で、保田、勝山、岩井、富浦、那古船形、館山と続く南房総の東京湾に面した内房総海岸が半島の先へ続く一帯の海岸線に面している。漁業の町でもあるが、農業も盛んで、房総半島を内房から山越えして、鴨川市をはじめとする外房地域まで続く広い山間地域を後ろに背負った、いわば海と山のある、農業や花栽培も盛んな、温暖な地域の町だった。現在では保田、岩井と合併して鋸南町になっている。その名の通り、険しいノコギリの刃のような山形を持つ鋸山の南にある町であり、この山を隔てて、気候も、また、人の気質や文化も異なることがわかる。現在は鴨川へ続く嶺岡道が鈴蘭道として有名である。
鋸山の長いトンネルを越えると、海が拓けて、川端康成の『雪国』とは反対に、明るい別世界が目の前に開ける。しかし、戦時中はここを通る時には車窓にスクリーンを降ろされて、外は何も見えないようになった。内房線の汽車は鋸山以南にはトンネルがたくさんあって、煙と煤で目が痛くなるのが子供時代には苦手だった。
隣町の保田町は勝山町に比べて古くから別荘地として名が通っていたおしゃれな雰囲気のある町で、物理学者で歌人の石原純博士と歌人の原阿佐緒が世間を騒がせた大恋愛の末に愛の居を構えたところであった。石原純は、この事件で東北大学を辞めることになって、保田町の丘の上に瀟洒な家を建て、二人の世間を逃れた愛の住処としたのである。勝山町にはそのような有名なエピソードは残っていなかったらしいが、関東大震災の時にはいくつかの別荘が倒れて、その家人の救済や復興に土地の若者たちが大きな力を発揮したという。平田さんは別荘に来ていた東京のお嬢さんと結婚したと聞いていたので、勝山にも別荘があったのだし、別荘には原阿佐緒に劣らぬ優雅な令嬢がいたのだろう。
龍島は、その曲がった形が龍に似ているところからその名になったのか、あるいは、その静かな湾と浜辺の持つ雰囲気が、どこかこの世離れをしていて、乙姫様のいる幻の世界、夢の中の場所のような幻想をいだかせることからそう呼ばれてきたのかもしれない。事実その浜辺を浦島太郎が釣竿を肩に歩いていてもおかしくはないのんびりとして、賑わいのないあたりの景色なのだった。勝山漁港から離れた,保田との境に近い湾で、漁港ではなく、浜辺付近に住む漁師の人たちも、自分の小さな船は持っていても、本格的な漁は網元の傘下で行なっていた。船がつくほどの大きな桟橋は龍島の湾にはなかった。それだけに、水泳にはもってこいの浜辺で、人の少ない、まるで今で言えばプライベートビーチのように、小さな波が寄せては返す、静かで美しい海辺だった。近くに浮島という島がぽっかりと浮かんでいて、水泳が得意だった母やすぐに上手になった姉はそこまで遠泳していったものだったが、まだ幼かった私は、彼らが帰って来るのを浜辺で一人座って待っていた。竜島は隠れ里のような佇まいがあり、疎開生活の背景としてはふさわしい雰囲気に満ちていた。
松林すぐそばの家は、低い垣根はあっても、門構えと言えるようなものはなく、塀で囲まれた都会の家に住み慣れた私たちには、何となく開放的過ぎる感じがした。家の周りにはあまり民家がなかったので、心もとない感じがした。夜になると松林を通り抜ける風と、潮騒の音が、絶え間なく聞こえる。街灯の一つもない真っ暗な闇の夜の経験も新しく、疎開生活の第一印象を心に刻み付けることになった。それだけに水平線に大きな夕日が沈む浜辺の風景の輝きは驚きを与えたし、月夜の明るさにも感嘆した。お月様が大きいということも初めて知ったのだった。
雨を知ったのも勝山のこの家でだった。家が小さく、二間とも縁側を隔てて庭に開けていたから、雨が降ると雨足が庭の地面に落ちる様子を眺めることができた。土砂降りの雨の時には庭はたちまち水浸しになり、そして雨が止むといつも庭先の空に虹が出た。しかし最も強烈な経験は台風だった。房総半島は台風に見舞われることで知られているが、扉や窓に杭を打ち、テープを張って抑えても、暴風雨の威力は、その風の轟音と激しい雨で、都会では経験したことのない大事なのだった。勝山時代に何度台風を経験をしたことだろうか。敗戦の日の前も台風が通過し、あたり一面、家の軒下も水浸しになったのだった。
家の前には使われていない小さな土地があり、そこへは簡単な木戸がついているだけだったが、強盗やドロボーなどの心配は一切ないから、と平田三喜造さんは母を安心させたというし、その空き地の脇に、倉庫のような小さな二階建ての家があり、そこに平田さんの会社で働いている若い男性が住んでいたので、安心だと母も言っていた。その人は足に障害があり、平田さんの会社でも雑用係だったようだが、実に気のいい人で、ある日バケツいっぱいのカニを置いていき、大喜びをした母はすっかりお腹を壊してしまったことがあった。毎朝欠かさず魚を持ってきてくれるだけではなく、畑仕事も教えてくれたり、垣根の直しもしてくれた。夕方になると二階の窓枠に座って、ハーモニカをよく吹いていた。
私たち母と姉妹が、りっちゃんを連れてそこに住むようになってから、母は実に早く海辺の生活に対応し、生き生きとして、たくましさを感じさせるように見えた。水を得た魚というような、やることができたというような、熱意のようなものが感じられたのだ。子供たちを守らなければならないという気持も強かったのかもしれない。戦争は激しさを増していたが、まだ、敗戦が近づく気配は色濃く感じられなかった。風呂場のなかった引越し当初は、町の銭湯に行ったのが、珍しかったのか記憶に残っている。庭先での行水も始めてで実に楽しかった。その頃は都会でも風呂場のある家が全部ではなくて、隣の風呂を借りるという言い方も普通に使われていたのだった。
母が勝山での生活に苦情を言うのを聞いたことはなかった。母はその時は30歳になったばかりの頃だったと思う。東京で生まれ育った母には、何もかも不便な生活だったのではないかと思うが、反対に浜辺で泳いだりするのを楽しむ様子に新しい母の印象を持ったことを覚えている。青鼻を垂らし、髪にシラミを飼った子供達の間で私たちを育てることに神経を尖らせたはずであるが、それらの「ガキども」を寄せ付けないことなど全くなく、反対に、パンケーキなどを作って、いじめられないように、なつかせようとしたりした。東京にはよく帰って、少しづつ私たちの着物や人形を持ち帰り、塩や砂糖、シーツやノートや紙や鉛筆などを調達しては持って帰ってきた。私はそんな母の姿に影響されて、やがて裸足で駆け回り、勝山弁を話す浜っ子になった。大人たちに命じられて、よく土地の子供達と背負いかごを背負って松林に松の落ち葉を集めに行った。集めた松葉は焚き火にしたり、そのほかにも何かに使われたのだと思う。松ぼっくりもたくさん拾ったし、子供達はマツヤニも取っていた。松林は海岸線に沿ってずっと続いていて、子供達にとっては、大人たちの関与から離れた別世界だった。私たち家族は戦争が終わった翌年の1946年まで勝山の家に住んで、私はそこで小学校に入学した。
疎開生活では父は東京の家での私の生活でそうだったよりも、さらにもっと不在だった。父が帰って来ることは大変稀で、その時はいつも母や土地の知人たちと過ごす時間が貴重らしく、子供達は構いつけられることもなく、外に遊びに行かせられることが多かった。父は30歳半ばを過ぎた頃だったが、時代に押しつぶされる様子や、ビクビクしたところなど全くなく、また、都会的な雰囲気も持っていなかった。父は房総の温暖でおおらかな風土をその人間性に受け継いでいた人なのだった。父の人柄の醸し出すこの雰囲気は生涯変わることはなかったのである。
それに反して、群馬県の太田出身の母は、かかあ天下文化のDNAを祖母から受け継ぎ、何事にもめげず、負けん気で、立ち向かっていくたくましさに満ちていた。生き残りに長けた「肝っ玉おっか」といった雰囲気は外見やその容貌にはないが、実に敏捷で、勘も良く、優しさも備えていて、すぐに土地の人たちと親しみ、信頼されるようになった。
最初の頃だが、基地の若い兵隊さんたちがよく遊びに来たことがあった。母はその人たちに色々食事を作ってあげていたし、彼らの話を聞いてあげていた。そのことが評判になってはいけないと知人が父に忠告をしたそうだが、父はやがて戦場に出ていく若者たちへの母の慰めをむしろ大切に思っていたようだった。戦争が終焉に近づくにつれて、兵隊さんたちはぱったり来なくなった。
私は小学校に入るまでの短い日々をいつも母と一緒で、母の毎日の時間を私はべったりとくっついて共有する日常生活だった。初めての「普通」の幼年時代を経験したようなことだったのではないだろうか。姉はすぐに町の小学校に編入したが、私は幼稚園もなく、一人では遊ぶ場も知らない。第一言葉がよくわからないし、それを使えない。房総の浜辺地域の言葉は大変荒っぽかったのだった。仕方なしに初めのうちは日常生活の時間を母のそばで、母の後をついて回っていることで過ごしたのである。母との身体的な距離が最短に縮まった時代だった。しかし小学校に入るとその時間もすぐに変わっていった。
疎開生活は女だけで成り立った生活だった。家には父のいる部屋や場所はなく、母がここ家の主人だった。外との関係も、母は近所の主婦たちとすぐに仲良くなって、かなりのリーダーシップをとって子供達の病気や怪我の手当て、衛生上の注意などをしていた。母が最も強いお山の大将ぶりを発揮したのは、食糧難が急速に進んでいくに従って、山間部の農村へ買い出しに行くチームを編成した時だった。食物と交換する物資は、母が全て調達したし、それらは着物や靴など当時はほとんど田舎では手に入らなかったものだった。それに加えて、東京から買いだめしてきたり、持って帰ったりした塩や砂糖なども入っていたので、買い出しはかなりいい成果をあげたのだと思う。大きな背負い籠を背負って、数人で山の村へ朝早く出かけて行く母の姿はなんとも頼もしかった。帰って来れば、米やいも、牛乳、鶏肉、野菜などを含む食材を色々な人たちに分配するのも母だった。庭にゴザを敷いて、母は買い出しに行かなかった近所の人たちにも、食料品を分けた。中でも鶏肉は貴重な戦利品で、母は包丁で幾人分かにさばいて分けていた。そんな時の母は猿むらのボスの風格があった。
父が選挙に出た時に、最も得票数の多かったのは、父の生まれた鴨川市を抜いて勝山だったというのが、よく母が自慢したことだったが、事実、そのことは、その時代に発揮した母のリーダーとしての資質と能力の高さを表しているのだと思う。母は色白で、当時の女性としては背が高く、背筋がまっすぐに伸びた活動的な女性だった。女学校時代はテニスやバスケット、ピンポンの選手だった体育系の女性で、走ることや水泳はとにかく達者だった。親が進める父との結婚も、初めは大変嫌がっていたという話を母の姉の和歌子叔母からよく聞いたのだが、一度決まってからは、愚痴ったり、いじいじすることなどなく、失業中の父の下宿へお弁当を作って差し入れに行ったそうである。その当時、友人の下宿に宿狩りをしていた父は、数人の安房出身の友人たちと共同生活をしていたそうである。肩書きや資産などにこだわらなかった若い母の性格は、その行動力とともに、体育系の性格を生まれながらに持っていたからかもしれない。
むしろ父の方が文学青年で、私が読んだことのある婚約時代に二人が交わした手紙では、父は倉田百三の『出家とその弟子』について書いしたりている。母の女学校時代のエピソードは、のちに卒業校の第八高女(八潮高校)の友人たちと俳句の会などを作って交流を温めたこともあって、私たちはいくつかの話を聞くことができた。掃除の時に窓ガラスを拭きながら、「カチューシャかわいや、別れの辛さ」と大きな声で歌って、先生に厳しく叱られた話、「不思議なマント」や「流浪の民」などの劇でいつも主役を演じた話など、小さい時に聞いた母が唄う歌を思い出してなるほどと思ったものである。母にとっても女学校時代は、最も自由で夢の多い時代だったのかもしれない。それも短い期間で、すぐに大恐慌や軍事政権の出現で、女性たちが自由を奪われた時代がやってきたのだが、母が少女時代に養った明るく、物怖じしない行動力に満ちた性格は、その抑圧の時代を生き抜いて、戦後は本領を発揮することになったように思う。
意気揚々とした物々交換の買い出しも、次第に困難になっていった。食べ物はほとんど手に入らなくなり、少量の芋や大根ばかりを持ち帰って来るようになった。魚だけが命綱だったが、さすがの網元も非常時に漁業はうまく成り立たず、私たちは毎朝バケツに入れてくれていた魚の代わりに、自分たちで、岩に腰掛けて魚釣りをした。それでも私たちの釣り糸に引っかかる魚に事欠かなかったほど、房総の海は豊かだったのである。家の前の空き地に麦畑を作った。庭にサツマイモを植えた。自然に生えている木苺やグミの実、アケビ、桑の実など食べられるものは皆食べた。柿や栗、桃、みかん、夏みかん、西瓜、まくわ瓜、びわなどは何らかの形で手に入ったが、それもだんだんと難しくなり、渋柿と夏みかんだけがそこいらの農家の庭にも実をたわわに実らせていた。今でも私は夏みかんが大好物である。
1945年敗戦の年になると食糧難は最も厳しくなって、私たちの食事にはすいとんが頻繁に出るようになった。その頃には、母方の祖父母が、母の兄嫁の実家の山梨県の上野原から勝山の私たちと一緒に住むようになっていて、房総の温暖な気候と、とにかく何らかの食べ物があることを「恵まれている」と口癖のように言っていた。祖父母が敗戦後も館山の家で生涯を送るようになったのも、房総の土地が気に入ったこともあったのだと思う。
勝山時代は母の存在が大きな比重を占める時代だったが、祖父母の存在が次第に大きな影響を及ぼすようになった時でもあった。私たちそれまでは祖父母と一緒に住む経験がなかったが、勝山疎開時代から東京へ帰る1948年まで、祖父母と日常を過ごす生活が続いたのである。
祖父町田均は俳人で文人タイプの役人だったが、イタリヤやフランスなどの欧州、台湾や中国などに勤務した経験から、かなりのハイカラであったそうである。メロンやマンゴなどの果物が祖父母の家にはいつもあったのは、祖父のハイカラ時代の産物だったのかもしれない。その頃は逓信省を退職していて、毎日俳句を作り、私たちに俳句や百人一首を教えてくれた。新聞紙をかるたサイズに切り、そこに一枚づつ上の句と下の句を筆で書いてくれた。祖父は達筆であったこともあってか、私にとっては新聞紙の薄い紙と本物のカルタの違いは知る由もなかったので、この新聞紙カルタが私の百人一首の世界への導入路となったのである。祖母は茶道の教師をしていたので、勝山で私たちに手ほどきを初めてくれた。私はそのどちらにも夢中になり、中でも百人一首は大人の県大会出場者を負かすほど腕を上げて大いに褒めそやされたものだった。俳句を作ることが長く日常のことになったのはこの疎開時代に祖父母と一緒に暮らしたお陰だった。逓信省は運輸省と国土交通省、外務省とも仕事が総合的に一つだった戦前の省庁で、祖父はとにかく西洋も中国も知っている、いわば当時のグローバル人だった。母は名を清子(せいこ)というが、祖父が中国清時代に赴任している時に生まれたのでそう名付けられたという。祖父は無口で、口髭を生やした面長の風貌が、細身の着流し風の着物姿と相まって、いつも謎めいていた。私たちとはあまり話をしなかったが、俳句だけはよく教えてくれたのである。
祖父の実家は大田の呑龍寺の住職で、代々の墓がその寺にはあった。私たち姉妹は幼い頃呑龍坊主にさせられた。祖母は丹後家という武士の家柄の娘で、祖父とは反対に自分の意見をはっきりという女性だった。丹後の局の末裔だろうと、からかわれたほど、物怖じしない人だった。結婚前は小学校の先生をしていたのだから、教養豊かで、暗唱していた平家物語を語ってくれたりした。敗戦直後上野原の道で進駐軍のジープを呼び止め、「ウエノハラステーションダウン」とゆく先を言って乗せてもらったという逸話が残っている。好奇心が強くてなんでも聞きたがり、質問をして、知恵熱が出るぞ、と父にからかわれていた。
母方の若い叔父たちがよくやってきて私たちの遊び相手になってくれたのも楽しい思い出になっている。母の長兄基(しげき)叔父は日本郵船に勤めていて、話が実に上手な人だったので、お話をせがむのが、私たちの楽しみだった。母の下の弟直(裕康)叔父は通産省に勤め始めたところだったが、独身の身軽さでしばしば勝山を訪ねてきた。この叔父は絵が上手で、また美声の持ち主で、歌舞伎の人物を紙に書いて切り取り、紙人形で演じて見せてくれた。二人の叔父はともに俳句をよくし、祖父母の馬込の家では毎月句会を開いていたので、勝山でも彼らが来ると祖父母や母は、私たちも末席に加えて句会をした。特選をとったいくつかの句は今でも私の自慢の句である。その中の一つ、「大人まで乗り出して食う初秋刀魚」は、姉の「割り箸の先を焦がして秋刀魚焼く」とともに特選となったのである。
母の弟の直叔父はやがてお見合いをして結婚することになった。お見合い写真を私も見せてもらったが、美しい人で感心した。裕福な医者の娘でピアノが上手だということだった。その人が何かで入院したというので、母は私たち姉妹を連れて東京までお見舞いに行った。母にとっても初めてその人に会う機会だったのではないだろうか。私たちは着ていくような洋服を一枚も持っていなかったが、母は買いだめして持って来たシーツを裁断して、二人に洋服を作ってくれた。スカートはウエストをくりぬいただけの代物だったが、8枚はぎフレヤーカートのようにヒラヒラゴワゴワした、真っ白な洋服になった。叔母はその時の、お揃いのシーツ服を着た私たち姉妹のことを、結婚してからもよく話していた。
温暖で開放的、「かかあが強い」と言われるほど女性たちが活発で、人情の厚い風土の房総での暮らしは決して苦しくはなかったように覚えているが、それが非常事態下の異常な暮らしであることが、次第に日々鋭く感じられるようになっていった。本土への空襲が激しくなっていったのである。庭先には防空壕を掘ってあって、空襲警報が鳴るたびに私たちは枕元に用意しておく防空頭巾を被って、急いで逃げ込む日が毎日になっていった。房総は米軍機が東京を空襲する道にあたるので、その行き帰りに私たちの頭上を通って行ったのである。時には残った爆弾を帰り道で落としていくことがあり、機上掃射(機上射撃)という襲撃、つまり、地上で動いているものすれすれに近づいて爆撃機から狙い撃ちをする襲撃が、私たちを震え上がらせた。空襲警報が鳴ると小学生は家に帰るように命じられるのだが、私たちの家は勝山小学校からかなり離れていたので、私は姉に手を引かれて、駅の向こう側の学校から、線路を越えて、長い田んぼの一本道を懸命に走って帰った。道の終わる田んぼの果てに母が待っていてくれる。ある時は途中で私たちが狙われたと思い、田んぼの畦道に転げこんで身を伏せたこともあった。
勝山駅の近くで汽車が機上掃射に会い、多くの死者が出たことがあった。母はその時、母親をなくした赤ん坊を預かってしばらく育てたこともあった。東京が空襲に遭うと、東京湾を超えて東京付近の空が真っ赤になる。恐ろしいが興奮に満ちたような、遠くの景色を松林の端から見たことがしばしばあった。母にとっては東京の家へ帰ることが危険になっていったことで、帰ってくるまで私たちは不安に怯えていたのである。それでもお内裏様を持って帰ってきてくれた時には大変嬉しかった。それだけは買い出しにも使わなかったので、以来母は、孫たちのためにずっと飾っていた。着物は母のものも私たちのものもすっかりなくなった。
東京の田端の家にも庭に大きな防空壕を掘ってあったが、私は入ったことがなかった。しかし、勝山の家の庭先に作られた小さな防空壕へは毎晩のように入り、その狭い暗闇の空間での時間は、勝山時代の特別な経験で、長く心の風景となっている。家族の他に幾人かが入れるほどの小さな穴倉だった。爆撃に耐えられるような代物ではなかったが、危険な時をやり過ごす、隠れている、という意識がこの暗闇の時間を満たした。小児喘息持ちの姉のひゅうひゅうという息遣い、狭い場所に身体を丸めて座り、外を遮断し、内に閉じこもる意識が全身を覆ううちに寝てしまっていた。警報が解除される頃には、朝になっていた時もあるし、母に抱かれて家の布団に戻されていることもあった。警報が解除されるというのは、明るい外部に出ることでもあり、心地よい安心ないつもの布団に目覚めることでもあった。
姉の発作がひどい時もあった。母は姉の体にからしの湿布をするのだが、そのキツイ匂いが穴ぐらの空気の匂いだった。姉は小学校の4年生ごろだったからまだ幼かったが、息をするのが苦しいと喘ぐ姉をそばで見るのは非常事態の意識をさらに強くした。それは命に関わることなのだと。私が内にこもる暗闇の時間を何を考えて過ごしたかは覚えていないが、姉のそばで自分も息苦しくなり、目を固く閉じていたのだった。
勝山小学校に入った時のことは今でも忘れることができない思い出となっている。手元に残っている写真には、広いレースの襟のついた黒い天鵞絨の洋服を着て、担任の先生と防空頭巾を被った友達たちと写っている私がいる。初めての日、私が校庭に入ると、多くの子供たちに囲まれてしまい、私は泣き出したということである。それ以来、学校のそばまで行くと、急に尻込みをして校門から入りたがらなくなったということである。姉を手こずらせる毎日で、先生が出てきてくれてやっと教室へ入ることができたのだという。
しかしそんなことはすぐになくなって、私は土地の子供と同じように軍事下の国民小学校教育を受け、一方では裸足で駆け回り、自分のことを「おれ」と呼び、髪にはシラミも住まわせるようになった。敗戦後、米軍の兵隊さんたちに皆並ばされてDDTを髪に散布されたのである。りっちゃんが茨城の田舎から奉公に着た時に、トラホームを患っていたことに懲りている母は、目だけは決して手で触ってはいけないと厳しく言ったが、そのほかはダメ出しは何もなく、私は他の子供達と変わらない浜っ子にすぐになっていった。その代わりにたくさんの遊び友達ができた。泣き虫だった私は、元気で明るい性格だと言われるようになり、成績も良く、通信簿に「将来が嘱望される」と先生が書いてくれたのを母が自慢にしていて、その小学校一年生の通信簿を大切にとっておいていた。留学から帰ってそれを見た時には忘れていた母の疎開時代の姿を思い出して、涙ぐんだのだった。
小学校時代は何もわからない一年生から三年生の中ばまでを勝山小学校で過ごしたが、その時の先生方の印象は鮮明な記憶となっている。一年生の初めての担任の先生は、「風呂屋の石井の娘」で、実に聡明で美しい人だった。その後は校長先生の娘さんの高橋美恵子先生で、この先生が通信簿に将来が嘱望されると書いてくれた先生で、私は随分と励まされて、勉強が得意になった。三年の時の小宮先生は、戦後先生を辞められた後は東京で母の会社に勤めるようになり、それからはよくお会いするようになったが、私はいつまでも小学生扱いをされた。
戦前の田舎町であっても、学校の先生方はどの人も皆聡明で、知的で、物知りで、町の人たちに信頼され、一目おかれていたのである。彼女たちは、たとえば『二十四の瞳』など、よく物語や映画で見る先生のイメージそのままで、明治以後の日本の文化形成には欠かせない存在であったことがわかる。小学校の先生にはその頃から女性が多かった。知的な女性にとって開かれていた少ない知的な職業だったのである。農業や家内工業、商家を除けば、キャリアーとしての職業に就く女性は少なく、女性が働ける職は、看護師、バスの車掌や電話の交換手、デパートの売り子など大変限られていたのである。その中で、学校の教師は、子供達にとっても、村や町の知的、道徳的意見番としても質の高い人たちを明治以来生み出してきたのだと思う。
小学校なので軍事教練などはなく、軍人の姿も構内には見えない、比較的のんびりとした学校生活ではあってが、毎朝列を作って天皇陛下の写真に礼をしてから教室に入ることや、教室にも天皇陛下の写真があり、天皇のことが語られる時には背筋を伸ばして、居を正さなければならなかったことなどが鮮明な記憶に残っている。私はすっかり土地に馴染んで疎開してきたという意識を一切持たないで居たが、東京から勝山に疎開してくる子供が意外と少なかったのは、房総が東京に近くてあまり安全だと思われていなかったからだと思う。その数少ない疎開者の中の一人が、のちに東京女子大学の同期生となったことで再会し、それ以来同じ分野の研究者としてのキャリアを持つようになり、交友関係が続いている。これも戦争による奇縁だと言えるだろう。
すぐに仲の良い遊び友達がたくさんできた。中でも近くの旅館の子供の松本孝ちゃん(孝子さん)、薬屋の池田みどりちゃんとは毎日、毎日飽きることなく下校後も遊んだ。宮下初江ちゃんはのちに学校の先生になり、字の見事に美しい大変知的な女性になったが、その頃は小さくて色白なのに、負けずに裸足で駆け回って遊んだ。孝ちゃんは旅館を継いで立派な女将になったし、みどりちゃんは賢い子だと母がよく言っていたが、薬剤師になって薬局を継いだ。戦後の経済の復活の中で、そして、日本の国際的な発展の中で、敗戦国日本の田舎町のはなたれ小僧だった私たちも皆なんとか格好のつく先進国の女性になっていったのである。1990年代には何度か小学校の同窓会に呼んでもらった。父の選挙や、城西国際大学が東金にできたこともあって、長い留学時代の空白はあっても、疎開時代の友人たちとの交流が、時間を隔ててもまた復活できたことは本当に幸運でもあり、嬉しいことだった。東京では戦災で人々は住んでいたところを離れなければならず、皆バラバラになった。地方の町でも戦後は都会に移住する人も多く、子供時代の友達の消息が全部わかるということはなかったのである。
房総には海軍や陸軍の基地があり、内房線の上総湊以南の先は機密地帯だった。疎開した最初の頃は房総の基地に駐屯している若い兵隊さんが、街中を歩いている姿を見かけることもあった。我が家へ来る若い兵隊さんの中には、母に個人的な相談をしたり、小説の話などをしに来る人もいたということである。戦況は危機的になっていくばかりの頃であったが、戦地の前線とは異なって、国内の基地にいた兵隊さんには、まだ微かな余裕があったのだと思う。しかしそれもすぐになくなった。兵隊さんは皆戦地に駆り出されていったのだ。戦地の悲惨な状況を知るのは、戦後になってからだったのである。
房総地帯はまた、艦砲射撃の的地でもあった。中でも太平洋に面する外房一帯は、警戒を強めていて、父の生地である鴨川市も危ないという噂が流れていた。房総はこのように決して常識的には安全な場所、疎開先でなかったが、千葉県の東京に近い地域は空襲を受けたが、房総は空襲の被害はほとんどなく終わったのである。
私たちの疎開中の父の東京での生活は不便そのものだったと思うが、その頃は早稲田の建築科に在学中の父の長兄の長男、私たちの従兄(水田利根郎)が、父と一緒に田端に住んでいて、一人ということはなかった。妻子は安全な場所に置き、自分は働くという夫のジェンダー役割を父は忠実に実行していたわけだが、3月10日の東京大空襲で渡辺町の家が全焼してしまうと、大森の母の実家に一時滞在し、そこも5月24日の大空襲で焼け出されたあとは、東京で住む場所がなくなってしまったのである。
三月十日の大空襲の直後、父の会社の人が勝山に訪ねてきた。私たちはちょうど防空壕に入っている時だった。彼は大変申しわけなさそうに、実は大変なことになりまして、と口ごもりながら切り出し、私たちはてっきり父の身に何かがあったのだと思った。家が焼けたと聞いて、母はなんだとばかりにホッとして笑い出したし、私たちもそれにつられて安心し笑い出した。家が消滅したと聞いて笑ったのは、おそらく私たちだけではないだろうか。従兄は36発の焼夷弾が落とされた家から命からがら逃げ出して、毛布一枚とたまたま近くにあった蓄音機を持って、大森の祖父母の家まで歩いて逃げて行ったということである。手に大火傷を負ったが、しばらくして勝山へ大きな蓄音機を持って現れた。この蓄音機は敗戦後の欠乏生活で大いに楽しみを与えてくれたのである。水田家の長男の長男に当たるこの従兄は大学卒業後は建築家として活躍をして長い生涯を送った。
疎開生活は私の幼年後期と言える時期に当たるが、物ごとが分かっているようで、何もわからない無邪気な時代だった。戦争の怖さを知っていたのか、それほど感じなかったのか、今から思うと不思議な気がする。しかしこの頃に深層意識が出来つつあったことも確かなのだと思う。記憶のことの中には確かな心の風景があるからだ。疎開中の経験はその中の原風景でもある。父と母の姿も、時とともに影のように輪郭だけに薄れていくと同時に、鮮明な、固定されたイメージとしてその風景に確かん位置を占めている。それはある意味で、私の家族の原風景でもあった。この風景は幼い私の心の風景でもあり、それはそれからの私の心の原風景なのであった。
敗戦の直前父が帰ってきて「負けた」と母に話したそうである。その日は私は夕方まで浜辺で姉と下駄隠しをして遊んでいた。父が帰ってきたから家に帰りなさいと呼びに来られたが、隠した下駄が見つからないままだった。姉が先に帰って、私は下駄を諦めて片方は裸足で、一人遅れて家に帰った。松林を抜けると、大きな真っ赤な月が昇っていた。
異常なこと、何か大変なことが起こったのだ、という感じが心を捉えて、私は畏敬の念に駆られたことをおぼえている。家では数人の人たちが父や母と話し込んでいた。父はそのまま東京へ帰らなかった。それからの数日、は色々な人が入れ替わり立ち替わり家に来て、そして大雨になり、洪水が起こって勝山川が氾濫した。
その8月には母のすぐ下の弟の正叔父が亡くなった。この叔父は東北大学を出て銀行かどこかに勤めていたが、学生時代には父から本を借りては箱だけを棚に残して、あとは全部本屋へ売ってしまった、というほどの豪傑で、父とは気があうらしかった。父を東京鋼板という会社設立へ誘った人は、この叔父の結婚した人の養父だったのである。叔父は戦争中に腸結核を患い、終戦日前後に亡くなった。どさくさの最中で、誰も見舞いも、別れもせず、そして叔父の死も知らず、松子さんと言う叔母はずっと叔父の体を抱いていたということを聞いた。母はその知らせを後で聞いて、文字通り泣き崩れたし、私も、この叔母と叔父の非常時下の愛の話はそれからもずっと心を占めるようになった。
8月15日は洪水の後で、私はいつもの遊び友達と水かさの増した川の土手を歩いて海まで行った記憶がある。玉音放送の後で、家中も町中もシーンとしていた。海も濁っていて、私たちはなぜか怖くなり、無口になってそれぞれの家に帰った。庭には洪水で水浸しになったものもの、布団やシーツなどいつもの洗濯物干しでは見慣れない様々なものが庭いっぱいに干されていて、その中には私の着物もあった。せっかく買い出しから逃れたのに、水に濡れて着られなくなってしまったと母は悔しがっていた。その後の数日は子供達は全く構われることがなく過ぎたが、急に母から九重の伯母の家に行くと言われて、荷物を持って父母とともに汽車に乗った。基地が近いので、兵隊たちが暴動を起こすのではないかと父が心配したということらしかった。
それからの何週間かを私たちは九重の伯母の大きな家で過ごした。その頃伯父は長い間結核を患った後で亡くなっていたのである。伯母の家には父の母、私の祖母が曽呂村から移って一緒に住んでいた。伯母の家には陸軍の将校たちが泊まっていて、暴動が起きるような時にはそこが安全だろうということらしかった。それが当たっていたかどうかは疑問である。私の記憶にある将校たちは毎晩お酒に酔って、サーベルを振り回す人もいたからである。
すぐに父母は私たちを置いて、勝山に帰って行き、私と姉は伯母の世話になってしばらく暮らすようになった。伯母の家は、大層に立派な造りの屋敷で、玄関が五つあった。第一玄関は立派な日本庭園に開ける広い接客用の部屋やそれに続く日本間がある家の正式な入り口で滅多に使われなかった。第二玄関は、洋館への入り口であった。二階建ての洋館で、一階は客間、二階は寝室と書斎があった。玄関の前には大きなバナナの木があり、当時バナナの木は富裕層の流行りだったそうである。洋風の庭ができていて、バラの花や、花の咲く木が大きく聳えていた。第三玄関は一般の来客を迎える入り口で、客間と仏壇が置かれている仏間があった。その次には家の者や親しい人などが出入りする玄関があり、囲炉裏のある板敷きの居間とその奥にコタツのある畳の部屋が見えた。そこが祖母の居場所だった。暖炉のある板の間からは石床の台所と広い土間につながっていて、土間へ入る玄関がこれもかなりの趣を持って作られていた。その隣には、収納庫や貯蔵庫のような建物の部分があり、色々な人たちや小作人たちが、作業をしたり、物を運んだりして出入りをしていた。
家の裏側は日本庭園のある客間の部分、洋館の部分、そして家族のいる場所などが皆繋がっていて、寝室となる畳の部屋がいくつも並んでいた。私たちはその一間に寝起きをしていたのだが、それらをつないで押入れがあり、布団や座布団などがぎっしり入っていた。広い屋根裏部屋があり、そこには食器や書画骨董品が置かれていた。
母屋の脇には牛や馬のいる小屋があり、作業場となっていて、野菜や穀物がゴザの上に広げられることが多かった。家の裏には裏山があり、しいたけが栽培されていたり、山菜や薪をとったりしていたらしかった。大きな地主の家だったので、小作人たちが絶えず出入りをしていて、戦争中で人手がなくなったと伯母は嘆いていたが、農作業が中断されることはなかったようである。比較的のんびりとした戦時下の生活だったことが感じられたと、母は言っていた。この家の凋落はまさに敗戦とともに始まったのである。農地改革で広い農地は没収されて、裏山と内房線の線路を隔てた畑だけがかろうじて残ったのである。
幼い私には伯母の家での暮らしは冒険に満ちたもので、下男をしていた人が、よく山へ連れていってくれた。椎茸の収穫を手伝ったり、牛の世話や乳搾りを手伝わせてくれたりした。それは役に立たない遊びの域を出ないものだったが、私にとってはこれまで経験したことのない冒険ばかりで、毎日のほとんどすべての時間を外で過ごした。
九重のてい伯母は水田家の長女で、安房女子学校ではその頃も語り継がれるほどの優秀な才女だったということである。ずっと後になって私は城西国際大学の学生募集で安房女子高等学校を訪ねたことがあったが、その時も、ずいぶん前の話なのに伯母のことを話してくださった先生がいらした。安房女子高等学校はその後、安房高校と合併して男女共学の高等学校になった。伯母は房総地方では大きな地主の半沢家に嫁いだが、夫は結核を患って、あまり地主としての仕事や小作の面倒などを見ることができなかったという。伯母は代わりに半沢家の財政、農業、林業などの経営、小作人との契約やその世話、そして村の世話役など、すべてを伯父に代わって受け持ち、慕われる半沢家を作り上げたということである。父の大学の授業料はこの伯母が引き受けてくれたということで、父は生涯感謝していた。亡くなったことを知った朝の句があり、父の自伝『蕗のとう』には、その日大蔵大臣として予算を決めるために、すぐに駆けつけられなかったことが書かれている。
それだけの女傑であったから、伯母はなかなか厳しいところのある人で、母は小姑に当たるこの伯母に、嫁としてばかりでなく、頭脳明晰な、やり手の年長女性として、一目置いていた。伯母のところで厄介になっていた日々は、小学校の高学年で物事がわかる姉の方は気難しい伯母に気を使うことが多かったらしく、私の経験とはかなり異なる生活で、肩身の狭い思いもしたそうである。姉は小児喘息をずっと患っていたので、温度の違いや高い湿度に敏感で、一旦発作が起こると大変だった。背中にカラシを塗った布を貼ったり、蒸気を吸わせたり、と喘息は辛い病気で、姉の発作が起きないかと、母はいつも心配していた。母のいない間、姉は発作が起こりそうになると一人で色々抑える工夫をしていたらしく、寒さが防げない、典型的な日本家屋造りの大きな屋敷での生活は決して快適ではなかったようである。
伯母は戦後も長く生きて、目が見えなくなった祖母が1961年に亡くなるまで水田家の本家が九重に移ったかのように、親戚が訪ねてくる実家のような役割を果たしていた。祖母が亡くなった時、私は父とともに九重に別れを告げに行った。その年、私はアメリカのイエール大学への留学が決まっていたので、その別れもあった。暑い日で、薄い布だけがかけられた祖母の小さい白い体が印象に残り、今でもその風景はいつでも蘇ってくる。
やがて母が迎えに来て私たちは元の勝山の家に戻った。学校も始まったが、以前とは随分と雰囲気が違っていて、先生方を始め誰もが気が抜けたように生徒に厳しく当たることなどはなかった。そのうちにいつ東京へ帰るのかと周りの人たちに聞かれるようになり、自分の身にも変化が起こるのだという意識を持つこともあった。戦争中はなんとなく私には存在感が薄かった父の印象も変わり、母もそうだが、共にどこか張り切っている雰囲気を漂わせていた。その頃すでに父は政界に出ることを決めていたようで、母にとっては突然のことで、随分と反対もし、言い争いもしたとのことである。
私は小学三年生になっていたので、少しは状況の劇的な変化を感じたり、わかったような気持ちになったこともあったが、危機感や緊張感はあまりなかった。ごく自然にその翌年には、東京ではなく、近くの館山市に引っ越しをしたのである。館山は近くなので、勝山を離れることが友達と別れることだという実感はなかった。勝山時代は実に生々しい生活感に満ちた、実感の濃い生活だったという思いが残っている。何事もありのままで、裸足で、毎日を暮らしたような、そして土地の子になりきっていた時代だった。空襲警報は怖かったが、東京で何が起きていたかや敗戦のことなどよりも、母が不在のときに、ふと自分は一人でいるという実感を持ったことを覚えている。疎開時代は、子供でもどこか捨て身の生活だったのだと思う。
疎開中は一緒に来たりっちゃんが手伝いをしていたが、ある時彼女は家の前の倉庫のような家に住んでいる男に夜這いに入られて、妊娠をした。夜中に目をさますと母に叱られて泣いている彼女の姿があったのを覚えている。この家に忍び入る強盗もドロボーもいないと母を安心させた三喜造さんも、さすがに夜這いの習慣について母に警告することはなかったのだろう。母はすっかり驚いて、慌ててしまっていた。いくら女傑の素質が現れ始めた母にしても、厳格な家庭で育った東京育ちで女学校出の母には、夜這いは想像外の出来事だったのだ。
確かに、塀で囲まれていないこの家はどこからでも入ることができたのだ。母はあのハーモニカ演奏は、りつちゃんへのセレナーデだったのだと、気がつかなかったことを悔しがった。彼はりっちゃんを早くから狙っていたのだ。りっちゃんにとっては案外素敵な経験だったのかもしれない。
その男性はあまり生活能力のない人だったらしく、彼女は結婚して以来、生活の苦労が絶えることなく、その小さな家で何人もの子供を生みながら、貧乏生活に耐えていかなければならなかった。彼女は相変わらず無口のまま、いつも子供をおぶって、母や近くの家で手伝いなどをしていた。
初めての子供は双子で、しかも一人が逆子の大変な難産だったらしいが、赤ん坊たちをとり上げたのは母だった。母が疲れ切って涙を流している姿が、心に強く残っている。赤ちゃんの一人にはしばらく足に軽い障害が残り、母はそれを大変気に病んでいた。生涯彼女の家族の世話をする決意をしたのも、彼女の運命を変えるきっかけが我が家に来たことであるという意識を持っていたのではないだろうか。疎開先の親も親戚もいない知らない土地へ連れてこられたからだ。りつちゃんは茨城の出身だったから、千葉県で生涯を送ることになったのも、私たちに疎開先へ連れてこられたからだ。その後りっちゃんはまた双子をうみ、そのほかに幾人もの子供を産んで、文字通り貧乏人の子沢山で、幸せななのか、大変なのか、そのどちらもまぜこぜの、休む暇のない人生だったと思う。夫の人は最後まで定職につけないままだったらしいが、優しい人だったし、子供達は皆親孝行なことで評判だっという。母親の世話も障害のある姉の世話も皆よくしたと聞いている。りっちゃんの恋物語は多くのストリーと入り込んだ筋構成を持つ豊かな物語だったのに違いない。
私は留学直前の夏、九重で亡くなった祖母に別れをしたのち、勝山で汽車を降りで、りっちゃんに会いにいった。彼女はあいかわらず無口で、子供を背負っていた。それが私の勝山と幼年期への別れでもあり、日本を離れて新たな人生への出発でもあった。幼児期から、りっちゃんは世話をしてもらう日常生活の時間の中心にいたのいだが、私にとっての代理母ではなかった。彼女にお話を読んでもらった記憶は残っていないし、叱られたり、物事を教えてもらったりした思い出もない。しかし彼女はいつも私たちと一緒にいて、私の幼児期の記憶の風景にはいつも彼女がいたのである。りっちゃんはいつまでも私の心の中では15歳のままだったし、茨城から田端の家に来た頃の姿のままだった。
一方姉の乳母だった和子さんーーかずちゃんは東京の家では行儀見習いのような感じで姉の世話係をしていたが、父の会社で働いていたサラリーマンと結婚した。すぐ夫が招聘されて戦死してしまい、幼い息子を抱えて、勝山の家ヘ来ていた。彼女もまた稀有な人生を歩むことになったのである。
家の近所に船大工をしている蛭田さんという家族がいて、そこの奥さんが母のところへよく来ていた。掠れた声の持ち主で、彼女の声が聞こえると空襲警報が鳴ったとよく皆にからかわれたものだった。おっとりした人で、子供が4人いたが、皆利発な子供たちで、私たちの遊び相手でもあり、母が大変かわいがっていた。買い出し隊の一番のお供は彼女だった。船大工の家は龍島海岸の浜辺に突き出した工場の裏がわで、戦争が激しくなるにつれて仕事は全くなくなっていたという。
その船大工の奥さんが戦後大流行した赤痢で一番下の幼い子供とともに突然亡くなってしまったのである。母はりっちゃんを使っては子供達の面倒を見ていたが、かずちゃんが舟大工の後妻になる話が持ち上がったらしい、というよりは母がそれを考えたのだろうと思う。かずちゃんは女学校を出た女性で、都会暮らしもしていた人で、船大工氏は子持ちで歳も離れていたから、必ずしも良縁とは言えない話だったはずである。しかしかずちゃんはお嫁に行く事を決めたのだった。それは父親の顔を知らない息子の裕一郎の行く末を考えてのことも大きな要因だったのかもしれない。とにかく彼女はその船大工の家に住んで、残された彼の子供たちの世話をする決意をしたのである。彼女がいい加減な気持ちでそれを決めたのではないことは、すぐに子供達が彼女になつき、信頼して、母親として尊敬もするようになったことでも明らかである。ただ一つ、彼女の連れ子は成長するにしたがって、勝山の船大工の家庭をどうしても自分の本来の生きる場ではないと感じ続けたようだった。彼は義兄姉たちに親しむこともなく、義理の父にも母親にも心を開くことがなかったという。小説家志望で、引きこもりがちな青年になって、かずちゃんの心配は止むことがなかった。
船大工の長男は画家志望で、やがて東京でそれなりに生計を立てるようになったし、長女の澄子さんは洋服の会社に勤めて確かな技術を身につけた職人となった。洋裁師は戦後の花形職業だった。私たちより年下の三番目の光子さんは、母親と妹と一緒に赤痢にかかったが、一人だけ治って、しばらくは後遺症に苦しんでいた。かずちゃんはそんな家族の面倒を親身になってみ続けたのである。子供達が彼女を慕うのは当然だったのだ。光子さんは千葉や東京で色々な仕事をしていたが、やがて勝山に帰り、母親の仕事を助けてその片腕になっていく。
かずちゃんは戦後の復興が始まると、船大工の工場を壊して、民宿を始めようと考えたのだった。母も心配しながらも賛成して、資金を出してあげたという。その方向転換は大成功で、浜辺の家は民宿には最適だったから、毎夏お客が絶えることはないようになった。
房総の海岸は湘南のように高級なリゾート感はないが、穏やかな海と、富士山が東京湾を超えて見える美しい景色、そして龍島海岸の沖には浮島という島があって、やがて子供のいる家族向けのリゾたトとしても人気が出るようになっていったのである。かずちゃんは数々の工夫をして、ビジネスウーマンとしての才能を発揮するようになった。船大工の夫は、民宿経営のマネジャーとなったが、本来優しい人柄で、かずちゃんは幸せそうであった。二人の間に子供もできたし、かずちゃんに育てられた船大工の末の娘はかずちゃんの民宿の手伝いを引き受けて大いに活躍するようになった。
何年も経って、かずちゃんが亡くなってから、私はその娘さんの切り盛りする民宿を訪れた。そこで見たのはカズちゃんと船大工の夫が、西欧旅行をした時の写真がずらっと展示されている光景だった。船大工氏は実におしゃれな格好をしていて私は内心びっくりした。歳が離れていることを可哀想だと母は心配していたのが嘘のように、実にかっこいいハンチング帽姿でかずちゃんとイタリアや南フランスやナイアガラの滝を楽しんでいるのだ。妻や子を亡くして、仕事もなく打ちひしがれていた姿とは全く違ったおしゃれな姿に、かずちゃんは本当に真摯に結婚生活を送り、皆に生きがいを与えて幸せにしたのだとつくづく感動したのだった。観光業も時代に適した職業で、船大工氏にとってもやり甲斐のある良い転職だったのだ。小説家志望の息子の心配が解消したかどうかは知らないが、芥川賞の候補になったことがあるというのだから、小説を書き続けたのだと思う。
戦争は多くの人の運命を狂わせた。私の幼年期の勝山時代という疎開時代は、非常時下の母娘の巣篭もりの時代であったが、それは戦後の文字通りの断絶と転換を用意した転換期の巣篭もり時代だったのである。
敗戦は日本の男たちにとっては屈辱であっただろう。戦争に反対した人にとっても、同じだったと思う。疎開時代は女たちの時代だった。銃後の母の役割を真剣に背負った女性たちももちろん多かったが、戦時中はとにかく生き延びる、生き残ることに女性たちは全ての力を発揮したのだ。男性不在の生活で女性たちは母親として自分の子供だけではない村や町の子供や家族のために、リーダーシップも発揮したのである。戦後の参政権を得た女性たちの活躍箱の時代に準備されたと言ってもいいのだろう。社会全般からの巣篭もりが、女性には長かったが、疎開という、男性、中でも家父長が不在の緊急時での巣篭もりは、家庭というアナグラ、家族という防空壕を出た後の外部の女性の活躍を可能にする転換期の準備期間ともなったのだ。
しかし、女性にとっての転換期も、決して順調ではなかった。敗戦後、街頭に立つ傷痍軍人の惨めな、哀れな姿に象徴される戦争の加担者であり犠牲者となった日本男性の姿は、やがて日本のめざましい復興とともに忘れられて行った。戦後の世界で、復員兵、植民地からの引き揚げ者などの帰還者、そして、巣篭もりしていた者たちも含めて、男性は短期間でめざましい社会復帰をしていった。それに比べて、女性の社会「復帰」は、社会参加、男女平等、性別役割分担を含むほとんどあらゆる仕事、教育、家庭の分野で、進展するどころか、むしろ核家族の中への封じ込めという新たな状況の生まれる中で、後退して行ったのである。せっかく男女同権、男女平等を明記した新しい憲法を持ちながら、20世紀の後半男女平等社会の遅れは世界的にも課題にされて、1999年の男女共同参画社会法の制定までの戦後55年間は女性にとっては性差格差の社会的受難の時代は続いたのであった。
2020/06/7
崖の上の家
第二章
田端の家:父の気配
渡辺町での幼年時代(日中戦争か平洋戦争開始まで)
私の幼年時代の最初の記憶は「田端の家」と私たちが呼んでいた、田端の駅から坂を上がった渡辺町にあった家での思い出である。私が生まれたのは1937年だから、幼年時代は日中戦争とともに始まったのであり、1942年の暮れに千葉県安房郡勝山町へ疎開して、そこで小学校に上がるまでの、幼年期を渡辺町の家で過ごしたのである。
その時期は父が東京市勤務をやめて、カーテンレールなどのビルや住宅家建設の部品を製造する工業会社を始めた時期であり、それが思いもかけず戦争のための軍需産業へと駆り出されることになったのである。父がそのような転換をしたのには、東北大学を卒業したばかりの母の弟が結婚した人の父親が、父を会社創業に熱心に誘ったからだと聞いている。叔父の妻の松子叔母の家族は王子に住んでいて、私は母とともにそこを訪れた時の写真を持っている。母は実に若くて、矢絣の着物を着て、日傘をさしている。私は3歳くらいだと思うが母の袂をしっかりと握っている。二人は王子、あるいは飛鳥山あたりの広い野原の中に立っていて、私たちの姿は二人だけポツンと遠景に写っている写真だった。その当時は王子付近はまだ新興住宅が立ち込む住宅街化していず、写真には、家は遠景にぼやけていて、草原がずっとっと奥の方まで広がっている。もちろん白黒で、写真自体も小さい。私の記憶は実際に見た風景なのか、あるいはこの写真の風景が脳裏に記憶されたものなのかはよくわからないが、それが母の記憶の最も古いものであることは確かなように思う。家は空襲で丸焼けになったのだから、私の生まれた時からの写真などはほとんど残っていなかった。
田端の家は私が生まれた家ではなかったが、この家が私が生まれた家と同じ心の内密な場所だった。過去を思う時、この家が心に浮かび、一人でいる休息の夢想の場だった。そこでは私は幼く、草原に囲まれた家にいるのだった。
もう一枚長く手元にあって、記憶に深く残っているのが、父の弟で早稲田大学の英文学部に通っていた結伯父と銀座通りを歩いている写真の中の風景である。伯父はコートに中折れ帽を被り、私は銀座の石畳の道を、飛び石をしながら伯父の脇を歩いている。結伯父は大学を卒業後NHKに勤めたので、服装から考えても、その写真の時はすでに学生ではなかったのかもしれない。伯父は軽い肺浸潤があって、兵役を乙種不合格になってしまったと、大変悔しがったそうである。だんだんと学徒出陣も迫ってくる時代だった。戦線に出て行く友人たちを伯父は駅へ見送りに行き、その時にはいつも私を連れて行った。私はその友人の一人が水兵さんの姿でいたことを、これは写真ではなく、はっきりと覚えている。その時の叔父はいつも学生服に角帽をかぶっていた。角帽をかぶった叔父の痩せた姿は私の中で止まったままでいる。
渡辺町での幼年時代は、この伯父と過ごした時間の記憶が最も鮮明なのである。私は「日暮らし幼稚園」という、家から坂を下った「日暮し町」にある幼稚園へ行っていたが、そこでの記憶はほとんどない。ただ、姉に手を取られて帰ってくる時に、男の子たちから「のりこの体操、めちゃくちゃ体操」と囃し立てられたことを覚えているので、一番幼いクラスの私は他の子達の体操についていけないほどコーディネーションが悪かったのだろう。結伯父は二階の欄干に座って私の帰りを必ず待っていてくれたのである。当時英文学を勉強していた伯父は私に英語の本を読んで聞かせてくれ、英語の単語やことわざを教えてくれた。何度も繰り返し言わされたので、as cool as cucumberという言い方を私はその頃からずっと覚えていたのである。「キュウリのように涼しい」とは確かに、キュウリは触るとヒヤッとするが、「涼しいのは触った手だけではない、心が涼しくなるのだ」、と必ず説明するのだった。伯父の読んでくれた物語はRobert Lewis Stevensonの『宝島』だった。英語はちんぷんかんぷんであっただろうが、物語はしっかり覚えていた。幼い子供の想像力を掻き立てる物語だったのである。
伯父は戦争が激しくなるばかりで、友人は皆兵隊に取られ、学徒動員も進んでいるのに、自分だけ身の危険のない毎日を送っていることに、後ろめたい気持ちを持っていたのだと思う。大学へ行くことも次第に少なくなり、家で過ごすことが多くなったという。国難迫る非常事態下の東京で、若い彼はおそらく鬱々としていたのではないだろうか。何もわからない幼い私の相手をして過ごすのが、気が楽だったのかもしれない。私にとっては若い伯父の話は、別世界の不思議と刺激に満ちていて、伯父が大好きでいつもついて回っていたという。その別世界が私の日常であった。それは父や母が留守がちだったこともあって、私は叔父の見えない心の世界の住人であることが、現実感覚の希薄な幼い私の日常を形取っていたのだ。
この結伯父は父の父母、水田新太郎ともとの七番目の子供、水田家の五男にあたり、父の長姉が館山市の九重水岡地域の地主の家に嫁いでいたのだが、子供がいないことから、戦後半沢家の養子となって行った。NHKをやめて千葉の実家に帰り、農地改革でほとんど田畑を失った元地主の夫婦養子になってしまってからは、敗戦後の大きく発展していく日本で、生涯二度と東京に出てくることはなく九重で英語教師をして暮らした。
父の次兄の二輔伯父は中国上海の同文書院に学び、天津で海運会社を運営していた。父よりもさらに背が高く、体のがっしりとしたこの伯父は、幼い時から大変に威張っていたそうで、父も一目置いていたらしい。植民地時代の天津で、世界へ向いて開かれた良好な港で、日本をはじめ世界の国々へ物資を運ぶ運輸会社を経営していたのだから、大変羽振りも良かったのである。天津では大きな家に多くの使用人を雇って贅沢な暮らしをしていたと聞いている。母は陰ではいつも「海賊おじさん」と呼んでいた。この伯父一家はのちに敗戦とともに風呂敷包みを背負って引き揚げてくることになり、しばらく館山の家で父母と一緒に住むことになった。
伯父一家が、四人の子供たちを連れての里帰りで日本に帰って来るときは、必ず田端の私たちの家に泊まったが、チョコレートをはじめお菓子を山ほどお土産に持ってきてくれたことが忘れられない思い出である。3歳年上の姉はおお菓子の味を知っていたが、日中戦争勃発の年生まれの私はほとんど甘いものを食べたことがなかったのである。そのお菓子を近所の子供達と分け合って食べるのは、どこか、宝島から宝を持ち帰って来て、皆に分け与えているような、贅沢で、得意げな気持ちがした。
渡辺町は狭いが閑静な高台の住宅地で、石井柏亭画伯がすぐ近所に「美しいお姉さん」の娘さんたちと住んでいられた。私たちの家の斜め前は高崎さんという陸軍か海軍大将の家で、立派な軍服を着て、黒塗りの車で出勤する「お父様」の姿を見たことを覚えている。私たちの父は家にいるときはいつも浴衣と丹前姿で、仕事の現場も、また改まった服を着て仕事に出かける姿も見たことがなかったように思う。
父もまた大変な弱視だったので兵役を免れていた。結伯父と同じ丙種不合格だったのである。敗戦時父は39歳であったが、同い年の男性たちも、戦場に駆り出されるほどに戦状は厳しくなっていたのである。父は京都大学時代に河上肇先生の下で、反戦運動をしていたので、この時期は公的にも、社会的にも発言や活動をすることは全くなかった。若い父もまた、色々と考えることの多かった時期だったのだと思う。
高崎家には姉と同い年と私と同い年の二人の小さな女の子がいて、私の一番の遊び相手だった。大変利発なお姉さんの恵子ちゃんとおっとりとした妹の邦子ちゃんで、毎日のようにお互いの家の前で「のりこちゃん遊びましょ」「邦子ちゃん遊びましょ」と呼び声をかけては遊んでいたものだった。あまりしつこく呼び合うので、お母様やお手伝いさんに、「あとで」と家の中からそっけなくあしらわれたことも、お互いにあったほどである。このふた組の姉妹同士はなぜか家の前の石畳で遊ぶことが多かったらしい。家を隔てる道路は、行き止まりのようなもので、その先は細い、急な石の階段が、田端駅の方へと降りていく。道と玄関先は、格好な遊び場だったのだろう。家の中絵おはじきをしたり、互いの部屋を散らかして遊んだ記憶もあるが、石畳で遊ぶ幼児たちの風景は、私の幼年時代の原風景となっている。
道路を隔てた家の前は土塀の続く大きな屋敷で、確か商人の家だったということだった。そこの庭に遊び友達の男の子と忍び込んだことがあった。どのように入ったのかはよく覚えていないのだが、お年寄りの女性が芝生の広い庭で、くつろいでいた。西欧風のテーブルにはレースがかけられていて、婦人というにふさわしいその人は茶を飲んでいた。私たちにビスケットをくれて、叱ることもなく優しかった。冒険に満ちた悪戯のつもりが、急に悪いことをしたような気になって、ビスケットを食べたことを覚えている。その道の角には岩崎家の親戚が住んでいるということで、門の前に広い車寄せがあった。そこではいつも石蹴りなどをして遊び、チョコレートを分けたのもそこだった。
家の裏の貸家には医者が住んでいた。病気がちの姉のために、その先生はちょくちょく家に来てくれて、私たちも仲良しになった。近所に住む中年の女性のことを、私がおめかけさんのおばさん、と言って先生をはじめ皆が笑ったのを覚えている。その人はめがねをかけていたのである。その女性は青年の息子さんが一人いたが、作家だということだった。ずっと後になって、石川柏亭さんの娘さんが編集した冊子で、確か作品を読んだと記憶しているが、どのような話だったかは覚えていない。
しかしなんといっても私にとってのこの渡辺町時代の一大事件は、母の留守に私が針を踏んで手術を受けなければならなかったことであった。姉とともに留守番をしていた私は、お手伝いさんがお裁縫をしている部屋に入り、その膝に乗ろうとして、膝の周りに広げられていた着物の仕付け針を踏んでしまったのだった。長い太い針が足の裏に入っていくつかに折れてしまい、取り出すことができなかったという。母が帰ってきた時には、私は巣鴨のとげぬき地蔵のお札を口いっぱいに詰め込まれて泣いていたそうである。それからが大騒ぎとなり、東大病院での長い手術でも針の先の部分が見つからないというので、母が院長に掛け合って執刀を依頼したという話を聞いたものだった。針は体の中で動くので、放っておくのは危険なのだそうである。全身麻酔から起きて母と伯父の顔を見た時のことも記憶にある。目覚めて、随分吐いてしまったそうである。
私は手術に関しては何も覚えていないが、退院後にガーゼの取り替えに医者に連れて行かれるのが大変嫌だった。毎回伯父が母に付き添って私を抱いて病院へいってくれたが、待合室に入ると必ず私が泣き出すので、困ったそうである。注意をそらそうとあれこれ話をしてくれていても、その場になると泣き出してダメだったと伯父は言っていた。おそらく痛い経験だったのだろう。赤いトサカの鶏を見たので気を引こうとしたところ、「赤チンは嫌い」と言ったとかで、伯父はその話を私が大きくなってもよくしていた。この子は画家になる、色彩感覚が鋭いから、と伯父はいつも私の味方だった。
この事件は家族にとってはかなりのショックだったらしく、裁縫のねえやさんは、彼女のせいではないのに泣きじゃくってばかりいたそうで、その後やめて田舎へ帰ってしまったという。静やという母がいつも褒めていた人だった。その頃田舎へ帰った女性たちの働き場所はおいそれとなかったに違いない。母も姉もどこか責任を感じていたらしく、父と伯父はとげぬき地蔵のお札を飲まされた私の姿を想像しては苦笑していたという。私は二番目の子で、病弱な姉と違い病気をしない子供だったこともあり、また男の子を期待されていたのに残念がられていたこともあって、私はあまり特別な注意を受けない、手のかからない、男の子のように放っておいてもいい子だったのが、それ以来は、皆に大切にされて、中でも母は術後の湯治に湯河原温泉の旅館に私を連れていき、長い間滞在した。戦争中としては贅沢な、非国民的な行為だったのではないだろうか。
渡辺町時代には住み込みのお手伝いさんが常時3人いた。一人は母の手伝いが主で、食事も作っていた。あとの二人は姉と私の世話をする乳母の役割で、幼稚園の送り迎えやお風呂の世話などをしてくれていた。私のために田舎から出てきたのは当時15歳のきやという女の子だったが、きやでは呼ぶ時にきゃ!と聞こえるからと、りつと呼ばれることになったという。家に来た時にトラホームという目の病気を患っていることがわかって、すぐに目医者通いとなった。幼い私の腕を引っ張って、肩が抜けてしまって騒ぎになったという事件もあり、母や年長のお手伝いさんたちからかなり厳しく叱られながら、だんだんとものがわかってきたという。東京の生活になかなか慣れなくて、買い物などで街に出るのが苦手だったという。飛鳥山公園はその当時も桜で有名だったが、家族でお花見に出かけた時、私をおぶったまま迷子になった。家の住所もわからなくて泣いているりっちゃんの背中で、幼い私が家の住所を警官に教えた、という話が家族のエピソードとして残っている。
無口で、才走ったところの全くない、体の動きも鈍い「田舎の娘」そのもののりつに、母は二言目には「本当に手を焼かせる」と愚痴りながら、結局母が疎開先に連れて行ったのは彼女だつたし、戦後の困窮時代も、高度成長期も、そして生涯、母は彼女と家族の世話をし続けたのである。りっちゃんは15歳の時から私たちの家族の一員として大人になっていったのである。
姉の世話をする乳母は、和ちゃんといって、千葉県館山市の旅館の娘で、女学校出の利発な女性だった。彼女はやがて父の会社に勤めていた人と結婚をして、憧れだったという都市サラリーマンの家庭生活を送るようになったのだが、すぐに夫が戦争にとられて、一歳の子供を残して戦死をした。彼女もまた、その後生涯水田家と切り離せない人生を送ることになった。
3歳年上の姉は渡辺町の家から千駄木小学校に入学した。しかしその後疎開することになり、勝山小学校に編入学した。私は姉の千駄木小学校時代の話をあまり聞いたことがないのか、覚えていないのか、記憶にないのだが、それは勝山での姉の学校生活についても同じだった。ただ、千駄木小学校の一年生受け持ちの先生が、家族の親しい友人となったこと、そしてその家族との交流は生涯続いたのである。その先生は中田先生と言って、ご夫婦共先生だった。疎開先の勝山に一家の4人のお子さんのうち3人が一緒にしばらく住むことになった時期もあり、戦後も親しい付き合いが続いた。その私たちも含めた付き合いは、お子さんたちやお孫さんにまで続いたのである。
戦争で渡辺町一帯は焼き尽くされ、そこに住んでいた家族は皆バラバラになって、戦後に皆が元に帰ってくることはほとんどなかった。私たちの家も家族も同じであった。しかも敗戦後の貧窮時代に、疎開先から帰れるにしても何年もたってからという人も多く、元のコミュニティが再現されることはほとんどなかったと思う。戦後の復興では、一戸建ての跡地にはマンションが建つようになり、住宅地そのものを大きく変貌させたのである。
1967年留学先のイエール大学を出て一時帰国した時に、私は田端の家の跡を訪ねたが、一目ではどこがそうだったかわからなかった。あとで開成中学のテニスコートがそうだと聞かされたが、それはあまりにも跡も名残も残さない、変貌というか消滅の風景だった。しかし間も無くそれもなくなって、1972年にもう一度行った時には辺りはすっかり新しい住宅地に変わっていた。石川柏亭さんの娘さんたちが、色々とその当時の写真や記録を集めていて、それが活字になっているのを読んだことがある。柏亭さんのお家へは、その頃母、姉と伺った記憶があり、洋風でおしゃれな感じの、ステンドグラスのあるお家だった。
1970年代に私はロスアンジェルスの大学で教えていたが、ある時突然、高崎さんの恵子さんが研究室へ訪ねて来てくださったのである。生涯教育プログラムの盛んだったロスで、何かで私の名前を見つけたのだろうと思う。その時の感激は忘れることができないし、思い出すと今も胸がいっぱいになる。恵子さんは昔の面影を残した聡明な女性で、ロスで仕事をしていられた。妹の邦子さんのことも色々お聞きして、再会を約したのである。とにかく私たちは、3歳から7歳くらいの小さな子供たちだったのである。それから30年は経っていた。田端ではなくロスでの再会が、二人とも遠くまで来たという感慨をひときわ胸に響いいた。
3月10日の大空襲で跡形もなく焼き尽くされ、財産を一夜にして失うという悲劇によって、敗戦以前の3月には、すでに近隣の家族は皆どこかへ移っていったのだった。その上敗戦という大きな断絶にもかかわらず、渡辺町での知人や友人との交流が長く続いていったのは、昔は知人や友人、そして人との絆の作り方がごく限られた範囲と仕方で、今のように一度に多くの人たちと交流ができるような「ソーシャルネットワーク」の作り方はなかったので、人との繋がりが、限られた血縁と地縁に依拠していたからではないだろうか。それだけにその関係や絆は利害を超えたものであることが多かったのだと思う。
同窓会や同期会、県人会、会社の同僚など、学校、大学、会社などによる繋がりは大きくなっていっても、血縁関係は少なくなり、また隣組のような住む地域の地縁も希薄になってきている。テレビに出ればいっぺんに多くの人に知られるようになるが、いずれにしても戦前の短い幼稚園時代の知り合いにアメリカで再開するなどは運命的なことのように思えた。地縁は記憶の中の最も深い場所との縁であるのだ。
渡辺町の家に多くの客や父の知り合いが訪ねてきたという記憶はほとんどない。私が幼かったのだから記憶にないのは当然であったかもしれない。しかし、父は政治家として名を知られるようになり、大蔵大臣を歴任して、財界、産業界、教育界などに多くの知人を持つようになっても、親しく付き合う人たちは昔の友人や郷里の人たち、そして若い頃の知り合いの人たちだった。戦時中の渡辺町時代には特攻に見張られていたということだし、大きな企業に就職していたわけでもないし、軍隊にも人脈があるわけでもなく、親族といっても、田舎のせいぜい小規模な地主の家の出であれば、多くの客や知り合いが家を訪ねてくることが少なかったのは当然であるだろう。
水田家の縁者で東京に住んでいた人はすくなかったが、父の従姉が寄席などの貸し席劇場を経営する人と結婚して深川に住んでいた。父の母の実家の田村家の人で、評判の美人だった。粋な着物姿の夫婦で、深川という下町の賑わいの中での商売で、生活も華やかだったという。はとこに当たる人たちは私たちよりも年上だが、それでもずっと戦後も付き合いが続いて、その一人から私は相撲部屋に連れていってもらったことがあった。父の故郷の曽呂村から上京する親戚は、必ずそこで美味しいものをご馳走になって帰ったらしく、結伯父もたまにご馳走になりにいっていたということだった。それも戦時中という非常時体制の下のことで、交友関係も自粛ムードだったのかもしれない。渡辺町時代の父は30歳になったばかりでの頃で、知り合いが出入りしない渡辺町時代は当たり前だったのかもしれない。
その寄席席も3月10日の大空襲ですっかり焼けてしまった。戦後スマックとかいうアイスクリーム会社に勤めた伯父に会ったことがあった。小唄や芸者遊びなど、寄席席のオーナーとして、ほとんど遊んで暮らしていた人が、戦後の有楽町でアイスウリームを売っていた姿は頭に焼き付いている。食料が極度に欠乏していた時代に、アイスクリームは飛ぶように売れたそうだった。
渡辺町時代の父は、結伯父と同じように、戦争に行かない男性として厳しい戦時中の緊張した統制時を過ごすことについて思うことが多かったのだと想像する。その意味では、親や息子、兄弟を戦線に送っている家族に比べて、軍事政権下の緊張は、田端時代の我が家では緊迫した空気をもたらしていなかった。誰も戦争のことを話さなかったし、愛国主義者として振舞うこともなかった。父はいつも仕事で外に出ていたが、家族はそれまでと変わらない雰囲気で、子供たちのしつけに関しても、今は大変な時なのだから、というようなことは全く言われなかった。その沈黙は結伯父の存在が影響していたと思うが、それ以上に父の原則的な沈黙にあったのだと思う。父は決して偉そうなことを言わない人で、誰に対してもお説教することは一切なかったが、戦争批判も、加担の言辞も一切言わなかった。田端時代の父は幼い私たちにとってはむしろ不在で、何も影響を与えない、沈黙した、見えない存在だった。
ただ私たちが普通の人より早く疎開をしたのは、父が激しい東京空襲を早くから予見していたからだと母はよく言っていた。母は父がこの戦争は勝ち目がないと早くから言っていたという。父の鋼板製造会社は次第に軍需製品の生産を強いられていくようになり、父は忸怩たる思いがあったと思う。その辺りは父の自伝でもあまり詳しくは触れられていないが、渡辺町での、有事とは思えない、何事もないような平凡な日常生活が、むしろ普通ではなかったような気がするのである。そしてそれが、私が経験した戦前の世界、都市中産階級の家庭の経験だった。
それもあってか、私の幼年期はあまりにも緊張感にかけた夢の中の時間のように思える。父や母の姿は私の記憶の中ではぼやけていて、今でも鮮明に思い出される数々の場面は、まるで映画の中の一コマのように、現実感や激しい感情の喚起、呼び起こされる歓喜や苦しみのない、いわば物語の中の場面のようである。それは私がこの時代の経験を内面化することが少なかったからではなく、この家での幼い頃の時間が、気配として流れる時間だったからであるだろう。いじめられた思い出や、姉妹間の喧嘩や軋轢などは、心に何の痕跡も残していないし、父や母に対する感情も同じである。留守で寂しかった思いの痕跡もない。私はそこで住んだのでもなく、暮らしたのでもなかったのだ。「生まれた家」の洞窟のような守られた空間で、そこに漂う気配の中にいたのだ。まるで神話的なたゆたうような時間は、確かに流れていたのではあっても、どこかスピード感や強度に欠けている。その中でうごめく者の一人だったのである。田端の家は父母が不在の記憶として残っていても、そこは確かな父の気配が漂う場であった。
個人的には針を踏んでの手術、2.26事件後の軍事政権、日中戦争がアジア、そして太平洋戦争へと進展していく国家非常事態下の世間の緊張、家族や知り合いが次々と戦場へ出ていく不安、私の幼年時代はまさに、非常事態下の時間だったのだ。それにもかかわらず、記憶の世界を流れる、ゆったりとした、非現実的な、神話的な時間の流れは、家の中を流れる時間のたゆたいでもあったのだろう。それは父の内面の時間でもあったのだと思う。父にとっての敗戦後の大きな人生の転換はこの時代には予測できなかっただろうが、それでも戦後の世界と身の立て方などを考える準備期間のような沈黙の時間だったような気がする。父がただ口を噤んで非常時をやり過ごそうとしていたのではないことは、国会議員とになるための総選挙に出る決断が降伏後間も無くできていたことでも明らかである。
それに比べて、このすぐ後に続く勝山での疎開生活は、幼い私にとってもどこか現実の厳しさに立ち向かう実感に満ちたものとして記憶に深く残るものとなった。
生活の場が急激に、しかも全く違うのもとなり、母の存在が、日常のすべての時間を強烈な密度で占めるようになった。父は相変わらず不在だったが、母と娘たちの密接な生活が、狭い家と異国のような場所で始まったのである。
2020/05/8
本全集は全12巻にわたる近代の出発期から現代までの女性文学を集成した日本ではじめての〈女性文学全集〉である。
第10巻は水田宗子の編集と解説によって、フェミニズム批評から見えてくるものは何かをもっとも明らかにしてくれる出色の1巻だ。
戦中から敗戦後にかけて自己形成し、1960年代以降に活躍した倉橋由美子・河野多恵子・大庭みな子・富岡多恵子・高橋たか子・三枝和子・岩橋邦枝・田辺聖子の作品を収録。
これらの作家は新憲法の男女平等思想や世界の新しい思潮を享受しつつ、家父長制の社会・家族・結婚制度における性差の現実との苦闘を余儀なくされた世代である。第二波フェミニズム批評の旗手水田氏は、彼女らの文学表現の深層には性差文化のディストピアが埋め込まれ、ジェンダー構造の破壊と鋭い批判を目指す、近代小説のアヴァンギャルドだと指摘。
男性主体の批評では見えなかった女性表現の深い闇を解き明かし秀逸である。
六花出版、2019年9月
定価・本体5,000円+税
2020/05/8
Mizuta Table of Contents Mizuta Chapter 1 Mizuta Chapter 2 Mizuta Chapter 3 Mizuta Chapter 4 Mizuta Postscript
2020/03/16
フェイクニュースとフィクション 中沢けい×水田宗子
pp1-29
2020/03/9
現代女性詩論序説 戦後女性詩のカノンの形成と消滅(第2回)
pp.88-101
2020/03/5
論文
現代女性持論序説Ⅰ 水田宗子
pp2-31
2020/03/5
小屋といえば、サダキチハートマンの晩年の家はまさに小屋というにふさわしい砂漠の中の家だった。カリフォルニア州のリヴァーサイドに住むようになったのは1971年だが、そこはロスから90マイルばかり東へ、内陸に入り、そこからずっと続く砂漠の入口のような場所にある街で、昔はハリウッド関係の人たちのリゾートだったという。ニクソン大統領が結婚式をあげたというミッションが街の真ん中にあり、ハリウッドの映画をまず最初に上演したという大きな映画館も残っている。戦後はリヴァーサイドからさらに砂漠の奥深く入っていったパーム スプリングが、フランク シナトラや副大統領のフォードが別荘を構えた本格的リゾートとして繁栄し、リヴァーサイドは昔の面影を残しながらも、ロスの郊外でもなく、リゾート地でもない、カリフォルニア大学のリヴァーサイド校のある大学街として、人口15万人の独立した地方都市となっている。
リヴァーサイド校にはジョージ ノックスという英文学者がいて、サダキチハートマンのアーカイブを図書館に作ろうとしている時期に、私はリヴァーサイドにニューヨークから移り住むことになった。なぜ彼がハートマンに興味を持ったのかは、リヴァーサイド近辺に住む少年小説を書いていた作家ハリー ロートンがいて、彼から、ハートマンがメランゴ インデイアン居住区に晩年なくなるまで住んでいたこと、そしてそこに彼の原稿や生涯の仕事の記録や資料をなどが入ったつづらが残っている、その整理と調査をしてくれないかと頼まれたからだという。
サダキチ ハートマンと聞いて、私は大変驚いて、それまで心のなかに燻っていたリヴァーサイドへ移住することへの逡巡がすっかりなくなり、この地の果てのような、砂漠へ隣接する街へ来たのは何か運命的なことだったような気がしたのを覚えている。私は東京女子大で、太田三郎先生から比較文学を学び、サダキチハートマンについて書かれた著書を読んでいたのである。比較文学は当時は国別に分類されていた文学研究分野の亜流と見られていて、文学漫遊だと相手にされないことも多かったと、後に島田謹也先生からよく伺っていた。大学院に都立大学を選んだ理由の一つには島田先生が比較文学を講義していられたからであった。大学では英文学専攻だった私にとって、アメリカ文学も、日本文学も一緒に扱うことができる比較文学は新しい批評の可能性を秘めていると感じたのである。
私は早速ノックス先生にお会いし、サダキチ ハートマンの住んでいたと言う家を見に連れていっていただいた。メランゴリザベーションはその頃はアメリカ中で一番の荒地という評判の居住区だった。同じインデイアンのために与えられた土地でも温泉が出たパームスプリングスなどは経済的にも潤っている場所であり、その他にも石油が出たりして、豊かになったところもある。しかしこのリザーベンションはその頃は文字通りのバッドランドであり、オアシスもなく、とにかく水が出なかったというのだから、経済的にも、また生活の上でも、大変な貧困地帯であった。実際、そこには小さな、コレクションも少ないミュージアムがあるだけで、観光客も来なかったに違いない。私がリヴァーサイドを離れた1980年代の半ばまでは、アルコール中毒や病気がはびこる問題地域であった。ちなみに現在はカジノが出来て、大変繁栄しているということで、それもまた驚きでもあった。
そのリザーベーションの中の小さな小屋がサダキチの終生の住処だった。彼が小屋の前に立っている写真が残っているが、彼は晩年そこでインデイアンの女性と暮らして、子供ももうけていたのである。ハートマンは明治の始まる前年に長崎で、ドイツの商人のハートマンとお貞(定?)という女性の間に次男として生まれた。二歳にもならない頃にお貞がなくなり、父親のハートマンは子供達を連れてドイツのハンバーグに帰国し、そこでドイツ女性と結婚した。ハートマン兄弟は厳格なドイツの家庭で育てられたのである。サダキチが十七歳ぐらいの頃、彼はアメリカに渡り、以来アメリカで暮らし続けた。ハートマンが知られるようになるのは、能のような寸劇(キリスト、仏陀、孔子についての劇で、不謹慎だというかどで上演禁止となり、警察で調べらたことで名が知られた)を書いて演出したり、香を嗅ぐ会として香水の嗅ぎ比べの会を催すいわばエンターテインメント芸能人としてである。日本のことを知らず、また幼い頃日本を出てから生涯日本の地を踏むことはなかったが、日本人としてのアイデンティティを強く前面に出して、日本を「武器」にオリエンタリズム時代のアメリカで芸術家のエンターテインメント人として人に認められるようになった。彼はまた芭蕉の俳句の翻訳をして、俳句を流行させたことでも知られている。短歌も書いていて、その原稿は出版され、残っている。メランゴの家のつづらには芭蕉やほかの俳人の作品の{英訳」が残っていたが、翻訳とはいえない、内容も異なる彼自身の創作短詩という方が適切である。
そのようなどこかまがい物扱いをされがちな芸能人がニューヨークの芸能界を生き抜いて行くことはできないのは当然で、ハートマンはアメリカ各地を放浪して、やがて砂漠を超え、ハリウッドまで流れ着いたのだという。ハリウッドではしかし映画俳優としても、特異なタレントとしても評判がよく、ダグラス フェアーバンクスの「バグダッドの盗賊」では盗賊の頭の役で、今でも人々の印象に強く残っていると思う。チャップリンに、フィンガーダンスを教えたのも彼だということである。彼は背が高く日本人らしい端正さとドイツ的な彫りの深さを併せ持つ風貌で、映画人だけでではなく、一般の人にも人気者であったということである。
つづらには定吉が描いた多くのパステル画が残っていたということである。ノックス教授はそれらを購入したということなので、リヴァーサイド校にはそのコレクションがあるに違いない。サダキチの娘さんのウイステリア ハートマン リントンさんは当時カリフォルニア大学リヴァーサイド校の写真家として勤めていて、ちょうど退職してアリゾナに移ると言っていた時だった。私も彼女にお会いしてハートマンのパステル画を3枚譲ってもらった。いいのは皆ノックス先生が持って行ったと言っていたが、私はそれら三枚の絵が気に入っている。綱渡りをするピエロや砂漠の山の絵で、パステルの青が実に美しい。世紀末のヨーロッパのサーカスやミュージックホールで演じるピエロの華奢な姿がいわれのない深い郷愁をそそる。
ポオも同じだが、亡くなった後の原稿や遺品の整理は、親身な家族がいたとしても、一筋縄ではいかないことなのである。ウイステリアは自分の身辺整理の中での父親の遺品の整理もかさなっていたので、私は幸にも絵を手にいれることができたのだ。それらの絵は砂漠のインディアン部落の小屋では飾られることはなかったであろうし、その頃は大学でも公開できるような場もなくて、まだ資料の段階で埋まっていたのだ。
ノックス教授はハートマンが写真批評を書いていたことを発見して、ハートマンが写真が表現メディアとして使われるようになり始めた当初から、写真表現を取り上げ続けた優れた写真批評家であることを高く評価している。事実ハートマンは写真批評の事実上の草分けとして、今日知られている。その業績は現在では本にもなっているが、当時は写真はダエレオグラフの域を出たばかりであり、ハートマンの感性や前衛芸術か、批評家としての目の確かさの証である。ウイステリアが写真家であったことは偶然ではないのだろう。ハートマンは芸術批評という分野で、文化的交流、影響、伝搬という根源的な的な課題を、身をもって実証した人物でもあったが、オリエンタリスム流行に乗ったエンターテイナーとしての評価が先に立ち、中々大手の、エスタブリッシュの出版界で著書を出すことができなかったのは、ポオの場合と同じだったのだと思う。サダキチも、ポオと同様に、批評の現在性を重要視し、雑誌というメディアに力を入れ、彼自身写真批評の雑誌を創設、刊行している。
定吉がもっと長生きをしていたら、というよりは第二次世界大戦が勃発しなければ、おそらく彼は晩年日本へ来たに違いない。ノグチ イサムもまた放浪のアーティストだったが、その芸術家としての生涯は自らの内なる日本を見つけ出して行く過程であったと言えるだろう。それを思うと砂漠の中の晩年、ハートマンが何を考えていたか知りたいと思う。ハートマンはフロリダに娘を訪ねている時に亡くなったが、ボヘミアンとしての生き方を生涯貫いて芸術家だった。
その晩年に関しては、興味深い話が残っている。彼は近くの郵便局へ毎日のように手紙を受け取りに行っていたらしいが、マラルメやヴァレリー、パウンドなどから手紙が届いて、郵便局の人たちを驚かせていたという。しかしその謎めいた生活が、世界大戦が始まってからは彼がスパイであるという嫌疑をかけられることにつながり、CIAや警察に見張られていたという。サダキチはよく砂漠の裏山に登って考え事をしていたというが、それが、どこかと交信しているのだと疑われたということである。ハートマンは若い時から、ヨーロッパの象徴主義芸術に深い関心を持ち、その影響も受けている。マラルメとも交流があり、それが晩年まで続いていたことがこのエピソードでわかるのである。前衛雨滴モダニストとしてのハートマンと、日系人人としてのハートマン、象徴主義芸術と日本文化の関係、そして写真批評の先駆者として、ハートマン再評価は、ジョージノックス先生がアーカイブを作り資料を出版し始めた1970年代から始まり、今日ではますます関心が高まっている。私のハートマンとの再会は、私自身が異国の未知の砂漠の入り口の街街リバーサイドに住むための旅と重なっていることに改めて感慨が深い。
明治開国となっての外国人と日本の女性の恋愛物語は「蝶々夫人」でも有名だが、サダキチは母がお貞(定)という名前だったこと以外に、何も知られていないし、サダキチ自身も知らなかったと思う。定が幼い頃に亡くなったことやその後家族がドイツに帰り新しい母親に育てられたことなどから、お貞に関する資料を探し残そうという動きがなかったこともあって、サダキチは大きくなってもほとんど母親のことを知ることもなく、その機会にも恵まれなかったのだと思う。サダキチという存在が唯一の歴史的時代の東西二人の男女の出会いの記録なのだ。
サダキチの存在を長い年月の間日本も日本人も知らなかったのだから、彼を探し出したのが、ハリウッド映画界という不安定で一攫千金と名声を狙う場、スターも生む代わりに落ちぶれも作り出す、いわば天国と地獄が一夜にして入れ替わる、詐欺師と本物の区別がつかない、野望と自堕落が渦巻く人間劇の場であったのは異邦人芸術家の行き着いたところとしては当然であったと言えるのだろう。
リヴァーサイドからRoute 60に乗ってロスへ向かうとやがてハリウッドの丘が見えてくる。メランゴインディアン居留地とハリウッドを結ぶのは、私が毎日南カリフォルニア大学へ通っていた同じハイウエイだったことに何か運命的なものを感じた。1959年東京女子大学で太田三郎先生からサダキチハートマンについて教えていただいてからの長い年月が、このハイウエイの続く道の果てに蘇っているような時空を超えた錯覚に襲われた。
コンコードの家とポオの小屋、その違歴然としていながら、今では観光スポットになっていることにはない。ソローのウオールデンの小屋とインディアン居留地の小屋は同じ小屋でも知識人が意図的に隠遁するために建てたい場所と食い潰れて流れてきた居場所と、その違いはこれまた歴然としているのだが、これらの居場所には、作家の家という共通項があるのだ。そうならば資産価値や作家の生前の社会的位置や経済状況には関わらない居場所としての共通項があるのではないだろうか。ユルスナールの家はそのことを強く感じさせた。家族の中で書いた作家と、一人居の孤独やプライバシーを守る中で書いた作家、社会や世間から受け入れられる存在を目指した作家と異邦人としての意識をを持ち続けて書いた作家。家や居場所は作家の自己意識と創作の原点となる自己存在意識を表彰していると思った。作家自身がそれを意識していたか、意識してそれを選んだかどうかは問題ではなく、結果的には彼らが残した作品と住んだ場所は分かち難く結びついているように感じたのである。
(了)
2020/03/5
アメリカに留学して一年目の1962年の夏にワシントンからミシシッピー経由でニューオーリンズへ旅する途中に、ボルテイモアのポオの住んだ家を訪ねた。その時はフォークナーの家のあるミシシッピー州のオックスフォードへいくことの方に、胸を膨らませていた。実際のところ、オックスフォードの家に閉じこもって仮想の南部世界を文学に再現したフォークナーと、生まれた時から自分の家がなく、住む場所を転々としたポオとでは、家や居場所の意味が全く違う。仮住い のポオ の家にはあまり期待などいだいてはいなかったのである。ボストンのミュージックホールで舞台に立っていたポオの若い母親は、ポオの父親が何処かに行ってしまったために、一人で赤ん坊のポオを抱えて舞台で歌っていたという。舞台裏の楽屋がいわばポオの託児所で大人しくさせるために、ウイスキーやジンをしみこませたパンを与えられていたなどと書かれている。その母親も亡くなってボオはリッチモンドの商人の家に引き取られて育てられる。しかし正式な養子にはしてもらえず、ヴァージニア大学に進学中に問題を起こしたかどで退学になると父親から勘当されてしまう。養父の家をポオが自分の家とも居場所とも感じたことがなかったであろうことは察しがつく。
ポオの人生は謎に包まれていて、ポオ自身の話にも嘘が多かったともいわれているし、その上ポオが信頼して自分の原稿を託した編集者が、ポオについて、アルコール中毒で、性的不能者であったという伝記を書き、ピューリタンの伝統が強いアメリカでポオは死後高く評価されるどころか忘れられ、ポオの全集は死後50年以上出版されることがなかった。
ポオの決定的な評価はボードレールによってなされることになったが、そのために日本での評価もボードレール経由であったのはポオにとっても日本の読者にとっても素晴らしいことだったと思う。しかしアメリカで無視された年月が長かったためにポオの伝記的な資料や住んだ家やアパートの保存などは大変少なく、同じ時代のホーソンやメルヴィルとは比べ物にならない。
ボルティモアのポオの住んだアパートは街外れの寂れた場所にあり、危険な場所だと行く前に注意されたくらいのスラム街で、アパートの建物の隣の建物はもう取り壊されていた。中に入ることはできなくて、外から眺めただけであったが、よくそれまで残っていたと感心したほどひどい状態の建物だった。ポオは晩年をニューヨークのフォーダムで過ごしたが、亡くなったのはボルティモアの路上で、叔母で義母のマライア クレムの住んでいたボルティモアに来ていたようである。その町の路上で倒れているところを見つけられたという。マライア クレムはポオのたったひとりの親戚でその娘のヴァージニアと彼女が13歳のときに結婚している。ヴァージニアが貧困のうちに肺結核で1848年に亡くなってからポオは悲しみと苦しみで自己破壊の淵に立っている状況を叔母に手紙で訴えている。ポオ自身はその一年後の1849年に40歳で亡くなっている。
そのヴァージニアと暮らした家、「ポオの小屋」と呼ばれる家が ニューヨークのフォーダムに残されていた。フォーダムはニューヨーク市ブロンクスのフォーダム大学のあるところだが、ポオの当時は本当に畑の広がる田舎の一地域だった。キリスト教の僧院があるような場所だから、周りには何もない、むしろ人里離れた場所だったはずである。それはホーソンやメルヴィルの住んだボストンの郊外と同じである。ポオの「コッテジ」と呼ばれるにふさわしい小さな小屋のような家で、中には家具らしいものはあまりなかった。大きな黒猫が病気のヴァージニアを温めるために布団の上に座っていた、と言われている。そのベッドも小さなものだった。私がそこを訪ねたのは1960年代半ばの冬で、ポオで論文を書き終えたころで、夫がフォーダム大学に勤めようかと考えている時だった。
ポオについて書いている間、私は彼の生活の実態や貧困の程度などについてあまり具体的に考えたことがなかった。文学雑誌の編集者として作品創作も旺盛に行っていたポオは、彼を尊敬して慕い、新しい雑誌のスポンサーになろうという年上の女性が一人ならずいたことも知られていたので、貧乏ではあっても、食べることに事欠く生活だったとは思っていなかったし、貧困と創作の関係は、ポオの作品の中にはほとんど手がかりになるようなものがなかったからでもあった。しかしポオのコテッジに私は強い感銘を受けた。そこには貧しさだけが、質素さではなく、むき出しに「表彰」されていたのである。
ポオが親も後ろ盾も、資産も、住む家も持てない人生を送り、いつも貧しかったことが、社会への定着の不可能さや、社会的な評価の低さに深く関係していたことは明らかで、ポオの特異な主人公たちの形成に大きな影響を与えていることも確かに思える。日本作家では林芙美子は貧困を売り物にしたとかえって意地悪く批判されたこともあったが、同じ貧しくても尾崎翠の作品には、貧困との関係よりも主人公たちの俗社会に根を下ろさない生き方が強い印象を与えている。意図的に隠遁生活を選んだ作家たちの、質素でも決して貧しいとは感じさせないソローの小屋や、鴨長明の方丈の家とは異なった作家の家がボルテイモアのスラムにあったのである。
かなり最近、そのフォーダムの小屋が、フォーダム大学のキャンパス拡張のために取り壊されたと新聞で読んでショックを受けた。しかし、現在は小屋は他の場所に移されて、美術館として公開もされている。写真を見ると家の中には色々な家具が置かれていて、ポオの生活が決して貧しくはなかったようにしつらえてある。貧困は確かに人間の尊厳を損なう屈辱でもあるが、芸術家や作家、詩人は決して金銭的に豊かで、社会的名誉を国家から認められているような生涯を送らない中で、後世に残り、時代も場所も超えて人の心に響く作品を残してきたのである。チャップリンの浮浪者はポオが原型だというが、hoboの代表格ポオの小屋が残っているのは、稀有のことなのであるだろう。家に象徴される家族を通しての社会的定着を持たなかった作家や詩人のアパートなどは保存されることはほとんどなかったのは当然なのである。しかし今は大勢の人たちが海外からも訪れる観光人気スポットである。
ホーソンとメルヴィルはポオと並んで文学想像力の持つ「黒い力」を作品に表彰した作家として、アメリカ文学批評家のハリー レヴィンに高く評価された作家である。ホーソンは生前は社会的評価が高かったとは言えないし、メルヴィルは長い間船員として海洋放浪をしていたなかから多くの作品を書いた作家でもある。しかし彼らの家が残されているのはエマーソンやソローという友人たちの社会的、文学的評価が生前から定着していたからであろう。その点、南部出身で、トランセンタリズムや東部の知識人への反感と批判を持っていたポオには、彼の作品をを評価する作家や批評家の友人にも、そして彼の生活を助ける編集者や友人にも恵まれていなかったのだ。ホーソンやメルヴィルが住んだボストンの郊外が、現在観光地としても高級住宅地としても高い資産価値を持つようになっていることに比べて見ても、アメリカにおけるポオの再評価がもう少し早く行われていたらよかったのにという思いを禁じられなかった。
ポオ評価は、しかし、20世紀後半に入ってからは高まるばかりである。アメリカよりもフランスや日本で最も早く高い評価を受け、その影響が大きく続いていることが、やっとアメリカの一般社会にもわかってきて、ボストンにもポオの銅像が立ったし、フォーダムの小屋は修復されてそこを訪れる観光客は年々増え続けているという。小屋の修復には日本人の著名な建築家が加わってもいる。
同じ感慨を私は尾崎翠についても持ったことがある。尾崎翠は現在ではその作品の評価は定着しているといえると思うが、それまでには長い年月があり、しかもその生涯は貧しく、晩年は無名のまま養老院で過ごしている。忘れられた作家の代表のような生涯を送ったのである。鳥取県が尾崎翠を顕彰し始めたことは嬉しいことだが、地域おこしとして作家や詩人、画家を行政が手がけることは、常に複雑な課題もはらんでいる。ポオの場合も、アルコール中毒や性的不能者、変態者であるという噂が彼の社会的認知を著しく歪めたように、作家や詩人、芸術家の性的特徴や俗社会の規範を逸脱したり、過剰な行動を行政がどのように理解するか、が課題となる。少しでも規定に外れたことを摘発し指導することを生業にする行政が、喜び推奨するような生き方をした人なら、芸術創作はしなかったのではないだろうかとさえ思ってしまう。ハリー レヴィンのいう文学の内包する「黒い力」を評価するには俗社会を超える想像力を必要とするのだ。
ポオが友人に恵まれなかったのも、ポオの生き方から当然のことでもあり、金持の女性からの援助を最終的には断ってしまう、その強情とも言える自負心に満ちた孤独への向かい合い方には、惹かれるものが多いが、尾崎翠には、彼女を尊敬し、貧しい時代をともに生きた林芙美子という友人がいた。鳥取に帰って創作をすっかりやめてしまった尾崎翠の消息を林芙美子は知らなかったことは事実だろうが、なぜ尾崎を探し出す努力や、文壇に連れ戻すだけではなく、せめて少しでも金銭的な援助ができなかったのかと、悔しいような、恨めしいような気持ちになる。長い晩年を沈黙し続けた尾崎翠への愛惜と無念と、同時に尊敬に満ちた気持ちを抱かずにはいられない。もし書き続けていたなら、どのような作品が生まれていただろうかと、優れた感性と想像力、才能を持った作家の沈黙に心を揺すぶられるのは私一人ではないだろう。 豊かになった現在の日本では新人作家を育てることがむしろ難しくなっているのは皮肉なことではあるが、同時に、創作へ駆り立てるもの、芸術家の想像力と感性の根源について多くを考えさせられるのである。
(了)