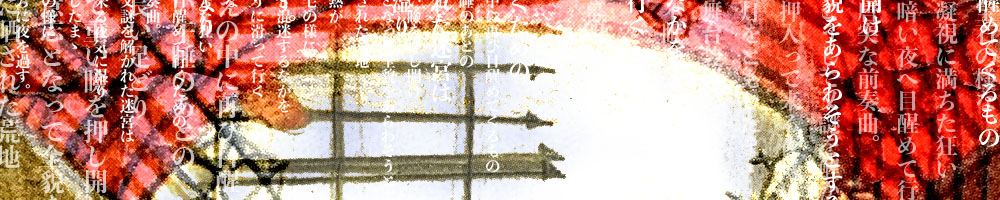
2023/01/31
私が最初に祖母と孫娘のフェミニズムについて考え始めたのは、マヤ・アンジェロウの『歌え飛べない鳥たちよ』(I know Why the Caged Bird Sings 1969)を読んだ時だった。その頃はまでアメリカに住んでいて、女性の自伝についていろいろと調べている時だった。女性の自伝は少なく、自伝といえば社会的に成功した男性が書くものと考えられていた時代で、自伝とはなんとなくいかがわしいという気をいつも持っていたが、女性の自伝について調べ始めると、いろいろな発見があった。
まず女性は自伝を書かなかったわけではなく、女性は「自伝的小説」を多く書いてきたということである。そして女性の自伝は、「女になる」というボーボワールのフェミニウムの根幹的なテーマを主題としているものが多いということだ。少年が男になる通過儀礼は、神話、民話、歴史ロマンス、そして教養小説のテーマだが、ほとんどの民族、文化集団は制度としても、たとえ儀礼化していたとしても、通過儀礼の伝統を持ち、維持してきていたのだ。しかし、少女が女になる通過儀礼は、少数の例を除いてはそれほど明確に制度化されていないように見えながら、男性のそれよりははるかに厳しい倫理的、道徳的規範が課せられてきたこともよくわかるのである。それが精神的。内面的に女性の自己意識の醸成に複雑な屈折を持つ道筋を描いてきたのである。
マヤ・アンジェロウとリリアン・ヘルマンの自伝(An Unfinished Woman1969)が、私が最も深い感銘を受けた自伝だった。主人公の少女の成長、つまり女性として、個人としての自己意識の形成過程には、必ず代理母が存在することが、その時分かったことの一つだった。
リリアン・ヘルマンの場合は、黒人の乳母だが、マヤ・アンジェロウにとっては祖母だった。
近代文学では、娘は母に抵抗し、また反面教師として反抗、無視、離反をしながら女性に成長していくことが顕著である。これは、日本文学にも、西欧文学にも共通する。マヤ・アンジェロウは祖母に育てられるが、それは、母が娘を預けて働いているからであり、社会からも、夫からも受ける黒人であることの人種差別と、女性であることの差別を、生き残るための闘争をしているからだ。その闘争は、生活費を稼ぐために働くということだけではなく、犠牲者として自分を潰されないための、あがきでもある。家族や、娘のことを顧みる余裕はない。なんとか成功して、金持ちになって社会を見返してやることだけが、母親世代を駆り立てる。
近代女性である母は、心のうちに自由への願望を持ちながらも、娘には結婚をして、母、妻として家父長制家族の中で安定した居場所を持たせたいと、ジェンダー制度の性規範を叩き込もうとする。また戦後日本の女性は、自らキャリアーウーマンを目指して働き、性的差別が生み出す格差に苦しんでいるために、娘にはより良い教育を授け、競争社会で成功する力を持たせたいと娘を競争に駆り立てる。その上、社会的成功とは、エリート男性と結婚して、社会の上層階級に居場所を得ることだとも思っている。それこそが成功の理想型なのだと。
娘は家庭か仕事かの二者択一ではなく、またキャリアーウーマンとしての単身での成功だけではなく、キャリアーも家庭もの二重の競争に勝つ力を持つように、母から期待され、教育される。それは母親自身の願望であるのだ。
しかし祖母はそうではない。差別の制度が人の心を縛り、傷つけてきた社会と文化の中で、生き残ってきた、いわば生活者としての生き残りの実践者として強者である。祖母のおおらかさ、少女の自由を縛ろうとせず、少女に競争力を持たせようと焦らず、性的規範も押し付けようとせず、どのように生きろと教えるわけでもないが、いつも明るく、自分自身のやり方で日常生活を生き続ける祖母の、頼りになるおおらかさに、安心を覚え、何かに追い立てられずに自分でいることができる心の余裕を得て育っていく。
それは過保護でも、放っておかれるのでもない、自分で感じ、考えることを必然とする、安心できる環境の条件なのである。本来的にはそれが家族という環境なのだが、父や母は、まず自分のことに精一杯で、また娘を社会人にする責任とは、娘に社会的制度の中での成功者になることだと信じているのだ。
祖母と暮らして、祖母の話を聞く、という素晴らしい経験、物語の楽しさを孫娘は知る。母である娘は自分のことで精一杯で、祖母の話などを聞く余裕も、その気もなかったので、家族の経験の話は、孫たちには伝わらないのである。語る人はいても、聞く人がいない。その物語の宝庫は、蓋を開けられずに放置されたままなのだ。
日本文学で、祖母と孫娘を基軸にした小説の中でも、私が一番好きなのは尾崎翠の『第七官界彷徨』である。尾崎翠自身、作家、詩人であることを強制的に辞めさせられて、姪や甥たちの代理母としてその長い「晩年」を送ったことを考えるとなんとも感慨深い。彼女は文壇や作家、友人たちから全く忘れられて長い人生を生活者として生きたのである。
最近祖母と孫娘を扱った映画を二つ、全く偶然にテレビで見た。
一つは『椿の庭』、そしてもう一つは『西の魔女が死んだ』という映画だ。共に美しい映像で魅了されるが、祖母と孫娘のテーマの他に、共通する異世界、異文化、異邦人というテーマが見えることも興味深く思った。『椿の庭』では、韓国人と「駆け落ち」して家を出た娘の子、という話の設定、そして『西の魔女が死んだ』は、森の中に住む「魔女」と呼ばれている祖母が、日本人の化石学者と結婚して日本に住み続けたアメリカ人の女性である。世俗世間、そして社会制度の規範の「外」を生きる「はぐれもの」というテーマが、はっきりと見えるのである。映画作品については次回に批評したいと思う。(続く)
( iiMWSニュースレター69号掲載 2023.1)
2023/01/31
先日蔵書を一部手放した。本棚のスペースが足りなくなり、熟慮の末、本の整理をすることにして、古本屋さんの店頭に置いてもらえるような「良い本」を選ぶのがいいと思った。私はこれまで、本を売ったことがなかった。棄てたことはもちろんない。戦後の本のない時代に育った私は、本は何よりも貴重なものだった。本を書くものとして、執筆の苦しさや喜びを知っているだけに、どの本も売ったり、捨てることはできないできた。私の亡くなった夫は、それに反して、読んだ本は次の本を買うために、古本屋で売る生活をして学生時代を過ごしたという。そこでは本は次の本を買うことのできる貴重な商品として通用していたことがわかる。彼は出版社でアルバイトをしていた学生時代から、生涯本を作る現場で仕事をしたので、本は彼の命と言ってもよかったのだ。小さな出版社を経営するようになった晩年には、古本屋を始めた元の同僚のために、商品となる本を自分の本棚から抜き出して持って行っていた。その姿を見ていたので、私はまず彼の蔵書を古本屋の棚に並べてもらうのがいいと思った。
ところが、私が良い本と思う本と、値のつく本とは全く違うことを知らされることになった。その上、古本業界の実態とは、私が本を探しによく出かける必要不可欠な場所や、夫を通して考えていた本の流通場所とは全く違うものになっていることも知った。心ある古本屋さんからは本が「捨てられる」までの経緯を詳しく説明してもらうことができたが、大抵の店は、いかに古い本は価値がないか、小説などの作品、そして、全集は引き取る価値がないとか、その上、本自体がもう売れる商品ではないこと、などをくどくどと説明される経験となった。人文分野を専門とする古書店でも、文学作品は買わない、という。デジタルでいつでも読めることと、作品を読む人が少なくなったことが理由だという。書き手の側から言えば、そのようなことはもうすでに長年、出版社や編集者から聞かされてきたので驚くことでははないが、古本屋に本を探しに出かける人を多く知ってもいるので、古本業界は本を商品として売ることが主なビジネスの出版業界とは少し異なるのではないかと思っていたのである。
空になった本棚のいく列かを見ると胸が痛んだ。夫は1950年代の初めの高校生だった頃から本つくりに関わってきた人で、森崎和江さんの「エロスと闘い」をはじめ彼が編集したり制作したりした本は多数である。それらは皆残しても、他のどれも彼が愛読したり、高く評価して大切にした本だからいい本に決まっていると、必ず本棚に並べてくださいと古本屋さんに頼んで、苦笑された。
戦後は本が本当になかった。戦争中は思想統制が厳しく、外国の書物はほとんど読めなかったし、占領時代も言論、思想統制があり、またひどい紙不足だった。独立して小さな出版社を経営するようになってすぐにオイルショックが来て、大変苦労したことも聞いている。本を売っては新たな本を買う生活をした時代を生き抜いて、本が捨てられる時代になった今日まで生きたことはつらかったのではないかとつくづく思う。作者を掘り出し、掘り当て、一冊の本を作るために何年もかけて共にリサーチをし、討論をして、著者の最初の本を多く作った経験を持つ戦後の編集者は彼一人ではなかったと思うと、そういう編集者や出版社が少なくなってしまった今、そして、古本を大切に引き受けてくれるのではなく、売れない、商品にもならない紙の束として持って行く古本屋引き取り人の後ろ姿を見ながら、大切な時代の終焉を痛感する経験となった。本はそばに置いておくだけで嬉しかったのにと今更ながら思う。
本を処分することは、断捨離の行為のように受け取られていることを感じたのである。家の中をスッキリさせ、空間を作り、心を整理することにお手伝いしますよ、と来てくれた親切な助っ人である。亡くなられた方の本、大学や研究所などからでる本などの回収で大変忙しいという話を聞いていると、反断捨離派の私は、一言、二言、言いたくもなってくる。そもそも断捨離は出家する人が、俗世の楽しみや欲望から身を離し、断ち切るための行為である。しかし現在では、戦後の消費経済時代に、物を買うことに価値を認め、欲求を膨らませた結果として、限られた生活空間を物で埋め尽くされて、身も心も、にっちもさっちもいかなかくなっている状態からの救済が、今流行りの断捨離であるだろう。別にそのことに反対しているわけではない。自業自得で物に埋もれて、自分では処理できなくなった人が、誰に助けを求めようと勝手である。
気になるのが、物をゴミとして捨てる、しかも自分の家から社会へゴミを出して、それを税金で、他者に処理してもらおうという行為である。ゴミを出して、家の中はスッキリしても、その後誰が、どのような賃金で回収し、どれだけ税金を使って、地球上で少なくなってしまっているゴミ捨て場へ運び、そして、どれだけのエネルギーを使って焼却し、どれだけの環境汚染を引き起こしているか、そのことには少しも考えを至らせないで、人生が変わりました、と言っていること自体が、そしてそれを助長するアドヴァイザーが、貧富の格差と環境汚染に加担しているかを知らないことである。
ほとんどの地域では住民がゴミ焼却炉の建設に反対する。しかし、ゴミは家から外に捨てる。個人が燃やすのではなくて、社会がその処理をするのである。バブルで物を買い続け、欲望を満足させてきた個人の後始末をさせられているのである。
そのゴミの量は年々増え続け、中でもコロナ時代には、通常の何倍かのゴミが出されてきているのである。親しい友人の息子さんはコロナで勤めていた店が次々と閉店し、今はごみ収集の仕事をしている。彼はその仕事にやりがいを覚えていて、色々と社会観察を進めているが、この間病院からのごみの出方が急増していること、そしてこれも急増した個人の家庭からのごみの出し方が乱暴になったことを話してくれた。中でも家庭からでるごみの多くがプラステイックの食べ物の容器であるという。
一般市民はマイバッグを持って買い物に行くが、お皿やボウルを持ってスーパーには行かないだろう。マイバッグを忘れると、3円から5円払ってプラステイックの袋を買わされる。なんという皮肉なことだろうか。私はいつも紙袋を要求するのだが、それが叶ったことは一度もない。薬局で、紙袋に入れてくださいと頼んだら、即座に断られた。個人は頑張っているのに、これでは全くの負け戦である。
本が紙製で、プラステイック製ではないのが、せめてもの慰みであった。
水田宗子
2022.11.5
(iiMWSニュースレター67号掲載 2022.12)
2023/01/31
『ねむらない樹』
詩歌のモダニズム
2022.93 エッセイ
(原稿なし)
2023/01/31
『現代詩手帖』わたし/たちの声、詩、ジェンダー、
2022.8月号 掲載
(原稿なし)
2022/01/20
歴史と表現 4
移動する身体と留まる身体
随分と昔の話であるが、1960年代のアメリカの大学では、大学院の所定の単位を取得した学生が論文を書くためには資格試験を受け、また、論文についての趣旨や方法などに関してのプロスペクタスを承認されなければならない、というのがほとんどの大学院で制度化されていた。それぞれの大学院によって、異なっているが、イエール大学の大学院では、口述試験もあり、教授たちからの質問に答えなければならなかった。その時の質問の一つに、歴史文学を定義せよ、ホーソーンの「緋文字」は歴史小説か、フォークナーのヨークナパトファ物語群はどうか、というのがあった。
私はその前に都立大学の大学院の入学試験で、ユートピア文学について書けという問題が出て、のちに自分の答えを検討する中で、歴史との関係について考えていたので、イエールでの質問はあまり唐突な問いのようには思えなかった。しかし、具体的に『緋文字』が歴史小説かと聞かれると、答えはyes and noで、歴史文学を定義しても、緋文字がそれにきちんと適合する小説なのかどうか、解釈をひねりださなければならない。なんといっても若い大学院生の私の知識は限られていて、この問いに対する答えも、それ以来、ずっと考え続けることになった。
『緋文字』は、アメリカの歴史で清教徒の街として名高いSalemの税関に努める作者らしき語り手が、古い資料の中にAという文字が書かれた胸当てを見つけて、その背後の物語を探求していくことからはじまる。Salemは魔女狩りの街としても有名で、数多くの女性が魔女と言われて火あぶりになった、おぞましい歴史を持つ街でもある。アーサー・ミラーの1953年の演劇Crusible(るつぼ)は、Salemの魔女狩り裁判を描いて、当時猛威を振るったアカ狩りのマッカーシズムを批判したことで、長い歴史的時を経てSalemが新たに脚光を浴びたばかり時でもあった。
マッカーシズムによる大規模な反アメリカ主義の弾圧の時代、アメリカニズムという観念の元に、異常なまで陰湿で粘質的なよそ者への偏見と差別、排除と処罰への執念が人々に恐怖心を抱かせ、友人を裏切ることを迫られる極限状況を作り出していた時代が、魔女狩りの、正義と正当化の理論で自己の宗教政治制度を守ろうとする残虐な魔女狩りと重なって描かれることに、多くの読者が共感した。口述試験では、『緋文字』の主人公へスター・プリンが、子供まで作った恋人で牧師のディムズデールを、一緒に街を出て逃げようと誘う森の中の逢引の場面の解釈も求められた。牧師を性的に誘惑して、さらに牧師としての任務を捨てさせようとするへスターは魔女なのか、ファム。ファタールなのか、という問いも含まれていたのだろうと思う。
物語はディムズダールが自らの罪を告白して死に、へスターと子供は、街を出てその後の居所は不明のままだという結末だが、その間へスターの夫のチリングワースが、彼ら二人の心を揺るがせて破局へ誘う、悪魔サタンの役割を果たしている。このアメリカ文学史上の古典であり、近代文学の傑作でもある作品は、アメリカが清教徒の宗教国から、民主主義主義の国へ進展していく過程の物語であり、牧師が、共同体の、普遍的な「父」と、ヘスタ―と子供のいる家庭の父であることとの間で苦しむ、多分に歴史的な変容と推移の背景の中で描枯れる小説でもある。
へスターが魔女であるかどうかは、解釈の重要なポイントと見ることもできるが、へスターが、ピューリタンという思想と規範によって形成された共同体を離れて、その外へ出ていくことを志向する女性であることは明白で、その共同体の性規範を逸脱して移動する身体と恋愛する身体、子を育てる身体が、一体化していることが大変興味深いのである。
一方フォークナーも南北戦争に敗れた南部の社会が、奴隷制度によって維持されてきた荘園農業経済と封建的家族制度が解体されていく歴史的変容の過程で、頑なに過去の世界に生きる人たちを描く。その中で、『エミリーのバラ』のエミリーは、へスターとは対極に位置付けられる「動かない身体」、「留まる身体」である。
愛した男が裏切りをしたことを知る近い、ホラーストーリの主役である。彼女は、生まれ育った家を一歩もでることなく、家に男を殺して引き入れ、そこにとどまり続ける。どのような歴史的変化も社会的な変容も受け入れず、個人の世界の外に出ようとしない、変化を拒む「動かない身体」である。
へスターもエミリーも恋愛する身体であるが、へスターは産む身体でもあり、新しい時代の中へ愛する男性に過去を捨てさせても出て行こうとすのに対して、エミリーは新時代のメッセンジャーである北部の男を、古い家に引きずり込み、共に白骨になるまでそこに留まる「産まない身体」である。子供を通しての未来はそこには存在しない。
「産む身体」、「産まない身体」という身体の記号化はこれまで女性の性、セクシュアリティを「産む性」に規範化した上で、分断し、対立させる、差別の概念を表象している。
「移動する女性」というタームは、この「産む性」、「産まない性」という分類、女性の性の分断を、異なる分類で撹乱し、なし崩しにする概念である。これまで、移動する女とは、結婚して家庭に定着しない女性、家父長制家族の形成する共同体に定着しない女性を意味した。家と共同体を離れて「外地」へ移民として出て行く女性、共同体の外へ周縁化され、追放され、あるいは自ら共同体の治外法権へ出て行く女性、放浪する女性像として用いられてきたが、移動する女も産む女であり、家庭内、共同体内に定着する女にも、産まない女もいる。山姥で表象される「山」に住む女には子連れも多く、生き残りの力強い身体を持っている。
移動する女はいわば、里、野、山のトポス概念を用いるなら、共同体である里を出て、里の性規範が及ばない野や山に出て行く女性ということができるだろう。野や山に住めば里の掟は及ばないが、同時に保護もされない。野に住む女は、里と様々な接点を持ち、経済的な交渉関係にもあり、その生存を多分に里に補完する役割を果たすことが多い。
へスター・プリンもまた、街=里の外に追放された女だが、助けが必要な里の人々を世話し、介護することで街=里の存在を助けている。胸に貼られた緋文字は、彼女が街に住む女ではなく、その境界線の外に住むが、役に立つ限りは一時的な出入りも許されている女であることを公に示す印なのである。野はへスターのように追放された女が住む「外部」なのである。
小説『緋文字』でへスターが、愛する牧師のディムズデールと森で密会をし、一緒に逃げようと誘う場面は、野のはずである。恐らくは人に見られることのない、森に隣接する野の奥深くの場所かもしれない。しかしそこはサタンの住む森ではないはずである。へスターの誘いは、共同体の宗教的な「父で」あることを捨てて、一家族の個人的な父になってほしいという願いなのである。共同体の人々に宗教的、思想的な責任を果たすが、それだけに揺るがない権威と権力を有する大文字の父から、一介の、一人の男として、妻と子供の小文字の父となることを、それが幸せであると説得しようとしているのだ。
19世紀半ばから急速に進む、フロンティアの消滅、そして、宗教的ではない共同体としての民主主義アメリカの建設にとって、家族こそが、価値の源泉とみなされる民主主義の礎とされる時代が到来してきているのである。メルヴィルの『白鯨』における海と白鯨が象徴する自然=野性の消滅、そして海よりは陸への定着という、思想的、価値観的変容と歴史的展開が、『緋文字』のヘスターとデイムズデールの対立であり、二人の価値観の分断は歴史的な流れの中で起こっているのである。
名前のごとく、二つの間を揺れ動き、「曖昧な」牧師は、罪を公に告白して死んでしまい、二人の相反は、古い父の死と、「不倫」を自由な個人の恋愛だと主張する女が街の外に出て行く、移動する女となることで、解決をする。シングルマザーとなって自立し、家への定着を拒否するへスターは、男女平等が進むアメリカの象徴でもある。
移動する女を主人公とする林芙美子の『浮雲」は、19世紀のアメリカ小説『緋文字』とは異なって、「移動する女の身体」が、性規範を逸脱した女として処罰される小説である。この小説の女性差別構造は有島武郎の『或る女』の構造と同じである。この二つの小説の主人公の女性は、家庭からその外部へ、そして、『浮雲』では屋久島という日本国境界の僻地の島へ、また『或る女』ではアメリカへと移動して行くのだが、そこで、子宮の病気になり死亡する。彼女たちの居場所は里にはなく、里の外へ自分の思う自由を求めて移動する女は、子宮という女性の生殖器を侵され、生き残ることができないのである。移動する身体の生き残る場は、野でもなく、その果ての山にしかないだ。「移動する身体」は「産めない身体」として規範化にはめ込まれているのである。
ヘスタープリンが、自分のアイデンテティとして、積極的に胸に貼り付けたAという、共同体が追放者として刻印した記号が、姦通という忌まわしく、毒々しい記号から、異なった価値と意味を発信する可能性を示唆する曖昧な刻印に変容するのに反して、共同体の性規範からの逸脱、共同体から外に出ることが、「産めない身体の女」として刻印され、処罰されるという露骨な女性のセクシュアリティへの差別を、悲劇として描く作者の思想と想像力は、アメリカ小説から1世紀遅れたとはいえ、戦後社会の歴史的流れを見据えた反逆の「悲劇」として感動させられる。
へスター・プリンは恋を失ったが、自由を手にした。追放者の居場所、野は、自由への出口となった。場所とはそういうものなのだ。トポスとしての意味は、記憶として文化の中に生き続けるが、それゆえにこそ、場所は逆転の契機をはらんでいる。それが歴史的に見るという視野のことであり、歴史小説は同じ題材で、書き直され、書き換えられていく、連綿と続く記憶の体積の言語化なのであるだろう。
水田宗子
2021.12.22
2022/01/20
2014年ノーベル賞受賞者のパトリック・モディアーノ(Patrick Modiano)の小説の世界は「人探し」の世界である。イタリア系ユダヤ人の父を持ち、フランスで育ったモディアーノは殺戮収容所に連れて行かれたユダヤ人を親族にも、そして両親の友人、知り合いにも多く持っている。戦争後収容所が解放された後は、生死がわからない人が多く、「人探し」は戦後世界を生きる人たち、戦争と虐殺を生き延びた人たちの実存状況と言っていい。どこかに隠れているに違いない人たち、逃げ延び、生き延びて、どこかの町の片隅に、名を伏せ、過去を消して、ひっそりと暮らしているに違いない人たちを探し出すのは、生き残った人たちの役目である。
日本の戦後も同じだった。外地から引き上げてきた人、戦地から帰ってきた人、空襲で散り散りになったままの人、捕虜になった人やシベリアへ送られた人、行方知らずの人たちを、親族が探し回ったのである。ラジオの「尋ね人」は日常よく聞いたし、新聞の尋ね人欄は、戦後いつまでもあった。
東京は戦後すぐに闇市ができ、身元のよくわからない人たちが集まったり、暮らす場所ともなった。身元がはっきりしているということは、戸籍の問題だけではない。戦争を生き残った人は、どこかで心の傷を抱えている。尊厳を傷つけられた傷、後ろめたいこと、隠したいことを心のうちに抱えていて、できれば、語らず、人知らず、自分の存在を隠して、今をしのいで、現在を生き抜きたいと思っている人もいるはずだった。
モディアーノのノーベル賞受賞小説は、私立探偵事務所に努める男が、人探しを頼まれて、パリを探し回り、様々な、名も知らない人々の、隠されていた秘密=真実を知っていく話である。殺戮収容所へ連れて行かれたユダヤ人の少女を探す作品もある。モディアーノの世界で興味深いのは、パリという都市には、様々な裏通りや、安ホテル、下宿屋などのある地域が、パリの発展から取り残された場所として残っていることだ。パリの中心地や高級住宅街は、整然とした道路に、番号がついている建物が並んでいる。家を探すのは苦労がないが、それだけに、人が隠れて住むには適していないのである。
ゴダールの映画を見ても、そのような身元を隠したい人たちが住めるような、ごみごみとした場所があることがわかる。ジャン・ギャバンの世界でもおなじみである。アメリカ映画ならば、フィルム・ノアールの世界がそれに当たるだろうし、香港ならば、有名な九龍城があった。大都市とは、アンダーグラウンドとまではいかないまでも、そのような隠れ場所を内包する場所なのであった。
故郷を捨て、家を出たものたちは、都会ならばどこか行き場所、暮らし場所を見つけることができた。国外へ脱出するまでもなく、都市の中に、身を隠して生きる場所が、残っているのが大都会、近代メトロポリスなのである。移民、難民、亡命、ディアスポラの大規模な出現は二十世紀の世界的惨事の結果であるが、犯罪者や家出娘、息子だけではなく、スパイや革命家、暗殺者も名前や身元を隠して生きる場所があったのである。
モディアーノの人探しは、ユダヤ人たち、中でもあまり有名ではない芸術家やその恋人、家族など周辺の人々が、散逸し、それぞれが生き残るために少々いかがわしい世界に引き込まれていく話が多く、胸を打たれる。モディアーノ自身の父親もその一人らしい。綺麗事で立派に居残る術などないことを思い知らされるのである。小栗康平の『泥の河』の世界だ。
女性の居場所が、家庭内に限られていて、留学、移民、写真花嫁を除けば、女性が自由に海外へ移住することがほとんど不可能であった近代日本で、東京に地方から出てきた作家志望の女性たちにとっては、下宿暮らしが唯一の居場所であった。良家の女子は、兄の下宿、親戚の家が上京後の住み場所であったが、それも女性の自由を可能にする居場所ではなかった。林芙美子の『浮雲』の主人公の、東京へ、そして植民地ベトナムへの脱出は、同じ反逆と脱出のトポグラフィに位置付けられる。
近代における女性の家制度からの脱出を考える上で、居場所(=トポス)の持つ意味は重要である。西欧モダニズムは、芸術表現の権威の場であるパリから離れた、いわば文化的僻地から来た芸術家が、その台頭に前衛的な役割を果たした。パリはそのような周辺地から来た外国人の若く無名の芸術家が住める場所がどこかにあった都市でもあったのである。アメリカからの亡命者ガートルード・スタインがそのような若く無名な芸術家や作家の集まるサロンを持ち、戦争後の国籍離脱者や身元不明なはぐれものの貧しい芸術家や作家の居場所となっていたこともよく知られている。
東京もその役割を果たせる都市であった。作家や詩人、画家を目指す女性の多くは、地方都市から脱出して文化の中心地、東京へ来た。東京はさらに外国との接点であり、外地への出口でもあった。地方都市、東京、海外植民地=移民のコミュニティの三場所は、新しい女性表現にとっての不可欠なトポスとして存在したのである。女性作家の家からの解放は、地方都市というマイナー文化拠点からの脱出に見られる。閉鎖的な家父長制家族の文化が強い地方都市からの脱出は、東京へ、西欧文化へと向く移動のベクトルを示している。
脱出する、移動することを通しての居場所の探求は、抑圧や差別からの脱却を目指す表現者の必然的な道であったのは世界共通である。植民地時代、そして、戦後のポストコロニアル世界では、脱出と移動は、女性表現を可能にする唯一の実質的な道であった。
男性の中央へ向かっての移動は、大学教育と将来の社会的地位を約束する道であり、ホモソーシャルなエリート共同体の一員となる道であったが、女性にとって東京は、そのような機会を提供する場ではなく、共同体の一員になるには結婚しかなかったのである。それは家への再度の封鎖でしかない。
移民のコミュニティという国内の「外地」も、多くは都会の中に、というよりはその外れあたりに、作られてきた。それは文化の僻地であるが、文化・政治の中心としての東京からの脱出先であったことが、地方都市と大きく異なっている。都会の「僻地」は、国家権力と文化伝統の権威と抑圧から自由なノーマンズ・ランドでもあったのである。
外地の、都市を中心とした非農民移民コミュニティ、つまり、ディアスポラ集団の居場所が形成されていく過程は、アメリカやフランスにおけるユダヤ系文学・芸術、アジア系文学の展開する場の形成と同じ位相を有している。そこは自国語の新聞、文芸雑誌というメディアが形成されていき、脱出者に居場所を提供する場となっていく。アメリカでイエディッシュ呉の文学が書かれた背景である。
都市には当然貧民窟があり、産業革命以後、日本では明治以降は、日雇い労働者が苦しい労働と低い賃金で木賃宿に寝泊まりする場を形成していたし、地方出の労働者だけではなく、貧困から抜け出せない、「長屋」に住む家族も住んでいた。
東京は、単一な場所ではなく、常に外へと広がり続ける場所であった。新しい歓楽街、住宅街、そして文士村が、中心から外へ向かって環を描きながら広がっていく途中の、「移動する都市」なのである。関東大震災後は、住宅地が郊外へ移っていき、新しい歓楽街や商店街が、郊外方面へできていったのである。
そこでは、地方から上京してきた人たち、アナーキストや貧しい芸術家や作家たち、そして社会規範と権威からの「はぐれもの」の住む場所が、発展から取り残されていくところ、例えば、浅草、上野、谷中にできるていき、女性の不正規労働者として働く場所と家を持たない女性たちが、借り部屋暮らしができる界隈ができてくる。林芙美子や尾崎翠、また、プロレタリア作家たちが住んだ上落合、下落合界隈は、振興歓楽街の新宿に歩いて行かれる距離にあった。田端から、馬込、高円寺と、作家村ができていくと同時に、未だ畑が広がり林が残る世田谷、杉並の郊外へと都市サラリーマンの住宅街が広がっていったのである。作家の居場所と近代都市、東京の形成は深く関わっているのである。
作家の長谷川時雨や田村俊子が生まれた浅草、日本橋地域は、「山の手」である帝国大学、一高のある本郷台地、博物館のある上野台地から坂を下った谷間に当たる寺町で、昔から住み着いている商人や職人たちの庶民文化の中心地である「下町」であった。隅田川に近いために、セーヌ川の左岸を真似たサロンを詩人や画家が集まって形成していたことで知られているが、一高、東大のある「山手」に住む医者、学者、弁護士など知識人の住む場所から見れば、近代都市発展に取り残されていく、モダンではない「下町」である。夏目漱石や森鴎外は団子坂、道玄坂の上の方に、反対に樋口一葉は、漱石が『門』を書いた本郷台地の奥の西片町を植物園方面へ急降下した低地の、当時はあまり「陽の当たらない」丸山福山町に住んでいた。
同じように、東大前から低地へ下がる坂の始まるあたりの森川町には、多くの下宿屋や旅館が作家たちの仮住まいを提供する場を作っていた。石川啄木、今東光、林芙美子など実に多くの作家たちがその界隈に一時は住んだのである。
他方、東京生まれの宮本百合子、平塚らいてう、円地文子は、学者や官吏、建築家といった知的中産階級の出身で、田村俊子と長谷川時雨は商人の出身である。その違いが山手、下町の住む場所に象徴的に表されていることは興味深いが、男性に反して、女性作家には山手の住宅地への上昇移動の道は、結婚以外に拓けていなかったのである。
昔の東京、戦前や敗戦直後の東京は、上京してきた無名の芸術家や作家、地方出の働く女性、「はぐれもの」が隠れるように生きる場所として好都合な、裏通りや片隅、安下宿などのある界隈を持つ都市となっていったのであるが、其の名残りは、戦後の都市計画、都電廃止、道路拡張、高速道路建設、地画整理や町名変更、高層建築化。郊外の団地建設、スパーマーケットなどで、年々なくなっていき、現在では、東京の記憶取り戻しも、なかなか困難な状態にある。
それは戦後の現象だけではなく、軍事政権による管理体制の強化によって、家を出た女性やはぐれものの居場所の消滅が急速に進むのが一九三〇年代半ばからである。それは田舎から働きに出される若い女性が、働きながら生活する場としての(住み込みのお手伝い)、都市中産階級が、戦争が深まり、男性が戦地に引き出され、統制経済の進展に従って、減少していく過程でもあった。東京は次第に、全ての住民が管理体制に置かれる、「はぐれもの」や兵士にもなれない、子供も産まない「役立たず」の一人暮らしが困難な場となっていったのである。
そもそも戸籍制度は日本や中国特有の管理体制であり、国民が国土内に隠れて住めないようにする法制度である。神社と寺とともに、生死、結婚、家族の追跡ができるための制度なのである。例えばアメリカでは、社会保障制度が国民の管理、追跡を可能にする制度であるし、コロナ感染者の居場所や濃密接触者の追跡や、ワクチン証明書、マイカードシステムの導入が、国民の安全という見地から、「はぐれもの」が住めないような体制作りを目指すものだ。
私は東片町、西片町、森川町と本郷界隈に住み続けてきたので、この一帯は焼け残った街にもかかわらず、その変貌ぶりには日々驚いてきた。大学を卒業して、アメリカへ留学した時には、西片町は番地がい ろ はに分かれてついていて、西片町10―ろ−17などという番地だった。夏目漱石が『門』を書いたのは、西片町10―ろー7という番地の家で、現在は、自宅の近くなのに、番地をたどってはすぐに見つからないのだ。オリンピック以後は、町名も番地も整理されて、その上今はグーグルマップもあって、番地を頼りに場所を探すのが大変容易になった。その代わり、どんな家に住んでいるかも検索すればすぐにわかるようになった。プライヴァシーは著しくなくなったのである。
助けが必要な人たちが見えなくなっている状況や、病気の高齢者、取り残されてしまう子供達がかくされてしまうことも、都市の厳しい特徴で、どこに誰が住んでいるかが分かる制度ができれば、それだけ安心が増す。ひとりひとり、隅々まで管理される社会と、どちらも、居心地は良くないだろう。ニューヨークも、ロンドンも、パリも、同じだろうと思う。
パリではモディアーノの小説にも出てくるユダヤ人の革命家たちが住んだホテルに泊まったことがある。また近年、通りの角ごとに監視カメラがあるロンドンの街を歩いて、ヴァージニア・ウルフの家を、そしてシルヴィア・プラスとフロイドの家を見学した。住んでいた人たちはもういないが、家という物体は残っている。それらは歴史の何を表現しているのか。個人の痕跡が聞くとなり、また歳の記憶ともなる媒体は、家や道、や界隈というトポスであり、それは、訪れる人、返ってくる人と、歴史をつなぐ関係の場としてあるのだと思った。
終わり
2021/12/20
2014年ノーベル賞受賞者のパトリック・モディアーノ(Patrick Modiano)の小説の世界は「人探し」の世界である。イタリア系ユダヤ人の父を持ち、フランスで育ったモディアーノは殺戮収容所に連れて行かれたユダヤ人を親族にも、そして両親の友人、知り合いにも多く持っている。戦争後収容所が解放された後は、生死がわからない人が多く、「人探し」は戦後世界を生きる人たち、戦争と虐殺を生き延びた人たちの実存状況と言っていい。どこかに隠れているに違いない人たち、逃げ延び、生き延びて、どこかの町の片隅に、名を伏せ、過去を消して、ひっそりと暮らしているに違いない人たちを探し出すのは、生き残った人たちの役目である。
日本の戦後も同じだった。外地から引き上げてきた人、戦地から帰ってきた人、空襲で散り散りになったままの人、捕虜になった人やシベリアへ送られた人、行方知らずの人たちを、親族が探し回ったのである。ラジオの「尋ね人」は日常よく聞いたし、新聞の尋ね人欄は、戦後いつまでもあった。
東京は戦後すぐに闇市ができ、身元のよくわからない人たちが集まったり、暮らす場所ともなった。身元がはっきりしているということは、戸籍の問題だけではない。戦争を生き残った人は、どこかで心の傷を抱えている。尊厳を傷つけられた傷、後ろめたいこと、隠したいことを心のうちに抱えていて、できれば、語らず、人知らず、自分の存在を隠して、今をしのいで、現在を生き抜きたいと思っている人もいるはずだった。
モディアーノのノーベル賞受賞小説は、私立探偵事務所に努める男が、人探しを頼まれて、パリを探し回り、様々な、名も知らない人々の、隠されていた秘密=真実を知っていく話である。殺戮収容所へ連れて行かれたユダヤ人の少女を探す作品もある。モディアーノの世界で興味深いのは、パリという都市には、様々な裏通りや、安ホテル、下宿屋などのある地域が、パリの発展から取り残された場所として残っていることだ。パリの中心地や高級住宅街は、整然とした道路に、番号がついている建物が並んでいる。家を探すのは苦労がないが、それだけに、人が隠れて住むには適していないのである。
ゴダールの映画を見ても、そのような身元を隠したい人たちが住めるような、ごみごみとした場所があることがわかる。ジャン・ギャバンの世界でもおなじみである。アメリカ映画ならば、フィルム・ノアールの世界がそれに当たるだろうし、香港ならば、有名な九龍城があった。大都市とは、アンダーグラウンドとまではいかないまでも、そのような隠れ場所を内包する場所なのであった。
故郷を捨て、家を出たものたちは、都会ならばどこか行き場所、暮らし場所を見つけることができた。国外へ脱出するまでもなく、都市の中に、身を隠して生きる場所が、残っているのが大都会、近代メトロポリスなのである。移民、難民、亡命、ディアスポラの大規模な出現は二十世紀の世界的惨事の結果であるが、犯罪者や家出娘、息子だけではなく、スパイや革命家、暗殺者も名前や身元を隠して生きる場所があったのである。
モディアーノの人探しは、ユダヤ人たち、中でもあまり有名ではない芸術家やその恋人、家族など周辺の人々が、散逸し、それぞれが生き残るために少々いかがわしい世界に引き込まれていく話が多く、胸を打たれる。モディアーノ自身の父親もその一人らしい。綺麗事で立派に居残る術などないことを思い知らされるのである。小栗康平の『泥の河』の世界だ。
女性の居場所が、家庭内に限られていて、留学、移民、写真花嫁を除けば、女性が自由に海外へ移住することがほとんど不可能であった近代日本で、東京に地方から出てきた作家志望の女性たちにとっては、下宿暮らしが唯一の居場所であった。良家の女子は、兄の下宿、親戚の家が上京後の住み場所であったが、それも女性の自由を可能にする居場所ではなかった。林芙美子の『浮雲』の主人公の、東京へ、そして植民地ベトナムへの脱出は、同じ反逆と脱出のトポグラフィに位置付けられる。
近代における女性の家制度からの脱出を考える上で、居場所(=トポス)の持つ意味は重要である。西欧モダニズムは、芸術表現の権威の場であるパリから離れた、いわば文化的僻地から来た芸術家が、その台頭に前衛的な役割を果たした。パリはそのような周辺地から来た外国人の若く無名の芸術家が住める場所がどこかにあった都市でもあったのである。アメリカからの亡命者ガートルード・スタインがそのような若く無名な芸術家や作家の集まるサロンを持ち、戦争後の国籍離脱者や身元不明なはぐれものの貧しい芸術家や作家の居場所となっていたこともよく知られている。
東京もその役割を果たせる都市であった。作家や詩人、画家を目指す女性の多くは、地方都市から脱出して文化の中心地、東京へ来た。東京はさらに外国との接点であり、外地への出口でもあった。地方都市、東京、海外植民地=移民のコミュニティの三場所は、新しい女性表現にとっての不可欠なトポスとして存在したのである。女性作家の家からの解放は、地方都市というマイナー文化拠点からの脱出に見られる。閉鎖的な家父長制家族の文化が強い地方都市からの脱出は、東京へ、西欧文化へと向く移動のベクトルを示している。
脱出する、移動することを通しての居場所の探求は、抑圧や差別からの脱却を目指す表現者の必然的な道であったのは世界共通である。植民地時代、そして、戦後のポストコロニアル世界では、脱出と移動は、女性表現を可能にする唯一の実質的な道であった。
男性の中央へ向かっての移動は、大学教育と将来の社会的地位を約束する道であり、ホモソーシャルなエリート共同体の一員となる道であったが、女性にとって東京は、そのような機会を提供する場ではなく、共同体の一員になるには結婚しかなかったのである。それは家への再度の封鎖でしかない。
移民のコミュニティという国内の「外地」も、多くは都会の中に、というよりはその外れあたりに、作られてきた。それは文化の僻地であるが、文化・政治の中心としての東京からの脱出先であったことが、地方都市と大きく異なっている。都会の「僻地」は、国家権力と文化伝統の権威と抑圧から自由なノーマンズ・ランドでもあったのである。
外地の、都市を中心とした非農民移民コミュニティ、つまり、ディアスポラ集団の居場所が形成されていく過程は、アメリカやフランスにおけるユダヤ系文学・芸術、アジア系文学の展開する場の形成と同じ位相を有している。そこは自国語の新聞、文芸雑誌というメディアが形成されていき、脱出者に居場所を提供する場となっていく。アメリカでイエディッシュ呉の文学が書かれた背景である。
都市には当然貧民窟があり、産業革命以後、日本では明治以降は、日雇い労働者が苦しい労働と低い賃金で木賃宿に寝泊まりする場を形成していたし、地方出の労働者だけではなく、貧困から抜け出せない、「長屋」に住む家族も住んでいた。
東京は、単一な場所ではなく、常に外へと広がり続ける場所であった。新しい歓楽街、住宅街、そして文士村が、中心から外へ向かって環を描きながら広がっていく途中の、「移動する都市」なのである。関東大震災後は、住宅地が郊外へ移っていき、新しい歓楽街や商店街が、郊外方面へできていったのである。
そこでは、地方から上京してきた人たち、アナーキストや貧しい芸術家や作家たち、そして社会規範と権威からの「はぐれもの」の住む場所が、発展から取り残されていくところ、例えば、浅草、上野、谷中にできるていき、女性の不正規労働者として働く場所と家を持たない女性たちが、借り部屋暮らしができる界隈ができてくる。林芙美子や尾崎翠、また、プロレタリア作家たちが住んだ上落合、下落合界隈は、振興歓楽街の新宿に歩いて行かれる距離にあった。田端から、馬込、高円寺と、作家村ができていくと同時に、未だ畑が広がり林が残る世田谷、杉並の郊外へと都市サラリーマンの住宅街が広がっていったのである。作家の居場所と近代都市、東京の形成は深く関わっているのである。
作家の長谷川時雨や田村俊子が生まれた浅草、日本橋地域は、「山の手」である帝国大学、一高のある本郷台地、博物館のある上野台地から坂を下った谷間に当たる寺町で、昔から住み着いている商人や職人たちの庶民文化の中心地である「下町」であった。隅田川に近いために、セーヌ川の左岸を真似たサロンを詩人や画家が集まって形成していたことで知られているが、一高、東大のある「山手」に住む医者、学者、弁護士など知識人の住む場所から見れば、近代都市発展に取り残されていく、モダンではない「下町」である。夏目漱石や森鴎外は団子坂、道玄坂の上の方に、反対に樋口一葉は、漱石が『門』を書いた本郷台地の奥の西片町を植物園方面へ急降下した低地の、当時はあまり「陽の当たらない」丸山福山町に住んでいた。
同じように、東大前から低地へ下がる坂の始まるあたりの森川町には、多くの下宿屋や旅館が作家たちの仮住まいを提供する場を作っていた。石川啄木、今東光、林芙美子など実に多くの作家たちがその界隈に一時は住んだのである。
他方、東京生まれの宮本百合子、平塚らいてう、円地文子は、学者や官吏、建築家といった知的中産階級の出身で、田村俊子と長谷川時雨は商人の出身である。その違いが山手、下町の住む場所に象徴的に表されていることは興味深いが、男性に反して、女性作家には山手の住宅地への上昇移動の道は、結婚以外に拓けていなかったのである。
昔の東京、戦前や敗戦直後の東京は、上京してきた無名の芸術家や作家、地方出の働く女性、「はぐれもの」が隠れるように生きる場所として好都合な、裏通りや片隅、安下宿などのある界隈を持つ都市となっていったのであるが、其の名残りは、戦後の都市計画、都電廃止、道路拡張、高速道路建設、地画整理や町名変更、高層建築化。郊外の団地建設、スパーマーケットなどで、年々なくなっていき、現在では、東京の記憶取り戻しも、なかなか困難な状態にある。
それは戦後の現象だけではなく、軍事政権による管理体制の強化によって、家を出た女性やはぐれものの居場所の消滅が急速に進むのが一九三〇年代半ばからである。それは田舎から働きに出される若い女性が、働きながら生活する場としての(住み込みのお手伝い)、都市中産階級が、戦争が深まり、男性が戦地に引き出され、統制経済の進展に従って、減少していく過程でもあった。東京は次第に、全ての住民が管理体制に置かれる、「はぐれもの」や兵士にもなれない、子供も産まない「役立たず」の一人暮らしが困難な場となっていったのである。
そもそも戸籍制度は日本や中国特有の管理体制であり、国民が国土内に隠れて住めないようにする法制度である。神社と寺とともに、生死、結婚、家族の追跡ができるための制度なのである。例えばアメリカでは、社会保障制度が国民の管理、追跡を可能にする制度であるし、コロナ感染者の居場所や濃密接触者の追跡や、ワクチン証明書、マイカードシステムの導入が、国民の安全という見地から、「はぐれもの」が住めないような体制作りを目指すものだ。
私は東片町、西片町、森川町と本郷界隈に住み続けてきたので、この一帯は焼け残った街にもかかわらず、その変貌ぶりには日々驚いてきた。大学を卒業して、アメリカへ留学した時には、西片町は番地がい ろ はに分かれてついていて、西片町10―ろ−17などという番地だった。夏目漱石が『門』を書いたのは、西片町10―ろー7という番地の家で、現在は、自宅の近くなのに、番地をたどってはすぐに見つからないのだ。オリンピック以後は、町名も番地も整理されて、その上今はグーグルマップもあって、番地を頼りに場所を探すのが大変容易になった。その代わり、どんな家に住んでいるかも検索すればすぐにわかるようになった。プライヴァシーは著しくなくなったのである。
助けが必要な人たちが見えなくなっている状況や、病気の高齢者、取り残されてしまう子供達がかくされてしまうことも、都市の厳しい特徴で、どこに誰が住んでいるかが分かる制度ができれば、それだけ安心が増す。ひとりひとり、隅々まで管理される社会と、どちらも、居心地は良くないだろう。ニューヨークも、ロンドンも、パリも、同じだろうと思う。
パリではモディアーノの小説にも出てくるユダヤ人の革命家たちが住んだホテルに泊まったことがある。また近年、通りの角ごとに監視カメラがあるロンドンの街を歩いて、ヴァージニア・ウルフの家を、そしてシルヴィア・プラスとフロイドの家を見学した。住んでいた人たちはもういないが、家という物体は残っている。それらは歴史の何を表現しているのか。個人の痕跡が聞くとなり、また歳の記憶ともなる媒体は、家や道、や界隈というトポスであり、それは、訪れる人、返ってくる人と、歴史をつなぐ関係の場としてあるのだと思った。
終わり
2021/09/30

2021/05/19
「富岡多恵子論:はぐれものの思想と語り」(「めるくまーる」2021)
住本麻子さんのインタヴュー「週刊読書人」(2021.4月30日号)
2021/05/19
宗近真一郎さんの「音波」、「詩の魅力/詩の領域」(思潮社2030))書評. 「図書新聞」
2021/05/19
2021/03/9
シルヴィア・プラスについて書いていた頃、西欧の女性詩人が私の知っている限り妊娠や出産について詩を書いていないことに気がついた。そもそも女性詩人の数は多くなく、妊娠や出産経験をしている詩人が少なかったこともあるだろう。しかし、それ以上に、女性に限られると思われてきた妊娠や出産が、経験とともに、思考の対象としても男性の思考範囲には入っておらず、詩のテーマとしても、日常的、卑近な出来事である、という女性的、身体的な経験への無視と蔑視があったのだと考える。社会、国家、神について思考することが思想・哲学の根幹であり、妊娠、出産は女子供の、身体的経験として詩のテーマから排除されてきたのである。
シルヴィア・プラスはおそらく妊娠・出産を詩のテーマにした最初の詩人ではないだろうか。「三人の女」は出産経験だけではなく、流産経験も三人の中の一人のペルソナに語らせている。その出来事の前提には男性との恋、そして裏切りがあり、その「惨事」からの回復と新生への切なる希求が、テーマであると言えるだろう。その痛みと苦しみに、そして回復、生き延びへのあがきが身体的な経験として表出されているのだ。
出産のテーマと文学の関わりにつて考えた時、私が思い出したのは、ヘミングウエイの短編「インディアン部落」だった。インディアン女性の逆子の苦しい出産で、主人公少年の父親の医者が、麻酔なしの帝王切開をして赤ん坊を取り上げる。助ける。インディアンの夫は、出産に参加するという部落の習慣のためにその場にいたが、妻の苦しみに耐えかねて、自殺をしていた。生まれ出ることと、命を絶った父親との命の入れ替わりが、同じ場で行われ、そこには、苦しみを乗り越えて命を世に産み出す女性の身体と、他者の苦しみに耐えきれずに命を立つ男性の身体経験とが対比されてもいるのだ。帰りの舟の中で、手術の成功を自慢する医者の父親の側で、少年は湖の水の中に手を入れる。その暖かさに、いのちを感じるのだ。
この小説が、プラスの詩を介して、妊娠、出産と文学のことを考えた時に浮かんだ唯一の作品だった。他に思い浮かばなかったほど、妊娠。出産経験は詩や文学のテーマにふさわしくない、日常の、女性的な、身体経験と見なされていたことがわかる。1970年以降女性詩人は次第にその数を増し、女性経験と身体経験は、男性の頭脳経験との対比という図式から離れて、それ自体が、命の体験であり、実存の経験であることが、詩のテーマと題材になってきている。
最近私が読んだ詩集『星を産んだ日』(青木由弥子『詩と思想』2017)はだんだんと詩に表現され始めた妊娠、出産を扱った詩の中でも、深い思考と身体体験が一体化したいのちの起源への感性を見事なことばの表現へ結晶させている。
父親の死と子の誕生という生と死の、命の循環を、現実の目の前の、体内と外部をつなぐ身体経験として感じ、捉える感性が、詩集に納められた全ての詩に共通していて、いのちのありようが、その生まれるさまが、そしてその熟し終わっていく「時」の、手のひらに掴みきれない「感触」が、微妙な、そして時には、赤裸々な自然現象の中に感じられている。
雲が動いた
切れ間から陽矢が海を貫く
油凪の灰色の海
薄い皮膚の下で
たしかになにかが
再び
生まれ出ようとしている
(「陽矢」)『星の生まれた夜』)
命を感じる時にはペルソナの前には海が広がっている。そして木々の枝がしなやかに伸び、根が地を這っている。草叢が茂り、何かの気配があり、そして果実が実りだし、魚が産卵をしている。そこには命の起源としての自然の感触、通り過ぎていくものの、つかめない塊の気配と、やがてくだもの実となって確かな存在をあらわにするものの気配に満ちている。
海がふくらんでいく
うずくまっていたものが
ゆっくりと足をのばし雄叫びをあげる
通り過ぎる気配だけが吹き抜け
押し寄せる透き通ったかたまりが
私をのみこみあふれ流れ
―――――――――――
喉をうるおし身をやしなう
あなたの果実が
天をおおう枝の網目に
たわわに実り
夜を埋め尽くして
輝いている
(「くだもの」『星を産んだ日』)
果実の実りと魚の卵の塊はいのちの始まりの形としてその物体性を顕現化しながら、いのちの原型を表していく。魚の卵の塊は石榴の赤い実と等値化され、そのいのちの太古の姿と、その熟れゆく、機が熟しゆく、自然の経過が生まれ出る時と等価される。それは体内の、記憶の底の暗闇から光り出るものであり、夕闇へと沈む太陽の爛熟した赤色でもあり、生まれ出るものと消えゆくものとの循環を示唆しながら、その強烈な存在感を、前景化していく。
熟れきった石榴のような卵塊を
人肌のぬるま湯に沈める
赤い蜘蛛の巣を指先に受けて
半透明の卵膜から
好きとオタ粒をしごきとる
夕日の雫が生まれ落ちる
水中で回りながら沈んでいく
耐えきれず枝から落ちる
果物のような粒々
弾けて流れていく
オレンジ色のたまご
私の中の暗闇に落ちていく光
夜の海に落ちていく赤い月
(「回游」
この詩集には赤児を指で触り、腕に抱く皮膚の感触と、互いが応答し合う温もりと不安、また、自分の身体を突き抜けてやってきたいのちへの、驚きとその確かな存在感を、母体である自分、産むという行為を経た自分の身体との交感と距離の一体化した経験として表出する詩人の鋭い触手が偏在している。
甲羅を持たないままで生まれた無防備ないのちへの、神経の回収をまたぬ瞬時の皮膚の触手で受け止める繊細な母胎がそこにいる。それは身体ではあるが、森や草むらや海のある自然の中の一存在であることを感じている。これらの詩群は、揺らぎ、突き抜け、流れる曖昧ないのちの起源をかいま見せながら、その行く末を地球の自然を超えた彼方まで追っているように感じられる。極微な、目に見えない起源へ想像力と感性を誘っていく。
ここにはどのような理屈も説明もない。自らは触手を伸ばして無防備ないのちが生まれ、熟し、消える様と共にあろうとする、詩人の稀有な詩的感性と言葉が、その触手を身体を超えた大きな自然の中に位置付けているのだ。
出産の詩は少なくても、生まれた小さな存在、小さな命への愛をテーマとした詩作品は増え、むしろ現在ではメインテーマにもなっている。動物虐待を始め人間中心文化への批判、そして自然破壊、環境汚染とともに、生きものの命の循環を根本として成り立っている自然の循環の認識が深まってきた結果であるだろう。
震災と放射能汚染でいのちと自然が危機にさらされる経験は、人間が避難した後の空になった村や牧場を逃げ惑う家畜や放置された犬などのペットの具体的な映像で、人間の自己中的文明のを身近に感じる契機となった。
しかし、青木由弥子の詩は、そのようなことは一言も言わない。その表現空間は抱きかかえようとする手や腕を滑り落ちそうな、傷つきやすい生き物のいのちと、それぞれが生き延びようとする不安に満ちた場である自然への敏感な感性で、しかし光に満ちた空気で、満ちている。それが詩の魅力を、そして詩の言葉の力を読者の身体的感覚に伝えている。
水田宗子